|
|
 |

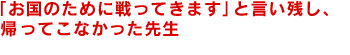
東京は山の手の静かな住宅街で生まれ育った私が、6歳、小学校1年生の12月8日に、日本はアメリカを相手に太平洋戦争を始めました。
おっとり育ってのんびり屋だった私が、その前後で覚えているのは、ラジオが物々しく何回も繰り返して戦争が始まったのを告げていたこと、周りの大人たちがなんとなくいつもよりあわただしく緊張しているように感じたことくらいでしょうか。
3年生のときの担任の先生は、今から思えば19歳くらいだった気がしますが、もっと若かったかもしれません。他の組の子からもうらやましがられるぐらい、元気で颯爽とした男の先生でした。
ある日、先生は五分刈りのような頭髪で現れ、教室の子どもたちに「先生は兵隊さんになって、お国のために戦ってきます。みんなもしっかり勉強するように」と挨拶して、それきり学校には帰ってきませんでした。
校門のそばには奉安殿がありました。何かの時には校長先生が白手袋をして、何か紙を取り出すようになったのはいつのことだったのでしょうか。

奉安殿は天皇・皇后の御真影と教育勅語等が納められた建物。
児童生徒はそこを通るたびに最敬礼をし、
教職員は、これを火災や盗難、災害から守ることが
大事な任務のひとつだった。
戦後、GHQの通達によりそのほとんどは撤去された。
写真は沖縄市美里尋常高等小学校跡地の一角に今も残る奉安殿。
(写真提供:沖縄市教育委員会、沖縄市立郷土博物館)
3年生の後半になると、戦争は子どもたちの日常にも濃い影を落とすようになりました。
学校に行く時も防空頭巾を持っていくようになり、学校では敵機来襲(アメリカの空爆機B29)に備えて、防空頭巾をかぶって机の下に入る避難訓練を、何回もやるようになりました。
「ウー、ウー、警戒警報発令、警戒警報発令……」とけたたましくサイレンが鳴り響くと、近所の者同士が隊列を組んで家に帰ります。
はじめは訓練でしたが、段々「警戒警報」から「空襲警報」に変わり、大人たちの話も「今日はどこそこがやられた」「ここも危ない」とかいう内容になっていきました。
庭には防空壕が掘られました。祖父を中心に、叔父にも加勢を頼んで家族で掘りました。近隣農家の男の人にも頼んだかもしれません。家にある着物などと収穫物を交換してもらう“たけのこ生活”をしていましたし、畑の肥料にするための、便所の肥溜めさらいなどを通じて、定期的に農家との付き合いがありましたから。
3世代の家族6人が入れるように、壕はかなり大きいものでした。細長い穴に階段をつけて(土で段々をつけた)、古畳や盛り土で屋根を作り、床に当たる部分にはすのこが敷いてありました。雨が降ると、すのこの下にピタピタと水が上がってきて、座っている布団を濡らします。
敵機は夜になると現れ、サイレンが鳴ります。隣組のおじさんが「空襲警報発令! 空襲警報発令!」と触れ回ります。空襲は段々頻繁になり、やがては毎晩となります。夜も一度では済まなくなりました。「空襲警報解除」になって防空壕から出ると、寝入りばなに、またやってきます。そのたびに起こされ、暗い庭を防空壕まで行かねばなりません。毎日何度も起こされました。「敵機来襲!」の声もかき消すほどの、焼夷弾投下の金属を引き裂くような音は、もう二度と聞きたくはありません。
ある夜、照明弾が落とされ、あたりがとても明るくなりました。形容しようのない金属音を立てて、焼夷弾が落とされます。いつになく明るかったので、防空壕の外に出たのだと思います。日本軍の高射砲がパンパンと斜めに飛び交い、B29がばらばらになって落ちていくのが見えました。
夜は空襲がなくても、電灯を明るくすることは許されません。灯火管制といって、電球の傘に黒い布をかぶせたり、電球に墨を塗ったり、来る日も来る日も、暗い中で空襲におびえながらの暮らしでした。
東京への空襲が激しくなって、武器を持たない老人や子どもまでもがたくさん死んだり焼け出されたりするようになり、田舎のある人や縁故を頼って疎開する人が増えました。 |
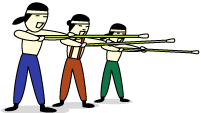 |
このぐらいの頃から、一家に一人は、竹やりの訓練に出なければならなくなりました。女の人たちも空き地に集められ、うちの母親ももんぺ姿で行きました。女の人は普段からもんぺ姿でしたが、着物をほどいて上下おそろいのもんぺにするのが、せめてものおしゃれでした。
もんぺ姿で竹やりを持たされ、号令で「えいっ、えいっ!」と竹やりで敵を刺す訓練をしました。これは在郷軍人という、以前軍隊に行ったことのある近所のおじさんが号令をかけます。
近隣単位で隣組が作られ、訓練を休むとすぐに「○○さんのうちは今日出ていなかった……」と言われるので、「体の弱い人や、歳をとった人のウチは大変だろう」と家で大人たちが話しているのを聞いた覚えがあります。当時は「♪とんとんとんからりっと隣組♪」と調子のよい歌が流行っていました。
「押入れにチョコレートが残っているといいなあ」と子ども心に思うほど、物資が不足していきました。庭はサツマイモや、かぼちゃが植えられるようになりました。子どもも、草むしりを手伝いました。
その頃の子どもの遊びは、縄跳び、おはじき、お手玉、めんこ、まりつき、鬼ごっこなど、今から思うと素朴なものでした。時節柄、陣取りや「開戦」という、敵味方に分かれてじゃんけんをして、陣地や捕虜を取ったり取られたりといった遊びもありましたっけ。あと、母親と一緒に、兵隊さんに慰問袋をつくり、中に入れるお手紙などを書きました。
「♪勝ってくるぞと勇ましく♪」や「のらくろ」など、歌も漫画も軍国調で、国民学校の子どもたちは、「ほしがりません 勝つまでは」「鬼畜米英」と教わりました。
 |
|
 |


4年生になった時、集団疎開が始まりました。我が家には田舎がなかったので、10歳の私も長野県下伊那郡の大きなお寺にお世話になりました。同じお寺に寝起きをともにしたのは、4年生から6年生まで、男の子と女の子あわせて30名くらいだったでしょうか。
いよいよ出発の日。明るいうちは空襲が危ないので、夜になって学校に集合しました。家族ともお別れです。一緒に歩いていた母親がぎゅっと手をにぎってくれたことと、とても緊張していたこと、警報が出たため汽車が途中で止まったことくらいしか思い出せません。
東京の空襲の状況悪化が急激だったせいか、お寺の受け入れ準備が整うまでの何日間かは、近所の農家に分宿させてもらいました。先生と別れて、学年や組も違う子たち4人(だったか)が、村でも一番大きい家に割り当てられました。
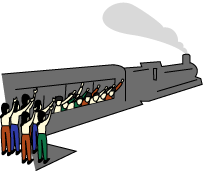
昨日までの東京の生家とは何もかも違います。土間のある暮らし、竃の火、角切りの芋がたくさん入ったご飯。ご飯のあとのお茶碗は自分で洗うようにと言われて、庭先の井戸水の冷たかったこと。外にある便所。下着もはじめて洗いました。洗濯板を使い、固形の洗濯石鹸でごしごしと洗うのです。なれない手は、すぐすりむけました。女手の多い大家族の中で甘やかされて育った私には、珍しいこと尽くめでした。
農家には何日お世話になったでしょうか。いよいよお寺に集められ、集団疎開生活が始まります。東京の学校からは男先生が1人、女先生が1人来て、あとお寺の娘さんが保母先生として面倒をみてくれました。
お寺の本堂が私たちの居場所になりました。夜はそこに布団を敷いて寝るのです。お寺のことですから、周りにお墓もあります。縁側をぐるりと回って真っ暗な便所に行くのが怖いので、おしっこはなるべく我慢しました。
自宅の防空壕も焼夷弾の直撃を受けたので、1年生になったばかりの妹が、あとから疎開に加わりました。「おしっこ」と起こされるたびに一緒に行ってやりましたが、ある夜、あまりの眠さに「自分で行きなさいよ」と邪険にしました。これは今でもかわいそうだったなあと、私のトラウマになっています。
上級生の男の子が「ひとだまが出た」とおどかしますが、その子も怖かったのかもしれません。結局、敗戦までの数ヶ月をそこで過ごし、秋に東京に帰りました。
疎開先ではお寺から村の国民学校に通ったのですが、学校のことはほとんど覚えていません。都会の子をどっと受け入れた村の人たちや、学校の先生たちも大変だったに違いありません。でも、お寺で大勢の子を引き受けた東京の先生は、もっと大変だったことでしょう。男の先生は30代、女の先生は24歳と若かったですし(なぜかここだけはちゃんと記憶しているのです)、保母先生も20代だったでしょう。
疎開生活を送るうちに、子どもたちの頭には黒っぽい色の毛ジラミがわき、体にも白いシラミがたくさんつきました。本堂の隅で、みんなでシラミを採るのです。右手の親指と左手の親指で蚤やシラミをぷちんとつぶすのも平気になりました。寝巻きの浴衣についたシラミが100匹以上いたので、泣き出した子もいました。「かゆい、かゆい」と、みんないつもどこかを掻いていました。 |
 |
食糧事情が段々悪くなって、おやつは寺の庭の青梅が2つだけ配られたりしました。田んぼで取ってくるイナゴをあぶったもの、お蚕さんの繭の中のさなぎを煮たものは、大事な蛋白源でした。山で食べた桑の実がおいしくて、ポケットにいっぱい入れて帰ったら、すっかりつぶれており、紫色が落ちなくてこまった事もありました。20粒くらいずつ炒った大豆も、おやつによく出ました。女の子は小さな袋を作って炒り大豆を入れ、1粒ずつ大事に食べていました。
この頃から、子どもたちの動作が緩慢になってきました。あとから分かったことですが、塩分が不足したためで、箸の上げ下ろしですらのろのろするようになったのです。子どもたちの中にお父さんが軍の関係で、塩の錠剤を持っている子がいたので、大事なおやつの大豆をその塩の錠剤と取りかえっこしてもらいました。
毎日のように缶詰のしゃけが出され、味噌汁の具にもなって出るようになったある日、私はとうとうじんましんになって、体中が蚤に刺されたようにぼこぼこになりました。かゆくてかゆくて仕方がありません。村のお医者さんに、そんなぼこぼこを見せるのが恥ずかしかったことを覚えています。
上級の5年生が学校の宿題で、「ジンムスイゼイアンネイイトクコウショウコウアンコウレイコウゲンカイカスジンスイニンケイコウセイムチュウアイオウジンニントクリチュウハンゼイ……」と呪文のように毎日暗誦しているので、4年生も真似して覚えました。歴代天皇の名前です。もう正確ではないかもしれませんが、今でも口に出すことができます。今は覚えなければならないことでもなかなか脳に定着しませんが、あの記憶力のよかった子ども時代が「もったいなかった」と、ふと思うのです。
 |
|
 |


夏の暑い日、境内の木陰に集められて、玉音放送を聴きました。女の人たちは泣いていました。私は意味がよく分からなかったためでしょう、わりとシラーッとした気持ちで聞いていたような気がします。ほかの子の様子は覚えていませんが、蝉がたくさん鳴いていたのは覚えています。
帰京するまでの記憶は、ほとんど空白です。ただアメリカの飛行機が山間を低空飛行で飛んできて、マフラーや顔が見えるぐらいの近さでしたが、別に怖くはなかったことは今でも覚えています。
疎開から帰ってくると、近くの電車の駅は丸焼けになっていましたが、近所はたいした被害もなく、焼け出された人に較べれば、私はとても幸せな部類でした。
でも、来る日も来る日も、シラミ取りに必死でした。毛ジラミのほうはなかなかしぶとく、髪を洗い、新聞紙を広げた上で、目の細かい櫛ですきました。でも、すいてもすいてもとりきれません。男の子は丸坊主、女の子はてっぺんの髪を残してバリカンで剃られたり、進駐軍の命令(と記憶しますが)で、DDTという粉の殺虫剤を、風船の空気入れみたいなもので頭や背中に吹きつけられたりしました。DDTはその後に毒性が問題になって、使われなくなったと記憶していますが。
学校は国民学校から小学校となり、校門の奉安殿はなくなっていました。初めての給食に出た薄い味噌汁は、豚の脂身の角切りだけが三つ四つ浮いているものでしたが、「こんなおいしいものがあったか」と感激したのを覚えています。
「ギブミー・キャンデー」とともに、「無条件降伏」「マッカーサー」「人間天皇」「民主主義」などという言葉が飛び交いました。
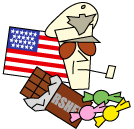
物資は不足し、食料も衣類も配給制で不自由でしたが、そんな大人の苦労にさして影響されず、子どもの私は、おもちゃも、絵本もお菓子もノートも鉛筆もない中でも、楽しい、いわば希望のある毎日でした(紙も布も貴重でしたし、トイレの紙も古新聞をちぎったものでした。特に木綿は貴重品でしたし、今でも捨てられません)。
また家族一緒の生活に戻りました。
学校に行くと、「新しい国のお話」と男女共学が待っていました。新制中学も最初から入ったのは私たちだったと思います。校舎ができるまでは、近くの女学校を間借りしていました。進駐軍から提供されたという新しいノートが配られたときは、とてもうれしかったのを覚えています。
新しい憲法が発布され、「男女同権」「平和・民主主義」は、中学生の身に染み渡りました。それらは子どもの頭ながら、努力さえすれば手に入るものとして定着しました。
しかし当たり前のことながら、それらの宝物は努力さえすれば手に入るというような簡単なものではなく、永遠の、気の抜けない努力の継続によっても、つくるのは難しいものであり、むしろ失われやすいものであることが、最近分かったように思います。
生意気な中学生の私は、「親の世代はどうして戦争を止められなかったか」と、心のうちでいつも批判的でした。今、再びきな臭い世の中になって、私が向けた批判は、私にも私たちの世代にも返ってくると感じています。
戦争をしない国、それを多くの人々が「いらない」と思ったわけでもなく、「どうでもいいや」と思ったわけでもないのに、いや、むしろ多くの人たちが大切なものだと思ってきたはずなのに、どうしてこうなったのでしょうか。ぜひ解答を共有すべきだと思っています。
一人ひとりが自分の意見を持つことを大切にして、お互いのコミュニケーションを深めること、違いを認めながらも合意を作る努力をすること。それは家庭で、職場で、コミュニティで、絶えず鍛えられるべきだったのです。そういう文化が大切ではないかと、私は思っています。
今ある危険な状態を食い止めるための最大限の努力とともに、どうしてこうなったのかを理解するための一歩を、私は子どものころの体験を胸に、これから踏み出したいと考えています。
 |
|