ハリウッドが見せてくれたもの
2月28日(日本時間27日)のハリウッド恒例の祭典「第89回アカデミー賞」の授賞式は、相変わらずの華やかさ。でもなんだか、毎年のお祭りムードの雰囲気とは少し様子が違ったようだ。
最高賞の作品賞は、プレゼンターのウォーレン・ベイティが開封した封筒を受け取ったフェイ・ダナウェイによって『ラ・ラ・ランド』(デイミアン・チャゼル監督)と読み上げられたのだが、なんとこれが主演女優賞の封筒だったらしく、作品賞は実は『ムーンライト』(バリー・ジェンキンス監督)だったという大ハプニング。さすがに、蒼白になったウォーレン・ベイティが「これは冗談でやったんじゃないんです」と大慌て。
まあ、長いアカデミー賞の歴史の中でも、最高賞の作品賞を間違えて発表するというのは初めてのこと。政界だけではなく、ショービズの世界でも大混乱が起きている象徴のような場面だったという。
でも、プレゼンターがこのふたり(アメリカン・ニューシネマの傑作『俺たちに明日はない』の主演)だったというのも、なかなか洒落ている。
それはさておき、今回のアカデミー賞でぼくが注目したのは、外国語映画賞の部門でイラン映画の『セールスマン』(アスガー・ファルハディ監督)が受賞したことだ。実は、ファルハディ監督は、この日の授賞式会場にはいなかった。彼は、トランプ大統領の移民政策に対する抗議の意思を示すために、授賞式には出席しないと事前に公表していたのだ。
ファルハディ監督は「自分と敵というふたつに分断することは、恐怖や戦争へのまやかしの正当性を生みだすのです」と、授賞式へ寄せたメッセージで語っていた。さらに「私の国と他の6カ国の人たちのアメリカへの入国が、非人道的な大統領令によって禁止されたことへの抗議」だとも説明している。
ハリウッドは、時として政治的な意思を鮮明にする。今回も、司会者や他の俳優たちが「私たちを分断するあらゆる壁に反対する」と述べるなど、反トランプの様相を色濃く反映した。
このイランの『セールスマン』の受賞にも、ハリウッドの政治的傾向がにじんでいる。その傾向を批判するつもりは、ぼくにはまったくない。逆に、映画というショービズ世界から、時の最高権力への批判が鮮明に表明されることこそが、表現の自由を守るために必要だと考える。
政治的主張が色濃く出た授賞に、2003年の『ボウリング・フォー・コロンバイン』(マイケル・ムーア監督)の長編ドキュメンタリー賞がある。ムーア監督はこの授賞式で、イラク戦争へ突き進んだブッシュ大統領を、口を極めて非難した。会場は賛否の声で騒然となった。これなどは、まさにイラク戦争に反対する映画人が多かったことの表れだったと言える。
このところのハリウッド映画が、アメコミ(とくにマーベル・コミック)原作の大げさなスーパーヒーローものに席巻されているのはつまらないけれど、やはりこういう時には底力を見せるようだ。
授賞式直前に行われた集会も異例だった。朝日新聞デジタル(25日配信)がこう伝えていた。
ジョディ・フォスターさんやマイケル・J・フォックスさんら米国の俳優らが24日、米西部のビバリーヒルズでトランプ政権の移民対策に反対する集会を開いた。
AP通信などによると、企画したのはタレント事務所「ユナイテッド・タレント・エージェンシー」(UTA)で、事務所前に約1200人が集まった。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズで知られるフォックスさんは「移民を追い出すことは人間の尊厳への攻撃だ」と発言。カナダ生まれの自分が米国籍を取るまでに8年間かかった体験を語った。フォスターさんはこれまで政治活動を避けてきたが、黙っていられなくなったといい、「歴史で唯一の時。闘う時だ」などと訴えた。(略)
UTAは、25万ドル(約2800万円)を人権団体「米自由人権協会(ACLU)」などに寄付すると表明している。
今さら、日本の芸能界と比較しても仕方ないけれど、この彼我の差はいったいなんだろう…としばし考え込む。日本の「芸能事務所」に、そんな度量があるか!?
マッカーシズムとハリウッド
前にも書いたけれど、アメリカの映画界には極めて厳しい「負の遺産」がある。それは歴史的敗北と言っていいものだった。
1940年代後半~50年代にかけて、全米を熱狂的に席巻した「マッカーシズム」である。少しでも共産主義的傾向があると見做されれば、追放の憂き目をみる。それは、政府職員から始まり、やがてマスメディアや芸能界へまで波及した。当初は「赤狩り」として共産主義者や社会主義者らが対象とされたが、次第に自由を擁護しようとするリベラル派にまで、マッカーシズムはその牙を剝いたのだ。
日本のいわゆる「ネット右翼」が、いまやリベラル派の人々にも罵声を浴びせかけるのとよく似ている。歴史は繰り返す。
特に娯楽の帝王の座にあったハリウッドは、かっこうの標的となった。あのチャップリンやジョン・ヒューストン、ウィリアム・ワイラー監督らまでが調べられ、マッカーシー議員が主導する「非米活動委員会」が猛威を振るった。その中で、委員会への召喚や証言を拒否したのが「ハリウッド・テン」と呼ばれた脚本家のダルトン・トランボら10人であった。彼らは、有罪を宣告されて、映画業界から追放されたのだ。
(なお、この件に関しては、「風塵だより 105」で触れた映画『トランボ ハリウッドが最も嫌った男』をぜひ観てほしい)
マッカーシズムが標的とした人たちとして「ウィキペディア」は次のようなハリウッド人名を挙げている。グレゴリー・ペック、ジュディ・ガーランド、ヘンリー・フォンダ、ハンフリー・ボガート、ダニー・ケイ、カーク・ダグラス、バート・ランカスター、ベニー・グッドマン、キャサリン・ヘプバーン、フランク・シナトラ…。
逆にマッカーシズムに協力した人名は、エリア・カザン、ウォルト・ディズニー、ゲイリー・クーパー、さらには後の大統領ロナルド・レーガンなど。
まさに、人それぞれである。
こういう背景があるからこそ、今でもハリウッドには、時の権力への批判の傾向が残っていると言われるのだ。むろん、そうではないショービズ関係者も少なくないけれど。
何が日本の芸能界を支配しているのか
ひるがえって、日本の場合はどうだろうか。
日本の芸能界は、実は「テレビ局支配」なのだ。映画界がハリウッドのような地位を占めていない。では、どうなっているのか?
タレント(俳優ではなくタレント)は、所属する芸能事務所の意向に金縛りにされているが、その芸能事務所を金縛りにしているのがテレビ局であり、さらにそのテレビ局を影響下に置いているのが電通や博報堂といった大手広告代理店であり、さらにさらに広告代理店そのものが、実は政権与党の手のひらにある、という複雑な構造なのだ。
政権→広告代理店→テレビ局→芸能事務所→所属タレント…。
こういう幾重にもがんじがらめの構図の中で、タレントが自由に発言したり行動したりすることは、事実上不可能だろう。言いたいことを自由に言える俳優など、超大物を除けば、ほとんど数えるほどしかいない。そんな人たちの顔は、すぐに思い出せる。ごくごく少数なのだから。
だが、そういう人たちさえ、あからさまな政権批判はしないし、もし少しでも批判の気配があれば、いわゆる「ネット右翼」の攻撃にさらされ、炎上してしまうケースも多い。
アメリカのように、有力俳優たちが自らエージェントを雇う(選ぶ)というシステムとは、まったく違うのだ。だから、日本では大きな影響力を持った人たち(とくに、頻繁にテレビに顔を出すような有名な人たち)は、テレビから消されることを恐れて、政治向きには口を出さない。あの石田純一さんの例をみればすぐに分かる。政治向き発言は、ほとんどが時の権力者におもねるものに限られる。
テレビのトーク番組の中の政治的発言が、ほとんど現政権寄りなのは、少し気をつけてみていれば、一目瞭然だろう。あの芸人やこのタレント…。
日本の芸能界は、かつては「地方興行」で成り立っていた。地元を仕切る親分たちがいて、仁義を切らなければ地方都市での興行は打つことができなかった。したがって、芸能界とある種の勢力とは切っても切れない縁で結ばれ、さらにその勢力は地方政界とつながっていた。
その名残が、現在でも政界と芸能界のつながりとなって、時折その一端を垣間見せることがある。安倍首相を囲んで、まるで閣僚たちのようにひな壇で嬉しそうに撮影されていた芸能界の有力者や出版界の仕掛け人たちの写真を、見たことがある人も多いだろう。
その持ちつ持たれつの関係は、いまも健在なのだろう。しかし、持ちつ持たれつ、とは言いながら、権力側と芸能界が「対等」だったことなどない。日本の場合はいつだって、奉仕する側とされる側という関係でしかなかったのだ。
ノーベル文学賞受賞者の語ったこと
2015年に著書『チェルノブイリの祈り 未来の物語』(岩波現代文庫、1040円+税)でノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチさんが2016年暮れに来日した。その折、ぼくが住んでいる府中市にある東京外国語大学で講演をした。
その時、とても印象的な言葉があった。「日本には抵抗の文化がない」という言葉だった。東京新聞(2016年11月29日付)を引用する。
福島で目にしたのは、日本社会に人々が団結する形での『抵抗』という文化がないことです。祖母を亡くし、国を提訴した女性はその例外です。同じ訴えが何千件もあれば、人々に対する国の態度も変わったかもしれません。全体主義の長い文化があったわが国(旧ソ連)でも、人々が社会に対する抵抗の文化を持っていません。日本ではなぜなのでしょうか…(略)
これは「日本文化」などと称するものへの根源的な批判だと、ぼくは思う。激しく厳しい批判だと思う。「旧ソ連と同じ」とまで言っているのだから。
実は、いま日本という国の中で「抵抗の文化」が残っているのは、沖縄だけなのかもしれない。
これからの「日本人」が作りださなければならないのは、まさに、この集団としての抵抗、まるで祭りのような「一揆」である。その祭りを、ハリウッドは少しだけだけれど、見せてくれたのだ。





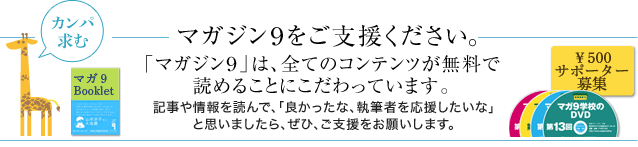


「抵抗の文化」が日本にはないというようなことは、竹内好も言っていたことを思い出します。日本では庶民の批判が末端の官僚(公務員)攻撃になるけれど,政治の中枢へは届かない構造になっている。そのようなことも彼は言っていました。なぜそうなるのか? いまだ明らかになっていないような気がします。抵抗の契機・核になるものは何なんでしょうか。沖縄の戦いに学ぶとしたらこの辺のことを深く考えるべきでしょう。
私達は憲法施行70年というが、民主主義制度をなぜ導入したのか。民主主義の危険性とは。人権保障の重要性。等を学校教育で学んだことがない。今も変わりはないだろう。学校、親から教えられたのは、人と同じように生きるメリットであり、従順さである。不確かな時代、不透明感が増す時代。その傾向は更に強まっているように映る。
この状況は、高齢者は孤独に怯え、若者は将来に怯え、総人口「考える」ことを放棄したとも映る。これは、「自信」を失ったとは違う。自信を失ったとは自信があった人の話である。もともと自我に弱い国民性、この段になって「自立心」の脆弱さが顕在化したに過ぎない。
そんな中、「抵抗の文化」を作る。この文化が根付かないと歴史は繰り返すことになる。これは歴史の教訓である。しかし、学校教育を通じては期待できない。少数を恐れず、一人一人の活動に待つしかないのでは。
ところで、いわゆる有名大学で学ぶ諸君に聞きたい。君たちは、その素晴らしい頭脳を何の為に使おうとしているのか。 地球単位で考え、複眼的視点で考え、そして、実践する。そのようなものに使って欲しいと願っている。
先週、東京大学地下中央食堂で昼食を食べてきた。これは永年の念願であった。孫を見学に連れて行くための準備でもあった。とても考えさせられるものがあった。