沖縄・普天間基地へのオスプレイ配備をめぐる抵抗運動の様子や、新たな米軍基地建設計画が進む沖縄本島北部・東村高江の住民たちの闘いを描いたドキュメンタリー映画『標的の村』を撮影した三上智恵さん。辺野古や高江の 現状を引き続き記録するべく、今も現場でカメラを回し続けています。その三上さんが、本土メディアが伝えない「今、何が沖縄で起こっているのか」をレポートしてくれる連載コラムです。不定期連載でお届けします。
第37回
死者の声を聞くこの島で生きるということ
辺野古のゲート前闘争が始まってから二度目の正月を迎えた。前回の正月は、なんと言っても歴史的な知事選の勝利に加え、「辺野古基地建設反対」から「推進」に転じた自民党議員を全員選挙区で落選させた衆議院選挙の直後だっただけに、座りこみテントは大晦日からどんちゃん騒ぎだった。みんな口々に「いい正月~!」と勝利を確かめ合った。
「いい正月」という言葉はもちろん、その前年の暮れに政府の懐柔策に乗って埋め立てを承認した前知事が「これでいい正月が迎えられる」と言って県民を唖然とさせた、あのフレーズへのリベンジである。しかしあれからの一年。二つの選挙の完全勝利も無かったことのように、2015年、政府は辺野古の基地建設を加速させた。去年の終わりには、翁長知事の「埋め立て承認撤回」を無効にする裁判まで国が提起した。県も抗告裁判で国を相手取って司法の判断を仰ぐ。県は国と全面対決する覚悟だが、ボーリング調査もほぼ終わりいよいよ実質上の埋め立て開始もカウントダウン状態に入った。
そんな年越しで、現場はどんなに厳しい表情で新たな年を迎えるのか、とおもいきや、動画を見て欲しい。大晦日が明けてみれば去年の三倍近くの人が辺野古の浜に押し寄せていた。みんなの表情は底抜けに明るい。鮮やかな衣装に金の扇で舞う「かぎやで風」の人数も、去年より格段に増えた。そこに真っ赤な初日の出。朝日を浴びた踊り手の誇らしげな表情。
政府が容赦なく北風を強めれば強めるほど、より多くの県民が輪に加わり、より強い力で腕を組もうとする。向かい風が強く、道が険しいからこそ体力がついた。それでも負けなかったことを喜び合うことがエネルギー源になった。何のことはない。シンプルにいえば、現場はパワーアップしたのだ。
辺野古の浜は東に開けているので初日の出の人気スポットだが、700人もの人が元旦の辺野古の海岸を埋め尽くしたのは恐らく初めてだろう。ラインダンスで全員手を繫ぎながら輪を拡げていったら、波打ち際まで来てしまった。初日の出が拝めたのも、ここ数年なかったことだった。なんとも幸先のいいスタートになった。
気になったことと言えば、初日の出を拝む神事の時に、祝詞を上げてくださった方の横で文子おばあの顔色がみるみる悪くなっていったこと。またなにか、普通の人には見えないものが見えたのだろうか? と私はとても心配になった。
また、というのは、数年前のまさに同じ初日の出の神事の際に、おばあは突然大きな龍が現れて辺野古上空に去っていったのを見たという。そして龍の頭の上に文子さん自身が、あぐらをかいて白い着物をつけて乗っている様子がはっきり見え、怖くなったと話してくれたことがあった。白い着物、というのは沖縄の村々で神事に携わる女性が身につけるもの。文子さんは元々、シャーマンの素質のある女性だった。若い頃から不思議な体験をたくさんされてきたようだが、いくら自分にしか見えないとはいえ、龍を従えて天に昇っていく自分の姿が辺野古の浜に現れたのだから、それは度肝を抜かれたことだろう。それ以来、浜には近づいていなかった文子さんだが、顔をしかめ、服で半分顔を隠していたので、私たちも一瞬青ざめてしまった。
あとで聞くと、神事が始まって間もなく焚いてもいないお線香の臭いがしてきて「この匂いは嗅いではいけない」と本能的に思って服で顔を覆って目をつぶって凌いでいたそうだ。お線香の匂いというのは、死者の登場を表す。私も一応シャーマニズムの研究者の端くれとして大学で民俗学の講義を持って12年になる。ユタやツカサなど霊的な能力が秀でている女性達は、神霊の姿を見たり、その声を聞いたりするわけだが、見る・聞くだけではなく、匂いがしたり、悪寒やしびれ、寒くなったり発汗したり、五感を使ってその存在を認識するとされている。
匂いで言えば、例えば白粉の匂いがしたら不幸な遊女の霊が来ていたり、食べ物の腐った匂いで悪霊が通過したことを知ったり、お線香の香りは死んだ人たちの存在を知らせるものだと言われている。もちろん普通の人には見えないし匂いもしないのだが、敏感な人がその場に複数居て同時にそれを確認したという話はよく聞くところだ。ただ、その存在に気付いた数少ない人間に対し、霊的な存在がなんらかの助けを求めてくると厄介なことになるので、文子さんはあえて顔を覆って匂いにも気付かない、何も見えないという形でガードをしたのだろう。
急に怪しい話になってきたと思う方も居るかも知れない。がしかし、私は何も幽霊や龍が沖縄にいます、などということを言っているのではなく、この島の人々が目に見えない世界をどう具体的に理解しているのか、どんな神観念や霊魂観、他界観を共有しているのかを理解するのが民俗学だからデータを紹介しているだけだ。
実際にことしも沖縄の大学生140人のクラスでアンケートを採ったところ、「マブイグミ」、マブイ(魂)を込める=魂を本人のところに戻してあげるという沖縄ではポピュラーな儀式について、それをやってもらったり、やってあげたりした経験を尋ねたら、ある人が7割以上いるのだ。島の言葉もほとんどしゃべれない18や20歳の若者でも、幼い頃、祖母や母にマブイグミをしてもらった経験は多くの学生が持っている。また成長して友達が事故にあったらその場でマブイグミをした、など人の魂を有るべき場所に戻すという儀式はごく一般的に沖縄社会の中に息づいている。
魂は不安定で、驚いたりくしゃみをしたりしたタイミングで飛び出してしまう。そういう感覚を今も共同体の中で共有し合っている中だからこそ、招かれざる死者の魂が、見えないけれどこの世に跋扈しているという捉え方も決して特殊ではない。
実際に、映画のシーンにもなった文子おばあと南部に行ったときの撮影で、戦争中に友達のお母さんの遺体を埋めたという場所に来たときに、おばあは急に頭を振り「だめだ!」といった。全く違う死者の霊が出てきたといって生唾を吐いて苦しそうにしていた。きつい体験をした場所に来るだけでも大変なのに、霊的な能力のおかげで死者の姿まで見なければならない。それは裏を返せば、おばあにとって死んだ人の存在は、過去でも無でもない。常にその方々の声や気配を感じる中に日常があるということだ。毎年旧盆の時に自宅に戻ってくるご先祖様のためにご馳走を作り、浮かばれない霊のためにエイサーを奉納する。そういう肌感覚で生活してきたからこそ、山城ヒロジさんもお盆の時に沖縄の警察官に対して、こんな風に訴えていたのだろう。
「うやふぁーふじが泣ちょーんどー!(ご先祖様が泣いて居るぞ)」「先祖の土地を金に換えて、基地を造ったのは私です、と自分の子や孫に言えるのか? 今夜、仏壇の前でご先祖さまに合わせる顔があるのか、バカタレ!」
沖縄で育った若者なら、この言葉は応えるはずだ。人間は自分が生まれてから死ぬまでの短い期間、単体として存在するのではなくて、先祖から受け継いだものの上に生き、また子孫に宝を残してこそ生きた甲斐がある。だからいい加減なことをすれば死者は死後も黙ってないで文句を言うだろうし、未来の子孫も自分を責めるだろう。そうやって死者の声を聞くこの島で、目に見えないものへの畏怖や畏敬の念が社会規範を作り上げてきた。
何が何でも基地を造ると権力をむき出しにしてくる政府を前にしても、あきらめず、揺らぐことなく前を向いていられる秘訣は、何も歌や踊りや楽天的な性格ばかりではない。先祖に対する感謝とバトンを受け取った責任、子孫への慈しみと最低限の義務を果たすことそれが生きる意味であり喜びなのだから、だから強いのだ。自分の使命が明確に解っている人間は、たとえそれが困難な道であっても揺らがないものだ。
沖縄戦で生き残ってしまったことの意味を考え続けた文子おばあ。ゲートの正面に立ちはだかる彼女の背中を押しているのは、たくさんの死者たちなのかも知れない。そして、生きるとは過去を背負い未来へ繫ぐことだから、そういうものなのだと受けて立つ構えの人々が、おばあだけでなくたくさん居るのが沖縄の強さなのかも知れない。





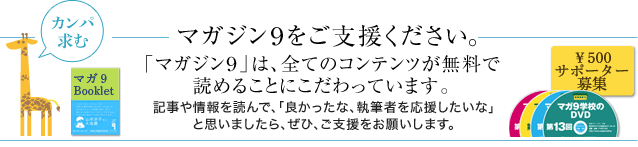


辺野古のゲート前に行くと、たくさんの方がそれぞれの思いを話してくれますが、なかでも印象に残ったのが、まさに「先祖から受け継いだ」「未来の子どもたちのために」というフレーズでした。沖縄の人たちは、長い時間感覚のなかで、基地の問題をとらえているんだと感じたのです。そういえば私も子どもの頃は、「悪いことをすれば、誰もみていなくてもバチがあたる」というようなことがいわれていました。いまの子どもたちはどうなのでしょうか? 私たちの社会は、数字や目に見える利益、「いま」や「自分」のことばかり考えすぎて、かえって息苦しく不安になっているのではないかと考えさせられます。
御意…ありがとう三上さん。