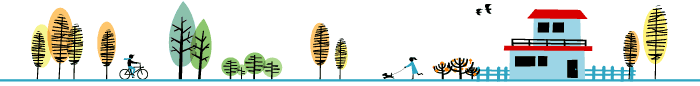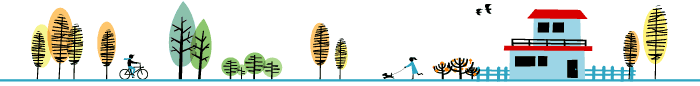| 6月30日、ドイツ最大の難関と言われた対アルゼンチン戦。アルゼンチンに専制を許し、75万人が集ったパブリック・ビューイングは一時沈黙。終了10分前にクローゼがゴール、さらにレーマンのスーパーセーブによる勝利で湧きに沸くドイツ・サポーターたち。後ろの3人はヨークシャーから来たイングランド・ファン。いいサッカーに国境や国籍なんて関係ない! |
|
英雄はいらない
「ドイツとアメリカの経営者の違いとしてわかりやすい例を挙げるとすれば、いわゆるビジネス成功本の人気の有無でしょう。ドイツの経営者がアイアコッカ(元クライスラー社長。1980年代に経営難の同社を立て直した)の自伝みたいなものを書いたら、軽蔑されこそすれ、尊敬されることはありません」
いまから4年ほど前、ドイツの企業風土について話を聞くため、フリードリヒ・シラー大学で経営心理学を教えるドイツ人教授と会ったとき、彼はこう切り出しました。
ドイツの書店には経営者によって書かれたビジネス成功本はあまり見かけません。サクセス・ストーリーは会社で働く者みんなで作り上げるもの。会社トップが1人成功をひけらかせば、社員の反発を買うし、そうした出版物は読者から冷たい目で見られる。ドイツの経営者にはそれがわかっているというのです。そして、教授はさらに言いました。
「1930年代初め、町には失業者があふれて、(当時のドイツの通貨)ライヒスマルクはハイパーインフレで紙屑同然。国民経済が破綻寸前にあったとき、ドイツ国民はヒトラーを救世主とみなしたのです」
国民のなかに英雄待望論が漂うのは危険の兆候です。ナチスドイツを逃れ、アメリカに亡命していた劇作家ベルトルト・ブレヒトが当時書いた『ガリレイの生涯』という戯曲には「英雄を必要とする国は不幸だ」というセリフがありました。 |
 |
 |
謙虚なFW
ドイツの企業風土には突出した個人の存在を好ましいものと見ない傾向があるとのことですが、たとえばFWミロスラフ・クローゼのプレーに、なるほどと思わせるものがあります。
2002年日韓大会1次リーグの初戦、サウジアラビアとの試合でクローゼはハットトリックを決め、鮮烈なW杯デビューを果たしました。でも、私がもっとも印象に残ったのはその試合ではなく、同リーグ最終戦のカメルーンとの試合。後半早々、敵陣ゴールの直前まで、ドリブルで持ち込んだ彼が、併走する同じFWのボーデにパスしたシーンです。ボーデは難なくシュートを決めました。
元名古屋グランパスの監督で、現在イングランド・プレミアリーグのアーセナルを率いるアーセン・ヴェンゲルは「同じような状況でロナウドがボールをもっていたら、彼は間違いなく自分でシュートを打っただろう」とコメントしています。日本のFWならまだしも、初戦でハットトリックを決め得点王を射程内に入れている彼であれば、自分で決めてもぜんぜんおかしくない場面です。それでもクローゼはチームのバランスを考えました。
それから4年。クローゼはずいぶんと逞しいストライカーとなりましたが、今回の決勝トーナメントの対スウェーデン戦でも、FWポドルスキに同じようなアシストをしたように、プレーの意識は変わっていないようです。ただし、これは同僚に「花をもたせ」て、自分は身を引くといった類のものではなく、ベンゲルが言うところの「コレクティブ」なプレー、つまり組織の力を最大限発揮させるための行為なのでしょう。その分、チームとしては意外性のあるプレーが少なくなり、観ていて面白みに欠けるところもあるのですが。
思い出すのは2001年2月、日韓大会に先立ってパリ北部サンドニで行われたフランスとの親善試合です。MFジダンの華麗なプレーの前にドイツが1対0で敗れた翌日、ドイツ紙は「芸術家が職人を打ち負かした」という見出しを掲げました。 |
 |


ドイツ人の女の子
(7/2) |
戦う集団の条件
先の教授との会話では、ドイツ・ダイムラーベンツと米国クライスラーの合併もテーマに上りました。
「ダイムラークライスラー」という世界第3位の自動車メーカーが誕生したのは1998年。同社の管理職の社内公用語は英語となりました。相手を呼び合うときは米国流にファーストネーム。ダイムラーとクライスラーの社長はお互いを「ユルゲン(・シュレンプ・ダイムラー社長)」「ボブ(・イートン・クライスラー社長)」と呼んでいたそうです。基本的に「〜さん」と丁寧語を交わすドイツ大手企業の社員は戸惑いましたが、彼(女)らを驚かせたのは、アメリカ人社員の気さくな言葉遣いの裏に、厳然と存在する上下関係だったといいます。
たとえば、社員食堂。シュトゥットガルトのダイムラー本社のそれはひとつで、原則として社長から整備士まで全員が同じメニューから選ぶのに、アーバンヒルズのクライスラー本社では、社員食堂が役職によって細かく分けられていたのです。社員食堂のランク付けは報酬が反映されています。合併直前のダイムラーベンツ取締役10人の年間報酬が約1100万ドルに対して、クライスラー社長イートン1人のそれは610万ドルでした。
ある集団のなかでに、これだけ大きな格差が存在する、(ドイツでは)競争のモチベーションは生まれないと教授は言います。サッカーに話を戻していえば、戦う集団にはなりえないということでしょう。「職人」たちには「職人」たちなりのチーム・スピリットがあるのです。
教授の勤めるフリードリヒ・シラー大学は旧東ドイツ、チューリンゲン州イエナ市にあります。ドイツのマイスター(職人)が造り上げたカメラ・レンズで有名なカール・ツァイス社のある10万人程度の小さな町。教授はデュッセルドルフ出身ですが、旧西ドイツの大手企業が英米流の株主を重視した経営手法を取り入れているのに比べて、互助的な意識をもった古きドイツの企業風土が残る旧東ドイツ企業に好意を抱いているようでした。 |
 |

|
国境の小さな町
「職人」チームの主将、MFミヒャエル・バラックは旧東ドイツ出身です。彼はイエナから約200km東、ポーランドと国境を接するゲルリッツという町で生まれました。
ナイセ川という小さな流れが両国を隔てています。戦前のドイツの領土は、この川のもっと東まで広がっていましたが、敗戦後、対東側国境はここまで後退しました。それはヒトラーとスターリンによって分割され世界地図から消滅、戦後復活したポーランドの国土が西へシフトしたことも意味しています。
ポーランドは2004年5月にEU(欧州共同体)に加盟し、実質的に独ポ間の国境はなくなりました。私が訪れた2002年の冬には国境検査が行われていたものの、たいしたチェックもなく、ほとんどフリーパス。ナイセ川に架かる橋を渡って、向こう岸のポーランドの町、ズゴルジェレツに入っても、言葉と通貨(ドイツはユーロ、ポーランドはズロチ)を除けば、町の雰囲気はほとんど変わりません。
「そりゃそうです。だってむかしはひとつの町だったんだから」と当時のゲルリッツ市長が言いました。
「いまでは、ゲルリッツにポーランド人の子供が通う幼稚園もあるし、1カ月に1組の割合でドイツ人とポーランド人が結婚しています。ヨーロッパが統合されれば、ゲルリッツとズゴルジェレツに2人の市長はいらなくなるでしょう」 |
 |


未来のサッカー選手たち
W杯と同時平行で、世界の子供たちを対象にしたアディダス主催の「+ challenge」フットサル世界大会が7月4日まで行われました。各国の子供たちがお揃いのユニフォームに身を包み、楽しそうに、でも真剣にプレーしていました。ここから世界に名を馳せるプレーヤーが誕生するのでしょうか。
|
|
統一ドイツを超えたナショナルチーム
今回のW杯をドイツが制すれば、統一ドイツとしては初めてとなります。いまだ東西格差が縮まらぬ厳しい経済情勢のなか、優勝は第2の「ベルンの奇蹟」になるかもしれません。旧東ドイツ出身のバラックが主将ならばなおさらです。
準決勝のアルゼンチン戦。起死回生の同点ヘッドを決めたクローゼは、ガッツポーズとともに胸で十字を切りました。ブラジルやスペイン、ポルトガルなどカトリック教徒の多い国の選手にはよく見られますが、政教分離が社会で浸透しているドイツの選手には珍しいしぐさです。
クローゼの両親は1980年代後半にポーランドからドイツへ移住しました。彼が9才のときのことです。ポーランドはヨハネ・パウロ2世・前ローマ法王の故郷でもある、カトリック系の国。胸で十字を切るのは、クローゼ家では日常的な行為なのでしょう。
ドイツ代表を見れば、もう1人のFWルーカス・ポドルスキもポーランド移民の子供です。また、同じくFWゲラルト・アサモアはガーナ出身、MFダヴィッド・オドンコルはドイツ生まれですが、父親はガーナ人。ドイツ代表内は、統一後もヨーロッパ共通通貨(ユーロ)の導入、EUの拡大という大きな変化のなかで、確実に「多民族」化が進んでいます。ジダンやアンリなど移民2世が中心となる、お隣のフランス・チームのように。
ところで、ゲルリッツは、ドイツ有数の古都ドレスデンから自動車で1時間足らずのロケーションということもあり、観光客の誘致に努力しています。
「知名度はまだまだ」と言う市長さんは観光メッセなどでドイツ国内を駆け回っているそうですが、
「そこでわが町の宣伝を始めるでしょう。すると相手の人が言うんですよ、『ゲルリッツというところから来られたのですか。ドイツ語がお上手ですね』って。私たちを外国人だと思ってるんだ」と言って市長さんは大きな声で笑いました。
司令塔(バラック)が生まれた町はドイツの辺境、ストライカー(クローゼ)の故郷は国境を越えたさらに東にある――これが現在のドイツ・ナショナルチームなのです。
(文・芳地隆之 写真・富田那渚) |

芳地隆之●ほうち たかゆき
1962年東京生まれ。 大学卒業後、会社勤めを経て、東ベルリン(当時)に留学。東欧の激変、ベルリンの壁崩壊、ソ連解体などに遭遇する。ベルリンの日本大使館勤務を経て、現在はシンクタンクの調査マン。著書に『ぼくたちは革命の中にいた』(朝日新聞社)『ハルビン学院と満洲国』(新潮社)など。
富田那渚●とみた なお
神戸市出身、現在、ベルリン自由大学で環境問題を専攻。日独通訳の資格も取得し、学業と仕事の二束のわらじ生活。ベルリン市公認の「2006年ワールドカップ日本人アテンドスタッフ」として、ベルリンを奔走するなか、相手の懐にすっと入っていくキャラクターで、各国の人々の表情や街角に残る歴史の断片をカメラに収めてくれました。 |
|
 |



ぜひ、ご意見、ご感想をお寄せください。 |