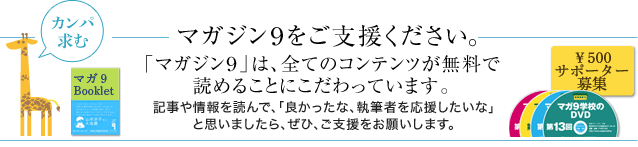2013年12月14日@渋谷校
「けんぽう手習い塾」でおなじみの伊藤真さんが主宰する、資格試験学校の伊藤塾では、
法律家・行政官を目指す塾生向けの公開講演会を定期的に実施しています。
弁護士、裁判官、ジャーナリスト、NGO活動家など
さまざまな分野で活躍中の人を講師に招いて行われている
「明日の法律家講座」を、随時レポートしていきます。
なおこの講演会は、一般にも無料で公開されています。

講師:西口 元氏
(早稲田大学大学院教授、元裁判官)
講師プロフィール:
国家公務員上級職(甲種)及び司法試験合格後、早稲田大学大学院法学研究科博士課程(民事訴訟法)修了。その後、裁判官に任官し、検事に転官した後、人事院在外研究員として、アメリカ(ジョージタウン大学ロースクール等)において、集団訴訟の研究に従事する。その後、裁判官に再任官し、東京地裁判事、大阪地裁判事、東京高裁判事等を経て、2013年3月に依願退官。現在は早稲田大学大学院教授を務める。Nコート(対話・対席・対質を基本とする訴訟運営)の提唱者として有名であり、旧態依然とした民事訴訟の改革を唱えてきた。編著書として、『現代裁判法体系13民事訴訟』(新日本法規)、『フランチャイズ・システムの法律相談』(青林書院)等多数。
■不思議だらけの日本の裁判
裁判では、一般の常識で考えると不思議なことがたくさんあります。例えば、主文読み上げのみで理由を告げずに数秒で終わる「セレモニー判決言渡し」です。また、判決では「社会通念」を多用しますが、何が「通念」なのか基準を示さないので、説明になっていないのです。
私はこのような法曹の常識に強い違和感を覚えます。先輩方のやってきたことは必ずしも正しいわけではありません。本日はそのような視点から日本の裁判、主に私が関わってきた民事裁判のあるべき姿について、みなさんとともに考えていきたいと思います。
■民事裁判の現状
多くの弁護士が関わる民事訴訟の基本は単純で、「争点整理」と「証拠調べ」をして「和解」、もしくは「判決」を下すという流れが一般的です。
その民事訴訟には、大きく分けても4つの不思議があります。1つ目は「口頭弁論」の際に行われる「準備書面交換儀式」です。なぜ3分で終わる儀式のためだけに、双方の当事者がわざわざ出頭しなければならないのか? 書面の交換だけなら郵送で十分なので、時間と金の無駄です。
2つ目は「証拠調べ」で、ほとんど全ての事件で証人に対して一問一答式で尋問する「交互尋問」が行われます。しかし、事件の性質や証人の性格が違うのに、ワンパターンな進め方で良いのでしょうか? 事件や証人の差に応じて、調べ方を工夫すべきです。
3つ目は「和解」です。和解は「交互面接方式」で双方が、相手のいない所で裁判官と面接して意見を述べます。相手のいない所で片方の意見を聞くのはおかしくはないでしょうか?
4つ目は「判決」です。2年近くの裁判の結果出される判決が、数秒の主文のみの朗読で言い渡されます。当事者が出頭しているのに、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする」とだけ読み上げて終わるようなものが多いのです。
日本はこんなおかしなことを100年も続けてきました。法文上、日本の裁判はすべて「間接審理」といって、当事者間で弁論せず、すべて裁判官を通して審理するスタイルです。原告が被告の主張に反論するときも、「裁判官、被告は嘘を言っています」などと、裁判官を通してやりあいます。日本では、意見は書面に書いているので議論する必要はないと考える弁護士が結構多いのですが、当事者間で自由に議論できないということは、当事者が裁判所に依存して自立していないのと同じことなのです。
日本の民事訴訟法の基となったのは、ドイツの民事訴訟法です。しかしドイツでは、当事者と裁判官の3者で議論するという規定があります。この点は日本との大きな違いです。
■Nコートの挑戦
私が提唱してきたNコートは、裁判で「対話・対席・対質を基本とする訴訟運営」を進めていこうというものです。NコートのNは西口のNでもありますが、ナチュラル、ニュートラルのNをとりました。特にナチュラル、自然体で裁判ができるというスタイルをめざしてやってきました。
私がまず力を入れたのは、弁論の活性化です。私の場合、弁論に30分を費やしました。日本人はディベート形式の議論が苦手ですが、日常会話から始めると、話しはじめるようになります。弁論する際に、最も大事なのは主張です。書面で書く際は、ありとあらゆる主張を書くので、読んだだけではどこが一番大事なのかがわからない。でも、法廷で弁論すればあまり恥ずかしいことは言えないから、重要な主張に絞られてきます。そうなると話が早い。「争点整理」では6回も期日をかけるのが通例ですが、30分間きちんと弁論できれば、6回もやる必要はなくなります。
2つ目は「証拠調べ」の工夫です。日本では、弁護士が事前に証人に面接して打合せをするということを日常的に行っていますが、ドイツでは禁じています。証人は法廷で記憶にあることをしゃべればいいのであり、事前打合せをする必要はないという考え方で、私もそう思います。事前に法律家と会うと、いろんなことを言われて、証人が影響を受けるということはあるでしょう。
一方アメリカでは弁護士が証人に事前面接することは許されています。アメリカの裁判はガンマンの一騎打ちみたいなもので、お互いに手の内を全部見せあってやりあうスタイルです。その前提には「中立な証人はいない」という発想があります。敵か味方かしかいないので、最後は裁判官に判断してもらおうという哲学なんですね。日本はアメリカと同じように事前に面接できるという形式だけ取り入れましたが、アメリカで大前提になっている「証拠開示」という制度がないので、お粗末な制度になってしまっているのです。
さらにアメリカでは弁護士の尋問の技術が優れています。しかし日本ではその技術を教えられる弁護士がほとんどいないため、鍛えることができません。それで、誘導尋問が多くなっています。私は、アメリカとドイツの良い部分をミックスして、日本に合ったやり方を取り入れる「ハイブリッドモデル」による裁判を提唱し、実践してきました。それがいわゆる「Nコート」なのです。
■司法への不信感を植え付ける「和解」
3つ目は、「交互面接和解」をやめたことです。弁護士と裁判官が法廷以外で個別に会って話すのはおかしいと思いますが、日本では平然と行われています。「和解」といっても実際に話をする相手は裁判官です。それでは、裁判官を説得しようとする駆け引きの場になってしまいます。「弁論」の場では弁論しないのに、「和解」の場で「弁論」しているのは不思議なことです。
「交互面接和解」を実施する理由は、「お互い顔を合わせると本音が言えないから」とか「双方が同席すると喧嘩になるから」と言われています。でも私に言わせれば対席で待つ「弁論」の場では本音で語っていないのか? と言いたくなるし、そもそも喧嘩したから裁判になっているのであって、裁判というものは、そういうものだろうと思います。
私は、相手がいない所で話をするのは公正ではないと考えていて、原則双方立会いのもとでしか和解をしませんでした。法廷では殴り合いの喧嘩をすることはできませんから、興奮しても15分もしゃべれば収まってくるのです。
「交互面接和解」の利用者はどう思っているのでしょうか? 利用者の実態調査によれば、非常に不信感を持っている人が多い、というデータが出ています。有利な和解をした当事者であっても、たまたま結果が良かっただけ、不利な和解をした側はなおさら納得がいかない。多くの人はこんな不公平な裁判は、二度と利用したくないと思っています。こういうことが、司法に対する不信感を国民に植え付けているのです。
そして4つ目は、理由を説明せず、数秒で終わらせる判決の改善です。数秒で終わる主文だけ聞かされたら、遠い所からわざわざ出頭した当事者は頭にくるだろうし、判決文は難しいので、一般の人はそれだけ言い渡しされてもよくわかりません。当然、控訴も増えます。
判決の言い渡しは裁判官と両当事者が顔を合わせる最後の機会です。また、私は裁判官と当事者の最後のコミュニケーションの場だとも考えています。私は15分くらいかけて、なるべく日常会話で理由を説明するよう努めました。特に、負けた方にあなたがなぜ負けたのかを丁寧に説明します。きちんと説明すれば、たいがい納得してくれるのです。それによって控訴が減り、税金の無駄遣いも減らすことができました。
■常識を疑え
このように日本の裁判をめぐる事柄には、おかしなことがたくさんあります。日本だけにいるとわかりませんが、他の国を見るとそのおかしさが見えてくるのです。
長い間、日本の裁判のスタイルは変わりませんでした。私はそれを法曹の怠慢だと考えています。これからも従来どおりの法曹の養成や裁判スタイルを続けていると、いつしか利用者=国民から見離されるはずです。それでいいのでしょうか? これから法曹をめざす皆さんには、このように、法曹界の常識を疑いながら取り組んでいってほしいと思います。