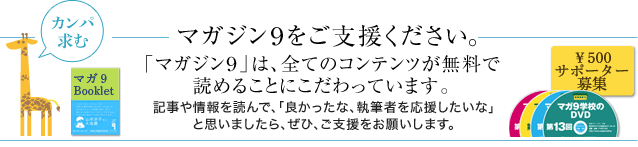2014年10月1日@渋谷校
「けんぽう手習い塾」でおなじみの伊藤真さんが主宰する、資格試験学校の伊藤塾では、
法律家・行政官を目指す塾生向けの公開講演会を定期的に実施しています。
弁護士、裁判官、ジャーナリスト、NGO活動家など
さまざまな分野で活躍中の人を講師に招いて行われている
「明日の法律家講座」を、随時レポートしていきます。
なおこの講演会は、一般にも無料で公開されています。

【講師】
樋渡利秋 氏
(弁護士、「TMI総合法律事務所」顧問、元検事総長)
●講師プロフィール
兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業後、1970年に司法修習修了(22期)と同時に東京地方検察庁検事に任官。最高検察庁検事、同総務部長、法務事務次官、広島高等検察庁検事長、東京高等検察庁検事長などを歴任し、2008年に第24代検事総長に就任。2010年に退任し、弁護士登録。1999年から内閣司法制度改革審議会事務局長、2001年から内閣官房司法制度改革推進準備室長を務め、司法制度改革と裁判員制度創設に携わった。
はじめに
「国民の司法参加」を掲げ、2009年にスタートした裁判員制度。以来、5万人以上が裁判員・補充裁判員としてかかわり、6500件以上の判決が下されてきました。
そもそもこの裁判員制度は、どういった背景と理念のもとで誕生したものなのか。制度の導入とともに、刑事裁判の現場はどのように変化してきたのか。そして今も残る、刑事司法改革の課題とは――。内閣司法制度改革審議会事務局長などを務め、司法制度の改革と裁判員制度の創設に深く関わった、もと検事総長で現在は弁護士の樋渡利秋さんにお話しいただきました。
事前規制型から事後監視型の社会へ
裁判員裁判の導入を含む司法制度改革は、1990年前後から急速に進んだグローバル化を背景として始まりました。人もモノもカネも国境を越えて自由に移動する社会では、経済的な規制の多い国には、なかなか資本が流れてこなくなる。そこで日本政府は、「官から民へ」をキャッチフレーズに、財政や行政、すべてにわたって規制を緩和するための改革を押し進めようとしたのです。
1997年の行政改革会議最終報告書では、〈『法の支配』こそ、わが国が、規制緩和を推進し、行政の不透明な事前規制を廃して事後監視・救済型社会への転換を図り、国際社会の信頼を得て繁栄を追求していく上でも、欠かすことのできない基盤をなすものである。政府においても、司法の人的及び制度的基盤の整備に向けての本格的検討を早急に開始する必要がある〉との提言がなされました。つまり、事前規制型ではなく自由に競争させて、ルール違反をする者がいればそれを取り締まるという事後監視・救済型の社会にもっていく。そのためには、ルール違反者に制裁を加える司法の規模を大きくする必要があるということです。
この提言を受けて、政府は1999年に「司法制度改革審議会」を発足させました。「民間の知恵で改革を進める」というので、13人の委員のほとんどが学者を含む民間人。そして、当時大分(地検)の検事正をしていた私が、事務局長を務めることになったのです。
ですから、司法制度改革の当初の目的は、民事裁判のための法整備でした。しかし、国会で審議会設立のための議論をしている段階で、「国民の司法参加」が重要な課題として浮上してきます。戦前に停止されたままの陪審制度を復活させるべきではないかという議論がずっとあったのを、この際解決すべきだということになったんですね。
また、日本においては、国民にとって司法の敷居が非常に高いのが現状です。知り合いに弁護士はおらず、裁判にかけても解決まで時間がかかる。困ったことがあったら政治家や地元のボスに頼んで話をつけてもらったほうが早いという感覚の人が少なくない。本来は法律で解決すべき問題の2割しか司法の場で解決されていないとして「2割司法」という言葉があるほどでした。
そうした背景のもと、私たち審議会がまず考えたのは「国民の視点から考えた司法制度をつくりたい」ということでした。同時に、いくら制度を分かりやすくしても、それを支える質・量共に豊かな法曹を育てなければ意味がないし、制度を十分に使ってもらうためには、国民が司法というものをきちんと理解してくれるような方策を考えなくてはならない。そして、「国民の期待に応える司法制度」「司法制度を支える法曹の在り方」「国民的基盤の確立」を三本柱とする司法制度改革がスタートしたのです。
裁判員裁判によって、刑事司法の現場はどう変わったか
「国民の司法参加」については、当初は意見が分かれていましたが、議論を深めるうちに、やはり国民に司法を理解してもらう一番の方法は裁判に参加してもらうことではないかという方向性がまとまりました。その経緯を表しているのが、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)の1条です。〈国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する〉。つまり、裁判員という役割を通じて、国民に司法への理解を深めてもらおうという趣旨で始まった制度なのです。
実施後5年が経ち、累計で3万7000人、補充裁判員を含めると5万人の方が裁判員を経験されました。当初は「みんな忙しくて参加してくれないのではないか」「年齢や職業が偏るのでは」といった懸念もありましたが、裁判員経験者の内訳を見ると男女比も、また職業比率もだいたいバランスが取れています。2013年に法務省に設置された有識者による「裁判員制度に関する検討会」が出した報告書でも、制度の運用状況はおおむね順調だという結論でした。
では、この裁判員裁判の導入とともに、日本の刑事司法はどのように変わってきたのでしょうか。
まずは裁判員法51条にあるように、裁判員に過剰な負担をかけないよう「迅速で分かりやすい」審理の実現に向けた取り組みが進められてきました。その具体的な方策が、2005年の刑事訴訟法改正で導入された公判前整理手続です。
これまでは、裁判官に事前に予断を抱かせるような書類などを提出してはならないという「起訴状一本主義」が極端に解釈され、公判開始前に裁判官、検事、弁護人が打ち合わせをするなんてもってのほかだとさえ言われてきました。それを、第1回の法廷までに三者が打ち合わせをして争点をはっきりさせるように、つまり検事は主張の内容とそれを立証するための証拠の内容を開示し、弁護人のほうもそれに反論する主張があればあらかじめ明らかにしておくようにということを、法律で定めたわけです。
これによって、裁判の迅速化は急速に進みました。これまで、裁判員裁判でもっとも長くかかったのは、さいたま地裁で行われた首都圏連続不審死事件の裁判で、2012年4月に判決が出るまで約100日かかりました。しかし、例えばかつてオウム事件が判決まで7年かかったことを思えば、雲泥の差です。裁判員裁判以外の一般の裁判でも公判前整理手続が行われるようになって、ずいぶん早く決着がつくようになりました。
この他、取り調べの任意性を裁判員に分かりやすく立証するためということで、取り調べの録音録画の試行も始まりました。また、「控訴審が継続審化して、一審と同じことをまた審議している」という批判を受けていましたが、控訴審は事後審に徹するという傾向も定着してきました。2012年には「事実認定がよほど不合理でない限りは裁判員の裁いた第一審を尊重すべき」という最高裁判決が出ています。裁判員裁判対象事件の主要15犯罪について、高裁における一審判決の破棄率は、裁判員裁判が始まる前の約18%から激減して、2012年春の時点で約7%。まさに控訴審が「事後審に徹する」ようになっているということでしょう。
取り調べの可視化だけでは問題は解決しない
もちろん、司法制度改革はこれで終わったわけではなく、まだまだ続いています。2014年7月には、法務省の法制審議会特別部会「新時代の刑事司法制度特別部会」が、法務大臣に対する答申を行いました。その中で重要な課題として取り上げられているのが、先ほども触れた「取り調べの録音録画」の義務化に関する議論です。
この試行にあたっては、現場の検事からずいぶん反対がありました。「自分たちを信用しないのか」「カメラの前では有効な取り調べができない」ということですね。それでも最高検がその反対を押し切って試行をスタートさせたのは、裁判員に供述調書の任意性を信用してもらえなければ、結果として裁判で調書が採用されず、実際の犯人を逃してしまうことにもなりかねない、そしてその任意性を分かりやすく証明するには録音録画しかないと考えたからです。
日本の刑事裁判にはかねてから、法廷の場で心証を積み上げるのではなく、事前に作成された供述調書ばかりが重視される「調書裁判」だという批判、本来目指すべき法廷中心の裁判に戻していくべきだという指摘があります。それなのに、調書を信用してもらうための手段でもある録音録画だけに頼るというのであれば、今後とも刑事裁判が「調書裁判」から一歩も脱することができないということにもなってしまいます。
では、本当の意味で「調書裁判」から脱却して、法廷中心主義を実現するためにはどうすればいいのか。私は、二つの方法があると思います。
一つは、関係者の供述以外の客観的証拠をより広範に収集できる方策を設けるということ。例えば、アメリカではおとり捜査や傍受なども幅広く認められていますし、DNAの集積も可能ですが、日本では非常に制約が多い。そしてもう一つが、調書に依存せずに供述証拠を得る、すなわち被告人・被疑者や証人に法廷で真実を話してもらうためのインセンティブを設けるということです。具体的には、司法取引制度や刑事免責制度ということになります。
そうした方策を検討せず、ただ単に捜査段階での供述に任意性があるかどうかだけを争うのでは何ら発展性がないというのが、「新時代の刑事司法制度特別部会」の考え方だと思います。私たち司法制度改革審議会でも同じ理由により、意見書の中で「取り調べの可視化」については、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能・役割との関係で慎重な配慮が必要であると指摘した上で、将来的な検討課題としたのです。
「法の支配」を社会に浸透させるために
「新時代の刑事司法制度特別部会」は、これからの刑事司法のあるべき姿を「国民の健全な社会常識に立脚し、制度の内容が明確で国民に分かりやすいもの」と述べています。司法制度改革においても、その内容が日本の国民性に合うかどうかということが非常に重要だと思います。一般的に言われるように、争いを好まず思いやりがある、そして世間体を非常に大事にする傾向がある。そうした国民性に合致するものであるかどうかが、司法制度改革の一つの山になるのではないでしょうか
他方で、司法制度改革審議会では「司法試験合格者を3000人にする」という目標を掲げていましたが、これは一つの段階に過ぎず、今後もっと増やしていきたいと考えていたのです。最初に申し上げたように、問題を司法の場で解決しようとしないという傾向が日本にはまだまだ強くあります。これではいつまで経っても、社会の中に「法の支配」が浸透していかないのではないでしょうか。そのためにも、もっともっと法曹人口を増やしていかなければならないのです。
世界的に見ても、「法の支配」をきちんと浸透させ、グッドガバナンスを作ることこそが、私たち先進国の変わらざる課題であり、今世界の大きな脅威になっているテロなどを撲滅することにつながると考えます。もちろん、狭い日本の中でさえなかなか浸透してこないのですから、簡単なことではないと思いますが、その意味でもぜひ次世代の皆さんの活躍を期待したいと思います。