とかく、「難しい、とっつきにくい」と思われている「法」。だから専門家に任せておけばいいと思われている「法」。しかし私たちの生活や社会のルールを決めているのもまた「法」なのです。全てを網羅することはとてもできませんが、私たちの生活や社会問題に関わっている重大な「法」について、わかりやすく解説してもらうコーナーです。今あるものだけなく、これから作られようしている「法」、改正・改悪されようとしている「法」、そして改正の必要があるのに、ちっとも変わらない「法」について、連載していきます。「法」がもっと身近になれば、いろんなことが見えてくる!
これだけおかしな材料が重なっても
開かない再審の扉
裁判所に再審(裁判のやり直し)を始めさせるのは、針の穴に象を通すよりも難しいと言われている。裁判所にしてみれば、先輩の判決とはいえ自分たちの組織が誤判をしたと認めるわけだから、なかなか積極的にならない。そもそも、当事者に自らの間違いを判断させるという仕組み自体に、無理があるのだ。再審開始の可否を決める時にこそ裁判員制度を適用するべきだ、と思う。
それにしても、とため息をついてしまう決定がまたしても出た。ところは名古屋高等裁判所(志田洋裁判長)。いわゆる「福井女子中学生殺害事件」で再審の求めを棄却したのだ。
この事件、普通の再審請求事件とは少し事情が異なっている。何より、有罪になった裁判では、1審で無罪判決が出ていた。そして再審請求でも、最初の決定は再審開始を認めていた。つまり、2度にわたり裁判所はどんでん返しの裁きをしたことになる。
服役後に再審を求めている前川彰司さん(47)と、逮捕直後から弁護人を務めている佐藤辰弥弁護士の報告を聞く機会があった。再審請求を棄却した決定の不当性を検証してみたい。
まず事件の概要と経緯を見てみる。
1986年3月19日の夜、福井市の団地の部屋で、卒業式を終えて1人で留守番をしていた女子中学生(当時15)が殺害された。ガラス製の灰皿で頭や顔を殴られたうえ、電気カーペットのコードで首を絞められ、ビニール製のこたつカバーを掛けた上から顔面や首を50カ所以上も包丁でめった突きにされていた。さらに、鴨居にドライヤーのコードを吊るして自殺を偽装しようとした形跡があった。
玄関先に争った様子はなく、顔見知りの犯行と見られていた。警察は当初、同年代のグループによる怨恨を疑い、次にシンナーや薬物中毒者に広げたものの、容疑者を絞り込めなかった。この過程で、前川さんも事件から2週間後に聴取を受けたが、すぐに対象から外されている。佐藤弁護士によると、警察は半年間で延べ約4000人から事情聴取したそうだ。
前川さんが逮捕されたのは、事件発生から1年後。「事件の夜、血だらけの前川さんを目撃した」とする知人の暴力団組員Aの証言が決め手となった。しかし、前川さんと被害者の間に面識はなく、指紋など犯行と結び付ける直接的な物証も出ていない。前川さんは一貫して無実を主張し、自白調書も取られなかったが、「シンナーを吸ってもうろうとした状態で被害者宅を訪れ、シンナーに誘ったところ断られたため激昂して殺害した」とされて殺人罪で起訴された。
Aの証言は、たとえば前川さんが犯行時に着ていたという血だらけの衣類について「川に捨てた」が「川の土手に埋めた」になるといった変遷があり、なおかつ衣類は発見されないなど客観的な裏付けがなく、信用性に疑問が持たれていた。「こうした捜査や公判の経過を分析することなく、適正な事実認定をすることができない事件です」と佐藤弁護士は説明した。
1審の福井地裁はAらの証言の信用性を認めずに無罪を言い渡したが、2審の名古屋高裁金沢支部は逆に信用性を認めて懲役7年の逆転有罪判決。最高裁も支持し、97年に確定した。前川さんは満期出所後の2004年に再審を請求。1審にあたる名古屋高裁金沢支部は11年11月、再審開始を決定した。これに対して検察が異議を申し立て、今年3月6日に名古屋高裁が出したのが再審開始を取り消す決定である。
再審請求審でポイントになったのは主に4点だ。
第1点は、解剖報告書や写真を調べ直したところ、被害者の刺し傷のうち2カ所の幅が、凶器とされた被害者宅の2本の包丁の刃の幅より小さいと分かったこと。弁護団は、現場から見つかっていない「第3の凶器」が存在した、と主張した。激昂して犯行に及んだとすれば事前に包丁を準備していたのは不自然だし、事件の前に前川さんに同行していたとされる男性の証言にも凶器の話は出てこない。弁護団は、前川さんの犯行を否定する新証拠だと訴えた。
しかし、名古屋高裁の棄却決定は、傷と刃の幅の矛盾は認めたものの、「傷の部位、方向、形状、形成順序や包丁の使用状況などを具体的に検討して総合的に判断されるべきで、傷や刃の幅の計測自体の正確性についても検討する必要がある」と述べたうえで、測定の誤差や皮膚の収縮によって数値が合わない可能性がある、と結論づけてしまった。
第2点は、前川さんが犯行後に乗ったとされる車のダッシュボードに「手のひらの形の血痕がついていた」というAらの証言の信ぴょう性だ。事件の約9カ月後のルミノール検査ではダッシュボードから血痕の反応は出ていない。弁護団は新たに再現実験を行い、100~200回以上にわたって執拗に拭き取らなければルミノール反応が陰性にはならない、との結果を新証拠として提出した。そもそも血痕は存在せず、証言に信用性はないとの論理である。
これについても名古屋高裁の決定は、唾をつけたティッシュで拭き取ったという「同乗者」の証言のほか、掃除の状況、期間の経過や日射によって血痕が変化した可能性を指摘し、「条件の違いが再現実験の結果に影響を及ぼした」として弁護団の主張を認めなかった。
佐藤弁護士は「傷の計測が正確であった可能性には触れずに、誤差があった可能性を挙げるだけで第3の凶器の存在を否定するのはおかしい。ルミノール反応にしても、単なる可能性を羅列しただけ。一般常識に反する決定だ」と強調する。
第3点は、犯人像だ。弁護団は、犯人が靴を脱いで室内に入ったとみられること、自殺の偽装工作をしていること、意識的に顔面にこたつカバーを掛けてから刃物で刺していることに加え、傷のほとんどが顔面や首に集中し、しかも浅いことから怨恨による犯行とみられ、「激昂のあまり犯した単純かつ短絡的な殺人とは到底言えない」と指摘した。さらに、第3の凶器の存在が疑われることは複数犯の可能性を、顔面に傷が集まっているのは女性の関与も感じさせる、との法医学者の鑑定書を新証拠として提出した。
しかし、高裁決定は「こたつカバーを使用したことに高度の判断能力までは必要としない」「殺害方法をもって犯人が複数の可能性が高いと推論することはできない」などと否定。「前提となる事実や推論がいずれも成り立たない」と鑑定書を退け、有罪判決の根拠となった証拠の証明力や、Aらの供述の信用性を減殺するものではないと判断した。
そして第4点は、関係者の証言の信用性・虚偽性だ。当初、事件当夜に前川さんと一緒に事件現場へ移動し、その後、喫茶店などに一緒に行ったとされたのはLという男性だった。Aら3人が一致した証言をしていたことが、再審請求審で新たに開示された供述調書で裏付けられた。ところが間もなく、Lが一緒だったというのは虚偽だったことが判明する。つまり、3人が一致して同じ嘘をついていたわけだ。
弁護団は「取調官が3人を仲介する形で誘導して供述調書を作成した」ととらえ、3人の供述の信用性が極めて低く、虚偽である可能性が極めて高いと主張した。しかし、高裁決定は、関係者の証言の変遷を認めながらも「変遷の理由には合理性があり、十分信用できる」と結論づけ、再審請求を棄却した。
簡単に言うと、弁護団が提出した新証拠の各部分に対して「そうではない可能性もある」と揚げ足取りの分析をして排除し、再審開始の要件である新規かつ明白な証拠にはあたらないとして請求を退けたのだ。「本来は、有罪にした判決が採用した証拠と、再審請求で提出した証拠とを総合的に判断すべきなのに、それはしていない」と佐藤弁護士は批判した。前川さんの犯行に「合理的な疑い」が生じれば十分なはずなのに、極論すれば「100%無罪」という証拠を出さなければ再審は開始されないことになってしまう。
そもそも、Aの証言自体、血の付いた犯行着衣、前川さんの同行者といった相当重要な部分で変遷していることだけ見ても、常識的に考えれば根底から信用性が疑われる。そこに、弁護団が再審請求で提出した新証拠を重ねて考察すれば、前川さんが犯人だとした元の判決に「合理的な疑い」が生じるのは自然なことではないだろうか。
この事件のように、物証など直接的な証拠がなく、間接的な状況証拠によって有罪を認定する場合の要件として、最高裁は3年前の判決で「被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実が含まれていること」という基準を示している。慎重な判断が求められているのは言うまでもない。
前川さんは最高裁に特別抗告した。再審にも「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の原則が適用されるとした最高裁の白鳥決定(1975年)に、今回の決定が反すると訴えている。
「この事件は冤罪です。証拠はすべてでたらめです。証言は、警察や検察に対して立場の弱い人が言わされている。最後には勝ちます」。前川さんはこう語った。最高裁が「疑わしきは罰せず」の原則に忠実に審理を進めることを切望するばかりだ。





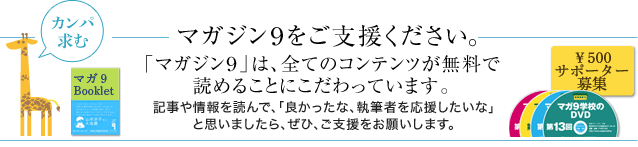


この事件に限らず、冤罪(が疑われる)事件の多くでの、
「市民感覚」からは大きく外れた裁判所の判断を見ていると、
「再審開始の可否を決める時にこそ裁判員制度を適用するべき」との 著者の主張に、
うなずきたくなります。
しかし、現行の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」では、
裁判員制度の対象となるのは地方裁判所で行われる刑事事件のみ。
あなたは、どう考えますか?