世間では、引き受けたいとは思われていないようだ。数日間、缶詰めにされて自分の時間を奪われる。それどころか、見ず知らずの人の自由を奪う決定に参画させられる。しかも、そこで交わされたやりとりを迂闊に外部で話すと罰せられかねないのだから、無理もあるまい。
裁判員である。
今年1~8月に裁判員を務めたうちの約4200人に選任前の気持ちを尋ねたところ、「やりたくない」と「あまりやりたくない」を合わせた否定派が49%と、ほぼ半数を占めていた。私は制度自体に反対ではないが、仕組みや運用には改善の余地がありそうだ。
この数字に変化が出て、否定派がさらに増えるかもしれない。ご存じの通り、裁判員裁判による判決が確定した死刑囚が12月18日、初めて刑を執行されたからだ。
もちろん、制度が始まった時点で予想されていたことではある。それでも、これから先、裁判員になる可能性があるほぼすべての国民に直接影響してくる事態に違いない。ちなみに、2009年5月に制度が始まってから今年10月までに裁判員(補充裁判員を含む)になったのは、6万3500人。これからも年間1万人のペースで選任される計算だ。
ちょうどその2日後、裁判員経験者である田口真義さん(39歳)の講演を聴く機会があったので、それをもとに「裁判員と死刑」について考えてみたい。
田口さんが2010年の裁判員裁判で担当したのは、元俳優が保護責任者遺棄致死などの罪に問われた公判だった。法廷で被告と接して「普通の人間だ」という印象を持ち、「自分も被告席に座るかもしれない」と感じたそうだ。同時に「僕らは司法のユーザーでもある。裁判員制度が、より良い司法制度であってほしい」との思いも強くした。体験を社会に還元したり、裁判後の精神的な負担を解消したりしたいと、2012年に裁判員経験者の交流組織を結成した。
そこで、死刑判決に関わった裁判員経験者から「舞台裏」を知らされる。評議で裁判官から伝えられた情報は、法律上、判決が確定してから6カ月以内に執行されることと絞首刑によることの2点だけで「死刑についてほとんど何も知らないまま判断していた」という実情だった。「執行されたら取り返しがつかないのに、そんな恐ろしいことで良いのだろうか」。疑問が膨らんだ。
法務大臣に宛てて「死刑執行停止の要請書」を出したのは、昨年2月のことだ。裁判員経験者20人の連名だった。死刑判決に関わった3人も加わっており、「彼・彼女らの言からは想像も及ばないほど壮絶な葛藤と今なお抱える重圧が読み取れる」と綴った。
裁判員裁判による死刑判決の確定者が出始めていた時期で、執行もそう遠くないとみられており、「国家の判断による国民への死刑」が「国民の判断による国民への死刑」に転換することに危機感を抱いての行動だった。
要請書で求めたのは、①死刑の執行停止、②執行の様子や死刑囚の状況などの情報公開、③死刑についての複層的な国民的議論の促進、の3点。まずは一度立ち止まり、関連するあらゆる情報を出してもらったうえで、市民レベルで議論をする必要性を訴えたかったという。国会ではなく国民的な議論にこだわったのは、国会議員は裁判員=当事者になれないと法律で定められているためだ。
要請書には「現行法定刑に死刑という特殊な刑罰が明記されている以上、必要的な選択として適法だという理解はしている」とも記し、死刑制度の廃止が目的ではないことを強調している。それでも執行停止を求めた理由を「あらゆることが不明瞭な状況下での執行に疑義と違和感を募らせている」と説明した。
しかし、政府から正式な応答はなかったそうだ。当時の谷垣禎一法相は要請書を出した翌日の記者会見で質問を受け、「死刑の執行停止は(国会で)法的措置がとられないとできない。情報公開は関係者のプライバシーもあり、今以上には必要ない」という趣旨の発言をしただけだった。
そこへ、今回の死刑執行だったのだ。
「何か恐ろしいことが起きてしまった。死刑判決に関わった裁判員経験者からは『現実として受けとめられないほど混乱している』との声が届いた」
田口さんは、さらに心情を吐露した。
「僕も何億分の1かの関わりで人を殺したことになる。国民どうしの『殺し合い』が始まった」
すぐに、抗議文とともに再要請書を法相に提出したそうだ。
マスコミ報道でも、死刑判決に関わった裁判員経験者が、今回の執行を知って苦悶する姿が伝えられている。
「国民の判断によって1人の命がなくなったわけで、改めて責任は重大だと思う。一生背負っていく覚悟でいる」「死刑が執行されれば、裁判員の自分たちが殺すようなもの。その苦しみは一生消えない」(朝日新聞・12月19日付朝刊)
おそらくは自分が裁判員に就いて、死刑判決の当事者にならなければ実感できない感情なのかもしれない。でも、悩み続ける裁判員経験者が1人でもいる限り、無視してはいけない問題に違いない。ほとんどの国民に裁判員になる可能性がある以上、決して他人事では済まされない。
個人的には、世論調査で多数を占める「死刑容認」の方々にこそ、深く考えてほしいテーマだと思う。
このまま何らの対応がとられず、今の仕組みのままで裁判員制度が続くとする。死刑を容認する裁判員であっても、評議中の、そして判決言い渡し後も続くであろう精神的な重みを想像すれば、萎縮して死刑判決に賛同できなくなるかもしれない。死刑の求刑が予想される事件に当たりたくないからと、裁判員の辞退を申し立てる死刑容認派が増えるかもしれない。世論調査での数字の差を勘案すれば、それらは死刑判決が自ずと減っていくことを意味するからだ。
たとえば「1年間」というように期間を限定して、少なくとも裁判員裁判による刑が確定した死刑囚への執行だけでも停止して、その間に集中的に情報公開と国民的議論を進めてはどうだろうか。
裁判員経験者の意見にも十分に耳を傾けたうえで、死刑の求刑が予想される事件を裁判員裁判の対象から外すなど、制度の抜本的な見直しを含めた対策を検討する必要がある。徹底した情報公開が行われるという前提であれば、最終的に死刑の執行停止の是非、あるいは死刑の存廃までを国民投票で問うのも選択肢の一つだろう。
田口さんは今回の死刑執行を受けて「もっと声を出し続けていかなければいけないと痛感した」とも話していた。繰り返すけれど、ほぼすべての国民が当事者となり得るテーマである。裁判員経験者の訴えを自分の問題としてしっかり受けとめ、真摯に向き合うことが求められている。





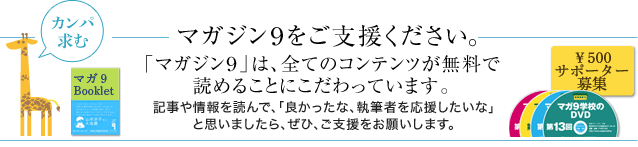


最近では話題に上ることも少なくなった裁判員制度ですが、制度導入の際には、多くの問題点が指摘されていました。「一般市民に死刑かどうかの判断を負わせる」という、世界でも類を見ない仕組みでありながら、その肝心の「死刑」についての情報が、ほとんど公開されていないという事実は、その最たるものでしょう。例えば、刑の執行の順番がどのように決められているのか。死刑囚が、刑の確定後にどのような日々を過ごし、どのように刑が執行されるのか。どんな言葉を残しているのか。そうしたことさえほとんど知られることがないままに、市民に責任だけを負わせるのは、あまりにもいびつだと思えてなりません。
外国の陪審員制度の多くは、有罪か無罪かを陪審員つまり市民あ判断し、量刑は裁判官という役割分担です。ここに日本の裁判員制度の特性があります。
しかし、プロの裁判官なら心の重圧なしに死刑の判決を下すのでしょうか。また、プロの裁判官にまかせていたら、普通の市民は誰かを死刑にすることに対し悩まずにすむので、それでOKなのでしょうか。
裁判員制度には多くの問題点があるかもしれませんが、たとえ一度も裁判員にならなくてもふつうの人が法に
関心を持つきっかけをつくったという意味ではよかったと思います。ことに、死刑について、国民全員にそれがあってよいものかどうかを改めて考えさせることになりました。
たとえプロの裁判官が死刑の判決を下すにしても、それは死刑制度を容認している国民が行っているのです。自分が死刑判決を下したくない、処刑を実行する立場にもなりたくないと思うのに、死刑容認という人は、その矛盾に気づくべきです。
裁判員が死刑判決にかかわらない方向に制度を変更するというよりも、死刑廃止になるよう心から願っています。