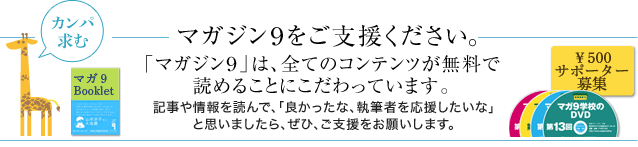皆さんの感想、そして皆さんからの新たなコンテンツの紹介もお待ちしています。
*コメント欄に【〜〜の本について】と前書きしてから、書き込んでくださいね。
 『愛と暴力の戦後とその後』(赤坂真理著/講談社現代新書)
『愛と暴力の戦後とその後』(赤坂真理著/講談社現代新書)
戦後史を知ったつもりになっていたのかも、と思わせる
芳地隆之
自らの皮膚感覚に忠実に、戦後史における違和感の正体を様々な角度から明かそうと試みたのが本書である。
たとえば、オウム事件の語りづらさについて。著者は、この団体のヒエラルヒーが現代の受験制度によるランク付けに酷似しており、ひいてはかつての軍のエリート輩出のシステムにまで遡ることができるとの考えに達する。しかも受験戦争を勝ち抜いた軍人らは、自らの権限を大日本帝国憲法よりも上位に置き、まともな戦略を立てることのないまま場当たり的な戦闘を指揮し、多くの自国民を死に追いやった。その姿勢は現在の自民党憲法改正案にもつながる。「天皇を国の元首とする」という記述には、「権威はあの方に、実権は私どもに」という意図が見え隠れするのである。
各章でばらばらに見えるテーマは、著者が深く掘り下げていくことによって、互いに底流で絡み合い、私たちが歴史と向き合ってこなかったことのツケがいろいろな形で表れていることが明らかになっていく。私は本書を読みながら、何度か自分の拠って立つ地平がぐらつく感覚に見舞われた。己が戦後史を「知ったつもりになっていたに過ぎない」ことを思い知らされたからだ。
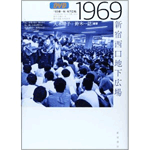 『1969―新宿西口地下広場』(大木晴子・鈴木一誌著/新宿書房)
『1969―新宿西口地下広場』(大木晴子・鈴木一誌著/新宿書房)
「金曜官邸前集会」の原点を、ここに見る
鈴木耕
多くの人が行き交う日本でも有数の雑踏、新宿駅西口「通路」。しかしかつて、ここは「西口広場」が正式名称だった。なぜ「広場」は「通路」と呼び方を変えられたのか。「広場」はなぜ奪われたのか。
1969年、日本全国に若者や学生たちの叛乱が起きていた。街には催涙ガスの臭いさえ漂っていた。そんな時期、新宿西口広場にギターを手にした一群の若者たちが出現した。その後、「フォークゲリラ」と呼ばれることになる若者たち、本書の主人公たちである。あの西口の地下空間に、数千人〜1万人もの人々が集まり、歌い、そして熱い議論の渦ができた。学生だけではなく、背広姿の帰宅途中の会社員までが、ベトナム戦争、資本主義と共産主義、民主主義とは何か、安保条約、基地問題まで、口角泡を飛ばしながら語り合う空間だった。
それがほぼ半年間の毎週土曜日。考えてみれば、これこそ現在の金曜官邸前集会の原型なのかもしれない。
しかし、権力は自由を許さなかった。やがて機動隊が実力行使、歌の環は潰され、若者たちは追い出された。「広場」から「通路」への名称変更だった。「通路に立ち止まってはいけない、歩きなさい、歩け!」そう叫ぶ機動隊のスピーカーの声が、付録の映画『‘69春〜秋 地下広場』(大内田圭弥監督、84分)のDVDの画面から生々しく聞こえる。それが今につながる権力の姿……か。
歴史の証言として、貴重な文章と映像。著者の大木晴子さんは、今でも土曜日のあのフォーク集会があった同じ時間、新宿西口「通路」に、反戦や反原発、反基地、そして平和を訴えるプラカードを持って、静かに立っている。
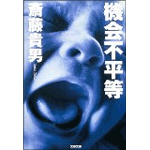 『機会不平等』(斎藤貴男著/文春文庫)
『機会不平等』(斎藤貴男著/文春文庫)
この本が10年前に予言したとおりに!
仲松亨徳
この書が単行本として出版されたのは2000年。小泉内閣が発足する前のことだ。文庫化が2004年。それから10年、斎藤貴男の「予言」は恐ろしいほど当たっている。
教育改革による格差社会、派遣社員など労働者の使い捨て、労働組合の権力擦り寄り、老人・子どもなど弱者の市場化……。何より、自由競争社会の必然である「結果の不平等」ではなく、スタートラインである「機会の不平等」の崩壊が目に見えて進んでしまった。
解説で森永卓郎は、本書での機会不平等社会の要素を次のように書く。一つは、一度下層に落ちると容易に這い上がれない階級固定化。二つ目は、その下層階級が最低限の暮らしを営む権利すら否定すること。三つ目は、上層階級による下層への蔑視だ。
圧巻は、やはり第五章「不平等を正当化する人々」だろう。現安倍内閣でも多用される「私的諮問機関の提言・答申」によって、いつの間にか“馴らされていく”人々。その中心に中谷巌、竹中平蔵ら「御用学者」と呼ばれる人々がいる。中谷は後にその立場を翻したが、竹中は10年以上経っても政権に強い影響力を及ぼしている。
いま、このような社会になったのはなぜなのか、振り返るためにも貴重な書だ。
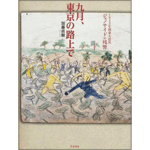 『九月、東京の路上で――1923年関東大震災 ジェノサイドの残響』(加藤直樹著/ころから)
『九月、東京の路上で――1923年関東大震災 ジェノサイドの残響』(加藤直樹著/ころから)
90年前、この大都市で起こったこと
西村リユ
関東大震災のとき、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」などのデマに煽られた民衆によって、多くの朝鮮人が殺された――。そんな話を史実として知ってはいても、実態がどんなものだったのかを、きちんと考えてみたことは正直なところ一度もなかった。その「朝鮮人虐殺」について、当時の新聞記事や体験者の手記、聞き取り記録などをもとに、殺し殺されたのがどんな人々だったのか、そこで何が起こっていたのかを、詳細に読み解いたのが本書である。
朝鮮人を列車から引きずり下ろし、手に手に竹槍や日本刀を持って襲いかかる人たち、「(私は)何もしていない」と泣き叫ぶ青年、死体が転がる横を通り過ぎていく日本人の子どもたち……読み進むうち、目を背けたくなるような残酷な場面も含め、90年前の「東京の路上」の光景が、リアルな感覚を持って目の前に立ち上がってくる。
そしてそれはそのまま、私たちが生きる2014年の東京(あるいは日本)につながるものでもある。虐殺の引き金を引いたのは大震災でも、その背景にはメディアがつくり上げた「朝鮮人は怖い」というイメージがあり、行政によるデマの拡散があった。「嫌中・嫌韓」を煽る雑誌や書籍が書店にずらりと並び、石原元都知事の「三国人発言」をはじめとする差別発言を政治家が平然と繰り返す現状を思えば、虐殺を「過去のこと」と片付けることなど、とてもできそうもない。
本書の中に登場するあるエリートサラリーマンは、当初は朝鮮人による爆弾騒ぎなどの流言を「あるはずがない」と軽蔑していたはずが、噂の拡大に徐々に動揺し、ついには自ら朝鮮人に殴りかかろうとまでしてしまう。広がる差別的な言説に目をつむり続けていることと、「虐殺」に手を染めることとの間にあるハードルは、私たちが思っているよりもはるかに低いのかもしれない。そんなことを考えさせられた。
 『現代語訳 日本国憲法』(伊藤真著/ちくま新書)
『現代語訳 日本国憲法』(伊藤真著/ちくま新書)
いまの言葉に置き換え、憲法の理念を解説
芳地隆之
たとえば日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」を、本書は次のように「訳」している。
「心の中でどのような世界観、人生観、主義、主張をもとうとも、国がそれを禁止したり、不利益を課すことはもちろん、どういう思想をもっているかをたずねることもできない」
なるほど、たずねることもできないのか――このように得心する箇所が随所にある。
現代語訳の横に付している著者の解説からは、日本国憲法のもつ理念の歴史的背景が伝わる。とりわけ第3章「国民の権利と義務」第12条「人権をもつことの責任と濫用の禁止」と第10章「最高法規」第99条「基本的人権の本質」では、基本的人権が保障される「べき」ものであるにもかかわらず、それが願望に過ぎなかった歴史の上にある価値であり、「人権を守ることは、今を生きる者の責任」との言葉は重い。
第9条については解説の部分から引用しよう。著者が愛国少年だった中高生の頃、武士道の精神が戦争放棄の9条にはあるとの発見に至る。なぜなら「刀をもっているから強いのではなく、人格の高さで相手を説得し、手を出させない」という考えに基づいているからだと。この言葉、憲法を解釈で弄ぶ為政者に伝えたい。
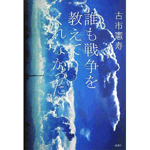 『誰も戦争を教えてくれなかった』(古市憲寿著/講談社)
『誰も戦争を教えてくれなかった』(古市憲寿著/講談社)
平和体験から思想や政治を創りだそう!
山下太郎
戦争をどう伝えるか。
昨今話題になっている問題の根幹には、この問いが潜んでいるように僕は思う。
たとえば集団的自衛権行使の問題。政府の議論を歴史的文脈のなかでどう捉えたらいいのかと問われた三谷太一郎東大名誉教授は、開口一番、「戦後も68年が経過して、日本人の戦争観が、敗戦直後とは大きく変化したということです。憲法9条の前提となっていた日本人の戦争観が変わってしまいました」と語った(2014年6月10日 朝日新聞朝刊)。
あるいは今年5月、修学旅行で長崎を訪れていた男子中学生5人が、原爆に被ばくし、現在はその語り部として活動している方に「死に損ないのくそじじい」などと暴言を吐いた出来事。はたして中学生に反省文を書かせ、校長が謝罪するだけで問題は解決するのだろうか。
そんなもやもやした気分を抱えながら読むのにうってつけなのが本書。若手社会学者としてメディアをにぎわす古市憲寿さんが、世界各地にある戦争博物館を観光気分でめぐり、戦争がどのように記憶されているのか――その国が戦争をどのように考えているかをレポートしている。
細かいネタが散りばめられ、「戦争あるある本」としても楽しく読めるが、「戦争をどう伝えるか」について鋭い批評も展開される。
日本には公の戦争博物館がない。戦争を国民が共有する「大きな記憶」として残すことを避けてきたのだ。それならば、なおさら戦争を語り継ぐことが大切……とは言わないのが本書のキモだろう。
古市さんは、「大きな記憶」を再構築するのに、太平洋戦争は「もはや古すぎる」と言い切る。そして、「約70年前の人々が、戦争体験を元に社会を作りだしていったように、現代を生きる人々は、今まさに長く続く『平和体験』から思想や政治を紡ぎ出していくしかない」と提案する。
僕は、これがこれからの平和運動の出発点じゃないかと思う。
本書の巻末には、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のメンバーと古市さんの対談が載っている。これを読むと、マガ9読者は言葉を失うんじゃないだろうか。
ちなみに僕が衝撃を受けたのは、このやりとり。
「戦争は大正ですか?」
「昭和。」
「一個前ってこと? 近いね。」
しかし、彼女たちも「戦争は嫌だ」と語るし、平和であることが日本の良さであると認識している。希望は、きっとここにある。
 『小さいおうち』(中島京子著/文春文庫)
『小さいおうち』(中島京子著/文春文庫)
気づかないうちに忍び寄る「戦争」
西村リユ
第143回直木賞受賞の小説。山田洋次監督、松たか子主演の映画も話題になった。
ストーリーのメインは、昭和のはじめ、東京のある中流家庭に女中として奉公していたタキが、当時を思い返して綴った手記。タキが慕う、若く美しい「時子奥様」の恋愛事件もさることながら、印象的なのはそこでの「戦争」の描かれ方だ。
〈「非常時」は一種の流行語ではあったが、生活するこちらがわにとっては、なにが非常事態なのかいまひとつピンと来なかった〉
タキがそう振り返るように、満州事変があり2・26事件や5・15事件があっても、人々の生活はそうすぐには変わらない。好景気に沸き、1940年に予定されていた東京オリンピックを心待ちにしながら、海水浴やショッピングに興じる「時子奥様」や一家の日々は、私たちが今想像する「戦争のはじまり」とは対照的に、明るくのどかですらある。
「戦争」は、私たちが考えるような分かりやすい形ではなく、気づかないうちにひたひたと、けれど確実に人々のそばへと近寄ってきていた。そんなふうに考えていると、当時と同じように「好景気」が叫ばれ、東京オリンピック開催決定に浮かれる最近の空気が、なんとも怖いものに思えてくる。今は果たして「戦後」なのか「戦前」なのか?
 『日本は戦争をするのか 集団的自衛権と自衛隊』(半田滋著/岩波新書)
『日本は戦争をするのか 集団的自衛権と自衛隊』(半田滋著/岩波新書)
「集団的自衛権論争」で見逃されている「もう一つの現実」
寺川薫
安倍首相が目指す「解釈改憲」のおかしさや、「集団的自衛権行使」の具体的事例やその危険性については、もうすでに多くのメディアで指摘されている。特にここ数週間はその話題が溢れているので、正直言うと私は食傷気味だ(なんて書いたらマガジン9読者に怒られそうだけど)。
私がお勧めする『日本は戦争をするのか 集団的自衛権と自衛隊』でも、もちろんそれらのことに触れているが、本書が他の書籍等と一線を画すのは、自衛隊「制服組」による「すでに進行中の恐ろしい現実」が書かれていることだ。さすが防衛庁(省)や自衛隊を長らく取材し続けてきた半田滋氏(東京新聞論説委員兼編集委員)ならでは、と言いたくなる。
半田氏は「集団的自衛権の行使解禁により、戦前のように軍人が大手を振って闊歩する国に戻るかもしれない」と言う。
この一文を読んだだけでは、行使容認論者は「そんなことあるわけないよ」と冷笑し、行使反対論者も「そこまでは行かないでしょう」と疑問視するかもしれない。でも、本書を読めば、半田氏の言うことが決してオーバーなことではないと分かる。
陸上自衛隊初の「戦地派遣」となったイラク派兵を機に、防衛省内部では「背広組」よりも「制服組」の発言力が増したこと。その制服組が政治家の家を夜な夜なまわって直接「お願い」をし、防衛政策に影響を及ぼしていることなど、海外派遣等の「実績」を積むことで「軍人」の力が増している事実が書かれている。
国防通を自認し、集団的自衛権論争でも自信満々に持論を展開する石破茂・自民党幹事長は「最終的には国民に選ばれた政治家が判断すべきこと」と言い、シビリアンコントロール(文民統制)を強調する。安倍首相も「政治による歯止め」を理由に、集団的自衛権の行使を容認しても「自衛隊の際限なき海外派遣」はないと言う。しかし、憲法9条の縛りがある現在でも、「軍人」が政治家を動かして防衛政策を事実上自ら決定する「逆シビリアンコントロール」が機能していることが、本書を読めばよく分かる。
「集団的自衛権の行使」によって、さらに「実績」を積んだ自衛隊が、どんな力を持ち、どんな行動に出るのか……。そんなことを考えざるをえなくなってくる。
 『ハンナ・アーレント』(矢野久美子著/中公新書)
『ハンナ・アーレント』(矢野久美子著/中公新書)
映画の台詞から興味をもって……
気仙沼椿
寒い朝、岩波ホールの第1回上映のために小一時間も並んだ。かかっている映画は『ハンナ・アーレント』(フォン・トロッタ監督 2012)。それまで、アーレントのことは良く知らなかった。なぜどうしても見なくては! と思ったのか、あんまりよく思い出せない。今まで見たことがないくらいの多くの観客が岩波ホールの前に並んでいたから? 有名な女性哲学者なのに、どんな人か知らなかったから?……理由は忘れてしまった。
ドイツ生まれのユダヤ人で、ナチスの手を逃れ、アメリカに亡命したハンナ。ハイデガーやヤスパースとの交流や、ナチスのアイヒマンの裁判傍聴記が有名で、この映画もそのアイヒマン裁判をめぐってのエピソードが主となっていた。
映画を見て強烈に印象に残った台詞がある。「自分が愛するのは友人だけ、何らかの集団を愛したことはない」(中公新書 175P/ 映画では、「民族を愛したことはない」と字幕がついていた)。いま、愛国心があおられ、隣国への嫌悪が喧伝されている。私はこの言葉に救われた気がした。私も個々人との関係性だけを信じていればいい。私は、友達が好きだし、家族が好きだ。でも、顔の見えない「集団」を嫌っているのか、憎んでいるのか……それはわからない。友人として信頼できるなら、それがすべてだ。
この台詞にひかれて、中公新書『ハンナ・アーレント』を読み始めた。著者は、長年アーレントの翻訳を手がけてきた矢野久美子。矢野はアーレントの一生を丹念におい、アーレントの思想や著作の内容もふくめて、わかりやすくまとめてくれている。自分が生きている時代に(ちょっと、かぶってるだけだが)こんなにも強く、聡明な女性がいたのかと感動するとともに、この本のおかげで、私は自分なりのもう一つのヒントを得た。
世の中のいろんな動きについて、いろんな立場が混在している。解釈改憲は反対だけど、自衛隊は他国でも活動すべき。放射能は怖いけど、福島については風評被害ではないか。中国とは経済の結びつきは大切だけど、島についての権益主張は譲るべきじゃない……などなど。違う誰かとすべての意見が一致することはほとんどない。そんなとき、議論下手の日本人(=私)は、失望し黙ってしまう。ああ、また私の意見は少数派だ、理解されない、と悲しくなる。
だけど、最近はアーレントを思い出すことにした。彼女は、アイヒマンについて、割り当てられた仕事を遂行したにすぎない「凡庸な悪」と評したことで長年の友人たちから絶縁される。エルサレムでも受け入れられない。それでも、彼女は一方で、学生たちや多くの人たちの支持を得る。考えを変えることはなかった。
思考と行動のレベルがあまりに違うけれど、私はアーレントを思い出す。自分の考えが正しいと思うなら、「仲がいい」と信じていた人が離れていっても仕方がない。複数性を、多様性を認められなければ、民主主義じゃない! と心の中で自分を鼓舞する。
ただ、アーレントは、こうも述べている。――「ソクラテスは、思考のためのパートナーである自己と矛盾するような悪をおこなうよりも、悪をなされるほうがましであると考える。こうした自己との交わりや自分のおこないを吟味することを知らなければ、すなわち思考しなければ、どんな犯罪を犯すことも可能になる」(221P)
思考するために、私はもっと本を読もう。
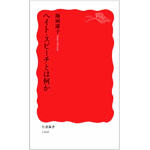 『ヘイト・スピーチとは何か』(師岡康子著/岩波新書)
『ヘイト・スピーチとは何か』(師岡康子著/岩波新書)
明快な定義と提言をくれる良書。自らの傲慢さを自覚した
気仙沼椿
両側から飛び交う罵声の中、池袋を歩いた。今年の春のできごとだ。最近顕著になっている「ヘイト・スピーチ」(差別扇動)と、そのカウンター勢力のつばぜり合い。白昼、罵りあう言葉の圧力で転びそうになりながら繁華街を歩くなんて、初めてのことだった。もちろん、カウンター側の野次馬として、である。これは何だろう? どうして笑いながら人を貶めることができるのだろう? ヘイト・スピーチを目の当たりにしたとき、その現象、意味、理由、影響……体感的に「なぜ?」と思った。
本書は、その疑問に明快に答えてくれる。ヘイト・スピーチとは何か? ヘイト・クライムとの違い、差別の構造、歴史的な流れ、国際的な規制法、各国の事例、そして日本の過去の事件、現在の問題点、今後に対する提言。弁護士である著者・師岡は、差別事件の弁護活動から、このテーマに関心を持ち、研究を重ねてきた。
ヘイト・スピーチがなぜ規制されなければならないのか。それは、差別が当然のものとなり差別構造を強化するからだ。最終的には、それはジェノサイドにまで到達する。また、マイノリティ集団に対しての否定は、マイノリティ個人が(集団としてではなく)傷つき自死を選ぶほどの苦痛となるからだ。そして、日本政府はまったくといって、この現実を見ようとしてこなかったし、今も見ようとしない。
街角の敵意は、私たちの国や社会がやすやすと自分たちに許してきた傲慢さの表出なのだ。この傲慢さは恥ずべきものだと思う。私たち自らが考え、適性な措置(法による規制、公人の発言への厳しい責任追及など)をとらなければ! 本書は、私たちの怠慢をも指摘する。
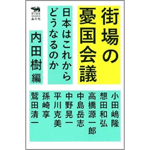 『街場の憂国会議 日本はこれからどうなるのか』(内田樹編/晶文社)
『街場の憂国会議 日本はこれからどうなるのか』(内田樹編/晶文社)
安倍首相に100%の「NO!」を突きつける
鈴木耕
安倍政権になってから、なんだかやたらと忙しい。これまで僕は文章を書くことを主体に、「反原発」に関する集会やデモ、勉強会、講演会などへの参加、新聞雑誌専門書ネットなどからの情報収集、さらには知人友人の専門家やジャーナリストから教えを乞う……なんてことをささやかにやってきた。テーマは絞られていたから、それだけならそんなに忙しくはなかった。
ところが安倍政権、原発再稼働はむろんのこと、原発輸出、原発被災者切り捨て、ウソまみれの五輪招致、武器輸出緩和、集団的自衛権、自衛隊海外派兵、特定秘密保護法、解釈改憲、消費増税、TPP、税体系と社会保障制度の改悪、高齢者医療負担増、教育への政治介入、沖縄基地問題、労働法制の改悪、そして最終的には憲法9条改悪……と、休む暇もなくこの国をメチャクチャにしようとする政策を連発。それが安倍悲願の「戦後レジームからの脱却」だというから恐れ入る。僕は、ここに挙げたことのどれ一つとして賛成できない。だから、時間があればそれらの勉強会などにも顔を出す。忙しくなるのは当然だ。
「一将功なって万骨枯る」という言葉があるが、安倍がやろうとしているのは、自分の頭の中で捏ね上げたゲームの政治化でしかない。国民なんかそっちのけ。安倍に付き合わされるんじゃ、万骨だって枯れちまう。
そんな僕の想いを、ゼーンブまとめて面倒を見てくれたのがこの『街場の憂国会議』だ。いやあ、嬉しかったねえ。
内田樹さんが自分の知人や「お目にかかったことはないけれどその方の書いたものから見識に敬意を抱いていた方」に寄稿をお願いして完成した本だというが、内田さんのほか、小田嶋隆、中野晃一、想田和弘、平川克美、高橋源一郎、孫崎享、中島岳志、鷲田清一という錚々たるみなさんの論考が並ぶ。ひとつひとつを紹介する紙幅はないが、とにかくどれを読んでも外れはない稀有なアンソロジーだ。
安倍のヤバイ行き方(生き方)に、100%のNO!を突きつける迫力。1編がそれぞれ1冊分の思考・思想に充ちていて、なんだかフツーの本の10倍得したような読後感だった。
 『靖国問題』(高橋哲哉著/ちくま新書)
『靖国問題』(高橋哲哉著/ちくま新書)
「国家」はマインドコントロールで「犠牲」をつくる
水島さつき
大学時代も社会人になってからもずっとノンポリだった私は、なんだかんだ言っても、「いざという時に、国は国民のことを大事にしてくれる」「真っ先に命も守ってくれる」そんな甘っちょろいことを、ずっと信じていた。この本に出会うまでは。
『靖国問題』の初版は、2005年4月。まさに「マガジン9」の前身である「マガジン9条」が立ち上がった1ヶ月後のことである。当時の小泉純一郎首相の靖国参拝がきっかけで、この問題がクローズアップされていた。で私も読んでみたわけだが、読み始めて早々に、2ページ半に渡って引用されている、雑誌『主婦の友』(1939年6月号に掲載)の「母一人子一人の愛児を御国に捧げた誉れの母感涙座談会」の会話の内容に戦慄した。
たった一人の自分の子どもが戦争で命を落としたというのに、「望みがかなって名誉の戦死をさしてもらいましてね」「私らのような者に、陛下に使ってもらえる子を持たしていただいてほんとうにありがたい」「うれしくてみんな泣いていた」などの会話がえんえんと続いていくのだ。どう考えてもまともな精神ではない。このような「マインドコントロール」が日中戦争から太平洋戦争に至るまで国を挙げて行われて、莫大な数の犠牲者を生んだ。靖国神社は、そんな「国民が血を流す=犠牲」を「神聖化」するための総本山だった。
なぜ、何のために国家はそんなことをするのか? それについて、高橋哲哉氏の論理的な考察が続く。沖縄基地問題や原発の問題など、私たち国民の「犠牲」を強いるシステムの根幹というか典型にあるのが、「靖国神社」である、ということがよくわかる。
この本を読んでからというもの、「日本人としての誇りを取り戻さなくちゃ」とか、「靖国神社にお参りするのは、日本古来の文化のようなもの」という意見に対しては、違和感がありまくる。また無邪気に「みたままつり」にデートにいくという友人の息子をつかまえて、「趣味悪いね。別の場所に行ったら」と言っては、嫌がられてもいる。
しかし、本が刊行された9年前より事態は悪くなっていると感じる。先日、安倍首相は、自民党内の腹心すら止めたそうなのに、強行に靖国参拝をした。そして集団的自衛権の行使容認に向けても、全政治生命をかけている。私は今、たまらなく恐ろしさを感じている。
かつての私のような人、早くこの本を読んで欲しい。そして「危機感」を共有しよう。
 映画「アクト・オブ・キリング」(デンマーク・ノルウェー・イギリス合作/ジョシュア・オッペンハイマー製作・監督 2012)
映画「アクト・オブ・キリング」(デンマーク・ノルウェー・イギリス合作/ジョシュア・オッペンハイマー製作・監督 2012)
人間にとっていちばん恐ろしいのは、殺されることより、殺すこと
柳田茜
1965年、インドネシアで100万人とも200万人ともいわれる大虐殺が密かに行われた。犠牲となったのは共産党関係者。当時の国軍は、有力な政党のひとつであった共産党の勢いを削ぐために、民間のヤクザや民兵に殺害を命じたのだ。
このドキュメンタリー映画は、大虐殺の実行者たちに過去の行為を語らせ、殺害の様子を再現させる。というと、さぞや陰惨な映画と思われるかもしれないが、慄然とさせられるのは、彼らが行った行為の残虐さそのものではない。
「殴り殺すと出血がひどくて片づけるのが面倒だから、こうやったんだ」
彼らは、針金でギリギリ絞殺するシーンを笑いながら演じる。やがて私たちは、嬉々として再現をする彼らを見ているうちに、「人間にとっていちばん恐ろしいのは、殺されることよりも殺すことだ」という現実に心底から気づかされる。呆れるほど陽気に振る舞う彼らの心の内に潜んでいるすさまじく深く暗い闇が、じわじわと明らかになっていくからだ。その衝撃は、残酷な場面をストレートに描くよりもはるかに大きい。
映画の冒頭では「殺人は許されない。殺した者は罰せられる。鼓笛を鳴らして大勢を殺す場合を除いて――ヴォルテール」という字幕が映し出される。
まさに今、私たちの国の政府も鼓笛を鳴らそうとしている。しかし、この映画が世界中の映画賞を受賞し、観客の心を揺さぶり続けていることに希望を見出せるのではないだろうか。だから、まずは国が命じる「罰せられない殺人」が、それを行った者の精神にもたらすものを直視したい。そして、多くの人が「それは受け入れられない」と認識することが、いつの日か社会を、国を、世界を変えることにつながると信じたい。