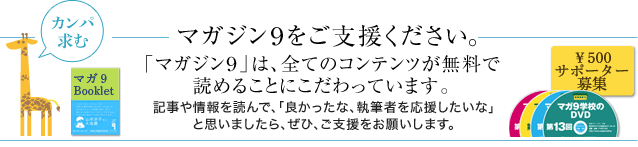皆さんの感想、そして皆さんからの新たなコンテンツの紹介もお待ちしています。
*コメント欄に【〜〜の本について】と前書きしてから、書き込んでくださいね。
 『日本のいちばん長い日』(岡本喜八監督/1967)
『日本のいちばん長い日』(岡本喜八監督/1967)
今の「戦争」イメージの、軽さを思い知らされる
芳地隆之
タイトルは、1945年8月14日の昼の御前会議から翌日正午の天皇の玉音放送が流れるまでの約24時間を指す。
ミッドウェー海戦、南方戦線、沖縄戦などでの相次ぐ敗退、そして広島、長崎への原子爆弾投下、さらにはソ連の満洲侵攻と、日本に戦う余力はなかった。
閣僚間では、ポツダム宣言を受け入れるか否かの議論が行われ、国体護持を条件に受諾すべしとする東郷外相、米内海相らに対し、阿南陸相は本土における徹底抗戦を主張。最終的に天皇が「終戦」を決断する。
日本の閣僚は誰一人「敗戦」という言葉を使わない。はっきり「敗戦」を言うのは、戦わずしての降伏を断固拒否する若手将校の方だ。天皇を守る役割を担う近衛師団の彼らは、宮城を占拠し、天皇にポツダム宣言受諾の翻意を進言しようと試みる。
陛下のお言葉を納めた録音盤を見つけ出せ、玉音放送を阻止せよ――陸軍兵士たちは宮内省になだれ込むが、彼らは「反乱軍」とみなされる。首謀者である若手将校は国民に決起を促すビラを撒いた後、宮城の前で自決。目を剥いたまま倒れているシーンに、ラジオから聞こえる天皇の抑揚のない声が重なる。
この映画には民衆がほとんど登場しない。当時の日本の中枢にいたエリートたちが、日本の敗戦を受け入れるまで、どのように考え、行動したのかが、史実に基づいて再現される。
それをどう評価するかは様々だろうが、半世紀ほど前のこの作品、いまを生きる私たちの目を引き付けて離さない力がある。私は、80人近い登場人物をきちんとスクリーンに収める岡本喜八監督の手腕に舌を巻くとともに、いまの時代に想起される「戦争」のイメージの、あまりの軽さを思わずにはいられなかった。
 『「法の番人」内閣法制局の矜持』(阪田雅裕著/大月書店)
『「法の番人」内閣法制局の矜持』(阪田雅裕著/大月書店)
「立憲主義を守るか否か」を争点としてなら、共闘できる!
望月トト
「立憲主義」という言葉、みなさんは聞き覚えがあったろうか。恥ずかしながら自分は昨年まで「そういえばそんな言葉もあったかな」程度にしか知らなかった。小中学校の公民の授業で出てきたのかもしれないが、「三権分立」や「国民主権」に比べてもまったく記憶に残っていない。憲法学者の小林節教授ですら「当たり前すぎて教えてこなかった」と述懐されていたから、自分だけではないのだろうと思う。
立憲主義とは、国家権力の行使を憲法によって縛り、国民の統制下に置くという、憲法の存在根拠ともいえる原理だ。議会の多数勢力を得て政権を握ったからといって、好き放題に権力をふるうことはできない。だからこそ多数者の専制を防ぎ、少数者の人権を守ることができる。しかし、安倍首相は「私が最高責任者」との理屈で、自らの判断で憲法解釈を変えられると言い切っている。これはつまり、立憲主義の死にほかならない。
従来、政府の憲法解釈を定めてきたのは内閣法制局だった。憲法9条をめぐっては「戦力を持たない」という条文と自衛隊の存在とを整合化させるため、「急迫不正の侵害に対処しうるだけの、必要最小限度の実力」であって戦力ではないという苦しい言い訳をしてきた。さらに90年代以降、自衛隊の海外派遣拡大にあたっては、「武力行使と一体化しない」「後方地域支援」「非戦闘地域」といった理屈でそれを正当化してきた。これを屁理屈だといえばその通りだし、実際左派はそんな法制局を権力の下僕として批判してきたのだ。
しかし、いま起きているのはその「土台」である立憲主義の破壊だ。集団的自衛権による自衛隊の武力行使が、9条の条文とも、過去の政府答弁の積み重ねとも、真っ向から矛盾してかまわない。それが「憲法解釈変更による集団的自衛権の容認」によって宣告されることだ。となれば、もはや憲法の存在自体が無意味ということになるだろう。万が一、海外での武力行使によって自衛隊員が他国民を殺しても、その正当な根拠が憲法上存在しないということにもなりかねない。
本書の著者である阪田雅裕氏は、かつて小泉政権で内閣法制局長官を務めた。その阪田氏自身が、法制局の内幕を語りながら、これまで政府がどのように9条解釈を説明してきたか、いまの解釈改憲論がいかに非論理的なものであるか、穏やかな口調ながら確たる信念のもとに語っている。聞き手は阪田氏より30歳年下、マガ9でもおなじみの川口創弁護士。イラク派兵違憲訴訟を闘った川口氏と阪田氏とは、一見あいいれない立場に見える。確かに論点によっては両者は意見を異にする。しかし、それ以上に、立憲主義という国家原理の破壊への危機感で両者は一致する。今年5月、阪田氏を含む法制局長官経験者、憲法学者、外交・安保の専門家らによる「国民安保法制懇」が立ち上げられた。これも過去の主義主張を超えた大同団結の一例だろう。
「自衛隊が合憲か違憲か」というレベルの闘いから、「立憲主義を守るか否か」というレベルへ、争点ははるかに引き下げられている。前者について一致できない人どうしでも、後者については共闘できるはずだ。安倍政権の暴走を止めるには、良識あるすべての国民が結束して立ち向かうほかない。私たちも試されているのだ。
 『福島からあなたへ』(武藤類子著/大月書店)
『福島からあなたへ』(武藤類子著/大月書店)
この本は、自分にとって〝運動のためのバイブル〟です
望月トト
2011年9月、明治公園に6万人を集めた「さようなら原発集会」……こう書いて、なにかもう遠い昔のような、あるいはパラレルワールドのできごとのような感覚にとらわれ、少し落ち込む。
あの原発事故の直後、私たちはその被害の巨大さや、何百年・何万年という放射性核種の半減期の途方もなさ、そしてそれらに何ひとつ有効な手を打てない人類の無力さに、打ちひしがれていた。それに輪をかけたのが、社会に深く根を張った原子力産業の巨大さ、それへの依存を断ち切ることの難しさ。被害者である福島県民自身が、声を上げて原発に反対できない理不尽さ。あの日からしばらく、不安と無力感から精神のバランスを崩した人も多かったのではなかろうか。自分もその一人だ。
そんな悶々とした日々のなかで、それでもやはり声を上げるしかないと参加した「さようなら原発集会」で、初めて武藤さんのスピーチを耳にした。「原発をなお進めようとする力が、垂直にそびえる壁ならば、限りなく横に広がり、つながりつづけていくことが、私たちの力です」……被害者であるはずの福島の人の言葉に、なぜ自分が癒やされているのか。矛盾を感じながら、ただ涙が流れた。
福島県三春町で里山喫茶を営み、「ハイロアクション福島原発40年」として福島第一原発の廃炉を訴える活動を準備していた武藤さん。3・11と「さようなら原発集会」でのスピーチによって、彼女は否応なく福島の被災民の声を象徴する存在となった。以後、経産省前での「原発いらない福島の女たち」の座り込み、全国から告訴人を募った「福島原発告訴団」の組織……と奔走し続けてきた。1万3000人超が参加した史上類のない大規模告訴はしかし、昨年9月、福島地検から東京地検へとなぜか移送され、全員不起訴となった。現在、検察審査会への申し立てにより不起訴不当の処分を求めるアクションが続けられている。
いま読み返して、当時の武藤さんの言葉の中に、すでに被害者の分断や、風化と忘却への予見が見え隠れしていたと感じざるをえない。チェルノブイリ事故の後から原発に反対してきた彼女にとって、人々がいかに忘れっぽく容易に分断されやすいかは見通されていたのだろう。しかし、それがわかっていてもなお、人を信じて行動するという意志が彼女を支えているし、周囲を勇気づけてもきた。さまざまなネガティブな感情を受け止めながら、つねに優しい微笑みをたたえ(最近は、疲れた表情をのぞかせることも多いが…)淡々と行動し続ける姿が、どれだけの人を励ましただろう。
本書は自分にとっての「運動のためのバイブル」だ。武藤さんの言葉は、癒し系のエコロジストとも、勇ましさだけの革命家とも違う。他者に流されない一個人であることと、自然のなかに生かされている感覚、そして民衆への絶対的な信頼が、絶妙のバランスで同居している。
六ケ所村の核燃輸送に反対した女性たちの非暴力直接行動の体験を語る言葉は、権力を上まわる力を持つことが運動の目標ではないのだと教えてくれる。東北の人々の優しさ、粘り強さを愛しつつ、かつての蝦夷の抵抗の歴史が「新しい風を吹きこまれ」蘇ることに希望をつなぐ。武藤さんがみなに教えた会津の土着の舞踊「かんしょ踊り」は、その後経産省前などのデモ行動でしばしば行われるようになった。
福島の事故が継続するなかで原発再稼働が画策され、同時に憲法さえもが危機に瀕している。数々の課題のうちどれを優先して取り組むべきか、苦しい思いにかられることも多い。けれども、武藤さんがこの本で、また彼女自身の行動によって教えてくれたものは、自分を含め多くの人の心の中に根付き、さまざまな運動の場で倍音のように響いている、と思う。