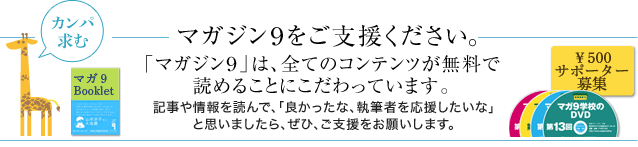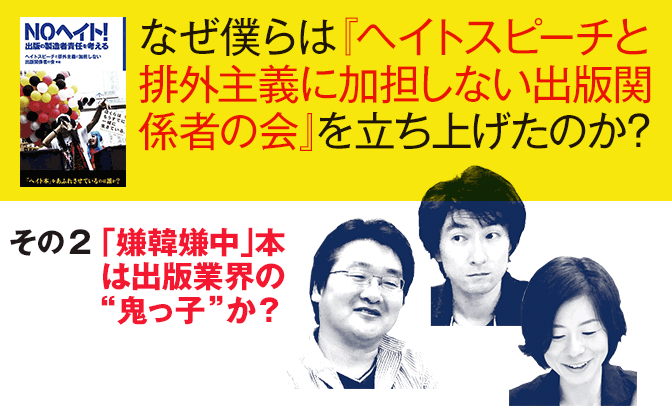
「嫌韓嫌中」本の「つくり方」
――前回は「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」の立ち上げから活動の内容、そして活動を進めていく上での悩みもお聞きしました。
お話の中で皆さんは、憎悪や差別を煽る本をつくっている編集者の多くは「生活のために心ならずもつくっているのではないか」とおっしゃっていましたが、最近の本のタイトルなどを見ていると、本当に中国や韓国を敵視していて、確信的に「正しい本をつくっている」といった編集者も増えているのではないかと思うんです。そういう同業者に対しては、何か言いたいことはありますか。
真鍋
いや、そういう編集者には会ったことはないから(笑)。
森
私も会ったことはないです。「日本はこんなに素晴らしいよ」と、「愛国」的なことをポジティブに伝えようというのなら、まだ想像できる気も…。だけど、中国や韓国のことをネガティブに露骨にバッシングするような本をつくる気持ちとは、どのようなものなのでしょうね。
岩下
僕も、つくり手側は直接には知りませんが、読み手は知っていますよ。親類や友人どうしの会話のなかでも「中国なんてね…」みたいな発言はよく出てきますし。そうすると、もともとそれに批判的なスタンスをもっていない編集者だったら、「中国や韓国が嫌いな人はいっぱいいるんだから、そういう本をつくれば売れるんじゃないか」というのは、職業的には正しい考えですよね。ヒットの「2匹目、3匹目のドジョウを狙え」というのは、どこの出版社でもやっていることですから。
ただ、その本の読者にどんな影響を与えているかということはよく考えてほしいなとは思いますね。
真鍋
何でもいいから売れる本をつくらなければいけないような環境にいたら、僕も「2匹目のドジョウ」を狙おうと思うでしょう。「中国はけしからん。韓国は嫌いだ」とテレビを見ながら口にする人は身近にいっぱいいますから、「嫌韓嫌中」的な言説を発している筆者を探す。そういうことを喋っている人、書いている人、新聞、雑誌、テレビ、ネット、いろいろなメディアを見れば、大体ピックアップできます。で、「これは!」と思う人の書いたものを集めて読んで、自分なりの切り口が見つかれば、執筆依頼の手紙を送って会いに行く。本づくりの基本は同じですから。でも、いつも自分がつくっている本と同じような部数しか売れなかったら、そこは「能力に問題あり」ということで、ものすごく落ち込むような気がします(笑)。
かつて、朝日新聞の記者だったむのたけじさんが、敗戦直後、自らの戦争責任を感じて退社されましたが、編集者として自分も同じようなことができるとは思えません。すぐに時流に乗っかった、売れ筋の、読者の「空気」を読んだ本づくりを始める姿を想像してしまいます。そういう自分に釘を刺しておきたいというか、みんな自覚がないまま加担してしまう可能性があることを、考えてほしいと思っています。
岩下
1945年8月15日を境に、ころっと民主主義者になった人たちがいたように、また同じことが起こるだろうと想像できてしまうのが悲しいことではあるんですが。近年の出版の動きを見ていると、先の戦争で経験しているんだから、もうちょっと学習しようよと言いたいですね。
会の名前は、個々人の意思表明
――会の名称を「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」としたのは、「自分は加担しない」という個々人の表明でもあるわけですね。
森
私は、もちろん「加担したくない」という気持ちが強いです。加害者になるということが感覚的にとても怖いんです。被害者になるかもしれない恐怖よりも、加害者になる恐怖。自分が加害者になったときに、どう後始末するのかとか、落とし前をつけられるのかと想像すると、それが自分にとっては恐ろしい。だから、担当した本で誰かを傷つけるとか、それだけは絶対に避けたいといつも思っているんですね。
真鍋
僕は、『スペシャリスト─自覚なき殺戮者─』というナチ戦犯のアイヒマン裁判のドキュメンタリー映画を観たときに、「あそこに出てくるアイヒマンは自分かもしれない」と思ったんです。アイヒマンは裁判で「命令されたことを実行しただけだ。自分に責任はない」と主張します。それは大なり小なり、どの時代でも、どんな局面でも、日本社会のそこら中で、みんな生きていく上で「仕方がない」と自分をだましながらやっているはずなんです。僕は、編集の仕事をする上で、そういう恐ろしさみたいなものを形にしたいんです。それが自分にとって、本づくりの原点になっているのかなと。
その原点というのは、中学生のとき本多勝一の『中国の旅』を読んだんですが、そこで初めて平頂山事件のことを知りました。日本軍が中国・撫順近郊の集落・平頂山の住民を殺害した事件です。「このときの日本兵と自分の違いは何だろう?」と考えたわけです。あの状況で自分が日本兵だったら、「撃ちたくありません」なんて言えるわけがないと思ったんですよ。当時の僕は、学校社会の中で同級生の顔色をうかがいながら過ごしていて、そんな自分に違和感をもっていたからです。思春期特有の自意識過剰からくるものだったのかもしれませんが、とにかく周囲に引きずられやすい自分の弱さを克服したかった。そのために、柔道部に入ったり、医者になれば最前線に行かなくていいんじゃないかとか、法律を学べば暴力に抗えるかもとか、子どもながらにいろいろと悩みました。結局、戦争にならないように考えるのは歴史だと思って、史学科に入っちゃったんですけどね(笑)。
そうして社会人になり、編集者になってからは、自分も含めて「空気」に弱い日本人に「それでいいのか?」と、歯止めをかけるような本をつくり続けてきました。出版不況と言われ続けて、「嫌韓嫌中」本がベストセラーになるような時代に、自分は何のために本をつくっているのかと思ったら、子どもの頃から考えてきたことに、ひたすらこだわるしかないんじゃないかと思っています。
岩下
森さんは「加害者になるのが怖い」と言ったけれど、それは誰でもそうだと思うんですね。自分の手で誰かを傷つけたり殺したりするのは、すごく怖いことです。後から良心の呵責に苛まれるかもしれないし。ところが、戦争中の日本兵のように、まわりが撃てば自分も躊躇なく撃ってしまう。それが真鍋さんのおっしゃる「空気」ということだと思うんです。
今もまさに似たような状況で、「韓国ってしつこいよね」とか「中国って見苦しいよね」という「空気」が社会全体で共有されている。出版業界でも、みんな「嫌韓嫌中」本を出しているから「うちはもっと強烈な見出しをつけよう」と、どんどんエスカレートする方向に流れていますよね。だからこそ、すべての出版関係者は、本をつくる側の責任に気づいてほしいんです。
差別的なPOPがあっても驚かない
――出版界の最近のトピックとしては、書泉グランデのツイッターアカウントのツイートがネット上で大きな話題になりました(※)。あの事件についてはどう思われますか。
※書泉グランデの事件……9月26日、東京・神保町の大型書店、書泉グランデのツイッター公式アカウントに「嫌韓嫌中」本を積極的に推薦するツイートが掲載され、抗議が殺到。書泉グランデはツイートを削除、公式サイトで謝罪文を公開している。
森
私はもう、単純にビックリしちゃって。だって、あのツイートには「隣国が嫌いな方、なぜ嫌われているのか気になる方、植民地支配…」と書いてあって。しかも著者が「在特会」代表の桜井誠で、タイトルが『大嫌韓時代』でしょう。それが「オススメ」って…。
岩下
僕は正直「またか」くらいの感想でしたね。大型書店のほとんどは、公式サイトにベストセラーになっている「嫌韓嫌中」本をいっぱい載せているし、店内にはヘイトスピーチまがいのPOP(※)が置いてあるから。書泉グランデは、右も左も何でも置く書店なので、ツイート自体にはさほど驚きはなかったですね。
※POP…ポップ。「Point of purchase advertising」の略。主に小売店で販売を促進するための広告・宣伝媒体を指す。書店では、版元(出版社)がつくった書籍のPRのために置かれているカードやパネルなどのこと。
真鍋
僕の感想も、岩下さんとまったく同じです。書泉グランデは、POPやいろいろなものがゴチャゴチャ置かれていて、鉄道・ミリタリー・旅・精神世界なんかが好きな人がわくわくするような本屋さんですよね。そういう売り場でどうやったら本が売れるかと考えたら、ああいうツイートになったんでしょう。
僕はむしろ「どういう人が書いたのかな?」という興味がありました。僕も営業から自分が担当した本のPOPをつくるよう頼まれることがあります。そのときは、どういう書店の、どの棚で、どんなお客さんが来るかを想像しながら、原稿をつくりますので、書泉グランデの人も同じように、自分のツイートがどういう反響を呼ぶかなんてまったく考えず、普段接している人に本を買ってもらいたいと思ったら、こんな言葉が出てきました…という程度のツイートだったんじゃないでしょうか。隣のおじさん、おばさんに「買ってね」みたいな文面でした。
――ハンナ・アーレントの言葉、「凡庸な悪」のように、普通の人でも組織の中にいたら、思考が止まって何でもできてしまう、ということでしょうか。
岩下
組織の中ということもありますが、資本主義の大きなシステムの中で、ニーズがあればそこに商品が供給されるわけですから、何も考えずにやっていれば自然とこうなる。
こう言うと怒られそうですが、僕自身ある時期から書店に行くことが苦痛になってきたんですよね。どの書店でも、愛国本やバッシング本が大々的に宣伝されていて、うんざりするというか。
自分がつくった本がどこに置かれているか確かめに書店に行くんですが、まわりはそういう本ばっかりで、「これじゃ、とても見つけてもらえないし、そもそもそういう関心の読者はここに来ないよな…」と暗い気持ちになります。もはや全国の書店で、読書好きの人たちにとっては、心地の悪い状況がジワジワと広がってきているんじゃないか。
業界構造が生む「嫌韓嫌中」本
森
だけど、「嫌韓嫌中」本が増えていることの前提には、新刊発行点数が多すぎるという出版界の構造があって、それは自分たちにそのまま跳ね返ってくる話なんですよね。多様なニーズに応じてという面もありますが、必ずしも古典になるような息の長い本ばかりつくっていないと、自分でも自覚がありますから。そういう構造があるので、そもそも書店さんは日々大量に配本されてくる新刊本を満遍なく売るのは不可能だし、売れている本をもっと売ろうとすれば、こういう結果になってしまうと思うんですよ。
岩下
そう、それはあるんですよ。過剰に生産して投入しているのは出版社の側で、書店さんはそれを置いて少しでも売ろうとしているだけ。つらいんですよね、そこが。
新刊に比重がかかって、良書が書店の棚に長く置かれるというようなことを、もはや期待できない構造がある。結局、そういう最悪の状況の中で生まれてしまったのが、「嫌韓嫌中」本というジャンルだと思うんです。
――そういう意味では、出版業界の積年の問題が噴出して、“鬼っ子”になったのが「嫌韓嫌中」本なんですね。
岩下
もうひとつ同じ構造から発している問題として、新書の雑誌化というのがありますね。どこの出版社でも新書をつくるようになって、定価の安い新書が広がってきたことで、週刊誌のような単発のテーマで手軽につくっては、あっという間に消えていく、そんなつくり方をしてきた結果でもあると思います。
それぞれの出版社の一貫性みたいなものとか、整合性とか、その本が学問的に正しかったのかどうかとか、そうした責任の問われ方が一切なくなって、「売れたからいいでしょう」というつくり方を僕ら自身してきた。結果、出版業界自らが反知性主義を後押ししてきてしまったということもあるんでしょうね。
森
自分の仕事を振り返ってみると、私たちも、いかに内容をわかりやすくして、いかに定価を抑えるかという方向でつくってきた本がたくさんあります。わかりやすく提示するために、内容もどんどん角をとって、やさしく、やさしく書き改めていただく。
難しいことをわかりやすく書くって、本来は大変な作業ですよね。古典になるような教養新書を出している出版社が数社しかなかった時代は、執筆する研究者も編集者も、ものすごい苦労をしていたはずです。ところが今、出ている新書の内容は基本の基本というか、かつての教養書のような意味合いでのわかりやすさではない。これを読んだ人が、その先に難しいものを読むのだろうかと疑問に思うような…。新しい発見があるというより、自分が考えていることを後押してくれて安心できる。そんな本が多くなっているような気がします。自戒を込めてですけれど。
岩下
新書でも単行本でも、今は「こうだ」と断定する本のほうが売れるのは間違いない。そのためには、なるべく複雑さを排除して単純化し、揺れとか葛藤はないほうがいい。その点、「嫌韓嫌中」本はすごくわかりやすくつくってあって、タイトルや小見出しのつけ方などもよくできていると言われます。だけど、わかりやすければ内容は二の次というのは違うだろう、と。世の中のことをほんとうに正しく理解しようとすれば、単純化してはいけない部分というのは必ずあると思います。つくり手としては、そこにジレンマが常にあるんです。
やはり、本は形として残るものですから、後世から見て恥ずかしくない本をつくることを考えたいですよね。後々に対してちゃんと責任を果たせるのか、本をつくるときに、そこは絶対に忘れてはいけないと思います。
――それでは最後になりますが、「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」では今後どのような活動を行っていくのか、お聞かせください。
岩下
7月に開催したシンポジウムの内容をまとめた本が、10月30日に出ました。『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』というタイトルで、版元はシンポジウムで講師をしてくだった加藤直樹さんの著書『九月、東京の路上で』と同じ「ころから」という出版社です。
今、僕たちが会を始めた頃よりもさらに嫌韓嫌中や朝日新聞バッシングが勢いを増して、店頭ではバランスをとろうにもとれない状態だと思います。でも、この1冊をその隣に置いてもらうことで、今の状況を客観的に見る契機になるかもしれない。そういう形で、全国の良識ある書店さんに使ってもらえたら嬉しいです。
それから、準備中のプロジェクトとして、神保町にこの本の屋外広告を出したいと考えています。この間、三省堂や書泉といった神保町の象徴ともいえる書店が相次いでバッシングを受ける事態がありました。僕たちも、出版の象徴である神保町の大手書店で嫌韓嫌中を煽るようなことはやってほしくないという思いがあると同時に、それを書店への批判や否定で済ませたくはない。だから、本や本屋さんって面白いですよ、出版も捨てたものじゃないですよ、というメッセージを込めたいんです。
費用はクラウドファンディングを通じて集める予定です。多くの人の目に触れる広告を出すことは、業界内で無関心な人へのアピールにもなりますし、これからの出版の希望につながると思いますので、ぜひご協力ください。お願いします。
(構成・写真 マガジン9)
※「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」趣旨文はこちらです。お読みになり、賛同される方はご署名ください。
※クラウドファンディングについては、「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」のフェイスブックページに発表される予定です。
◎読者プレゼント◎
『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』(ころから)を
5名の方にプレゼントします。
ご希望の方は、こちらのご意見フォームより
記事名「その他、感想、ご意見、ご要望」をお選びのうえ、
件名を「NOヘイト!希望」としてお申し込みください。※申し込み締め切りは、11月12日(水)です。
(当選の発表は発送をもってかえさせていただきます)