
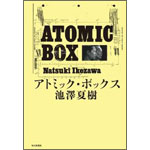 『アトミック・ボックス』(池澤夏樹/毎日新聞社)
『アトミック・ボックス』(池澤夏樹/毎日新聞社)
爽快な逃走小説
鈴木耕
亡き父に託されたもの、それは数十年前の「核の秘密」だった。その秘密を追う公安警察や謎めいた者たち。父の遺志を遂げるべく必死に逃げる主人公の美汐。追う者と追われる者、それを助ける市井の人々。この人々の優しさや考えの深さに共感する。これは、ぼくの好きな「巻き込まれ型サスペンス」のバージョン。著者の「核」に対する姿勢が明確に表れていて、その意味でも爽やかだし、テーマの重さをこれほど後味よく表現している小説もめったにない。一気読み確実の、夜更かし本。
 『ゼツメツ少年』(重松清/新潮社)
『ゼツメツ少年』(重松清/新潮社)
薄闇の中の希望…
鈴木耕
昨年9月に出た本だけれど、今年の毎日出版文化賞を受賞した作品。タイトルが物語るように「居場所」を失った少年たちの、ある種の逃亡小説で「ゼツメツ」とは、むろん「絶滅」の意味。「このままではぼくらゼツメツしちゃうよ」という少年たちの悲痛なココロを表現する言葉だ。いわば、「薄闇の中の希望」というしかない物語。ふたりの少年とひとりの少女(後半はもう一人の少女が参加する)がどこへ行きつけるのか。小説家のセンセイへの少年からの手紙と、その作家の別の小説の中の登場人物が邂逅するという、わりと複雑な構造を持つけれど、最終章まで目が離せない。
 『東京自叙伝』(奥泉光/集英社)
『東京自叙伝』(奥泉光/集英社)
壮大な妄想歴史書
鈴木耕
これまたそうとうに込み入ったストーリー。何しろ、主人公は東京という土地そのものなのだが、登場人物がやたらと変身(いや、人物ではなく猫や鼠などにまで変身)する。ややこしいことに、「変身前の人物」と「変身後の私」が出会ったりするのだから、面白さもぶっ飛び級。第1章から第6章まで、同じ人物だが違う主人公という凝った仕掛け。こう書いてもよく分からないだろうけれど、読めば納得の面白さだ。東京を語りながら、この国の歴史そのものを俯瞰する。なにしろ、江戸から明治維新、大正デモクラシー、昭和と戦争、戦後の混乱、新興宗教、CIA、TV放送開始、原子力発電所、高度成長、バブルとその崩壊、大震災…と目まぐるしく変わる東京の地霊の物語。しかも「アレは私がやった、コレも私の手柄、ソレも…」と、歴史の変わり目の大事件や出来事は、ほとんど主人公の仕業だというのだから妄想も超弩級。『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』や『竹内文書(たけのうちもんじょ)』などという「偽書」が有名だが、それらに匹敵するような「妄想歴史偽書」である。
 『暗黒寓話集』(島田雅彦/文藝春秋)
『暗黒寓話集』(島田雅彦/文藝春秋)
ザワザワと背筋を何かが這うような…
鈴木耕
不気味な未来を照らすような短編集。タイトルにもそれが表れる。曰く「死都東京」「夢眠谷の秘密」「名誉死民」「透明人間の夢」「神の見えざる手」…等々。例えば「死都東京」。4行ずつの短いセンテンスが連なる構成で、“死んでしまった人間”が、死都に甦る(?)、それも1978年の死都東京。混乱しつつも彷徨する。そして、結末は…。
この本の「はじめに」に、著者はこう書いている。「…人の話を大人しく聞き、反論を控えてしまう人が多い中、声が大きい厚顔無恥な人の恫喝的主張ばかりが目立ってしまう。コトバには様々な活用法があるから、それをどう使おうが勝手ではあるけれども、隣国への憎悪をまき散らしたり、使い古された愛国、憂国の叫び、呟きを垂れ流すより、個々の妄想や回想を温め、孵化させる方が、まだこのふざけた世の中に清涼をもたらすことができる…」。つまり、それを小説化した短編集なのである。
 『未来の記憶は蘭のなかで作られる』(星野智幸/岩波書店)
『未来の記憶は蘭のなかで作られる』(星野智幸/岩波書店)
過去から現在を照射する
鈴木耕
著者がデビュー以来、折に触れて書き続けてきた小説以外の文章から厳選したものを収録したエッセイ集。この本の最後に、著者は「私は『年代順』に縛られている…」と書いているが、それを逆手に取った構成だ。すなわち本書は、書かれた順序を逆にして収録している。2014年から始まって1998年まで遡っていく。なぜそういう構成にしたかは、読み進めればよく分かる。現在、何があるのか、それを生み出したものは過去のどこに萌芽があったか。次第に息苦しくなる現在という時点を、逆照射すれば見えてくるものは何か。ことに、2011年の息づまる感覚、「言葉を書く仕事なのに、何と言っていいのか分からない」のだ。そして2013年「宗教国家日本」と題された文章の、持って行きどころのない圧力の不快。作家の目に映った時代。
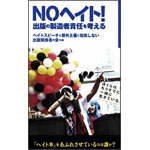 『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』(ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会編/ころから)
『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』(ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会編/ころから)
志がかたちになった!
鈴木耕
あからさまな「売らんかな商法」に突き進む出版界の現状に、批判の一石を投じた本。差別を助長し、他国を誹謗し、それでも売れれば何でもいいのか。出版界のあまりのていたらくに、ようやく若手出版人たちが立ち上がった。大きな評価を受けた名著『九月、東京の路上で』(ころから)の著者・加藤直樹さんの論考や、書店員さんたちの反応、シンポジウムでの記録、法規制など、ヘイトスピーチに関わる問題点を網羅した初めての本。ぜひ、読んでほしい志に溢れた本である。
 『またがりビトのすすめ
『またがりビトのすすめ
「外国人」をやっていると見えること』(姜誠/岩波書店)
生き辛さを逆手に
鈴木耕
これは「シリーズここで生きる」の中の1冊。著者は在日コリアン三世で、ジャーナリスト。これがとてもさわやかで面白い。著者が置かれた「在日」という立場が、日本という国で生きていく上で容易ではないことは誰でも想像できるだろう。ことに、最近のヘイトスピーチやヘイトデモ、さらには書店の棚に蔓延するヘイト本の類い、生きていくのに圧迫感を受ける感覚は、著者も持っているはずだ。だが、著者は「またがりビト」と自己規定する。つまり、差別を逆手に取って「どれかのアイデンティティにすがるのではない、真の個人として生きる戦略こそ『またがりビト』。四歩先の思想がここに!」というわけだ。その実践が、第三章「学校を作ってみた!」に描かれる。公的援助のない外国人学校をさまざまな人たちの協力の下に作り上げる。ドキュメンタリーとしても一級品。ほんとうに、いい本ですっ!
 『原発利権を追う』(朝日新聞特別報道部/朝日新聞出版)
『原発利権を追う』(朝日新聞特別報道部/朝日新聞出版)
腐臭漂うノンフィクション
鈴木耕
原子力ムラの暗い腐臭漂う闇…、と書けばあまりに紋切型だけれど、そうとしか言えないおぞましさに充ちた本だ。電力会社がどうやって地域支配、さらには政治家支配を成し遂げていったか、生々しい証言と証拠によって、つぶさにそれを明らかにしていく。ことに、原発城下町での支配力は圧倒的で、カネの力を背景に、物言えぬ住民を作り上げていく手法には背筋が寒くなる。しかも、陰で暗躍するゼネコンから、膨大なカネが流れ込み、それを差配する人物の黒い影もちらつく。並みのサスペンス小説よりも、ずっと恐ろしい迫力に満ちた本だ。最終章の「伝説の人物」の長い告白が、読ませる。
 『原発広告と地方紙――原発立地県の報道姿勢』(本間龍/亜紀書房)
『原発広告と地方紙――原発立地県の報道姿勢』(本間龍/亜紀書房)
金が歪める報道鈴木耕
同著者による「原発と広告3部作」の第3弾。『電通と原発報道』『原発広告』に次ぐ著書。なにしろ、収録されている広告紙面が半端じゃない。その数なんと403点。グリーンピース・ジャパンの協力で収集したということだが、電力会社、電気事業連合会、政府広報などがよってたかって地方紙を籠絡していった様子がまざまざと浮かび上がる。ことに、広告の装いをしない「タイアップ広告」や「ヤラセ記事」による原発プロパガンダの凄まじさ。カネで頬をひっぱたく原発マフィアの正体をここに見る。
 『東京ブラックアウト』(若杉冽/講談社)
『東京ブラックアウト』(若杉冽/講談社)
電力モンスター・システムとは?
鈴木耕
匿名官僚の原発小説、『原発ホワイトアウト』に続く第2弾。今回は特に、官僚たちの生態が詳細に描かれていて興味をそそる。本書では、政官民報学すべてが複合したシステムを「電力モンスター・システム」と名付け、この究極の力の恐ろしさを描く。小説としては生煮えの部分も多いけれど、実際の高級官僚でなければ知り得ない情報が、前作よりも多く盛り込まれている。登場人物にほぼモデルがいることが、作中の名前によって明らかになる。さらに興味を引くのは天皇の存在。第5章「天皇と首相夫人と原発と」を読むと、この情報の出所が知りたくなる。天皇が原発に関してどう考えているのか…。そして、日本人は2度目の原発事故が起きなければ目覚めないのか、という著者の悲痛な叫びもまた…。
 『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』(矢部宏治/集英社インターナショナル)
『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』(矢部宏治/集英社インターナショナル)
基地と原発と憲法と…
鈴木耕
タイトル通り、いまこの国を覆う不合理の象徴が「基地」と「原発」であることを見据え、その歴史的経緯を掘り起こして、謎解きしていく。この謎のキイワードこそ「日本国憲法」だ。憲法が制定された過程を追いながら、それが日本に与えたねじれを検証する。そして、憲法よりも上位に来るアメリカという存在、日米安保条約と日米地位協定。実は、同じことが福島原発事故にも言える。それが日米原子力協定という仕組みなのだということを、著者は明らかにしていく。ベストセラー・シリーズ「戦後再発見双書」(創元社)の企画編集者である著者が、怒りをこめて著わした1冊。
 『沈みゆく大国 アメリカ』(堤未果/集英社新書)
『沈みゆく大国 アメリカ』(堤未果/集英社新書)
日本の未来を投影する惨状
鈴木耕
すでにベストセラーになっているし、多くの書評などで取り上げられているから、あまり多くの評言は要らないだろう。けれど、一言だけ強調しておきたい。これは、明日の日本の姿なのだ、と。帯に落合恵子さんがこう書いている。「救いを求める崖っぷちの声が聞こえる。あれは、明日の私たちの声、だ」。まさにその通り。アメリカの医療保険制度改革の実態がいかに厳しいものであるか。アメリカのすべての領域での支配を達成してしまった1%のスーパー・リッチ(超富裕)層。格差拡大の波が押し寄せ始めた日本も、この姿から無縁ではない、との著者の指摘に真剣に向き合わなければ。
 『自堕落な凶器』上下(アリエル・S・ウィンター、鈴木恵訳/新潮文庫)
『自堕落な凶器』上下(アリエル・S・ウィンター、鈴木恵訳/新潮文庫)
1冊で3冊分の愉楽
鈴木耕
とにかく洒落た作品。どこが洒落ているか? 3編の独立した小説としても読めるが、第1部『マルニヴォー監獄』は警察小説、第2部『フォーリング・スター』が私立探偵もの、第3部『墓場の刑事』は犯罪小説…と、同じ著者で登場人物も重複しているのだが、テイストがまったく違う。つまり、ジョルジュ・シムノン、レイモンド・チャンドラー、ジム・トンプスンという、ミステリやハードボイルド小説ファンならだれでも知っている大作家へのオマージュでもあるからだ。文体模写、いわゆるパスティーシュ。ことに、第2部のチャンドラー節は見事というしかない。1冊(いや、上下2冊)で、3人分堪能できる珍しい作品。
 『7人目の子』上下(エーリク・ヴァレア、長谷川圭訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)
『7人目の子』上下(エーリク・ヴァレア、長谷川圭訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)
福祉国家の闇
鈴木耕
これは、ぼくが最近凝っている北欧ミステリ。舞台はデンマーク・コペンハーゲン。この地で名高い児童養護施設に秘められた謎…という設定だから、ゾクゾクする。この施設で育った子どもたちが辿る運命と、政府中枢に渦巻く陰謀。ポリティカル・ミステリでもあるけれど、そうとうに錯綜していて、最後までストーリー展開が読み切れない。社会福祉が充実しているとされる北欧デンマークの実態も…。
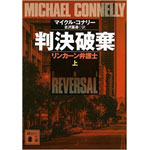 『判決破棄 リンカーン弁護士』上下(マイクル・コナリー、古沢嘉通訳、講談社文庫)
『判決破棄 リンカーン弁護士』上下(マイクル・コナリー、古沢嘉通訳、講談社文庫)
リーガル・サスペンスの醍醐味
鈴木耕
わりと理屈っぽいせいか、ぼくは法廷もの、いわゆるリーガル・サスペンスというジャンルが気に入っている。これもその1冊。しかも、マイクル・コナリーの刑事ハリー・ボッシュものと、リンカーン弁護士ミッキー・ハラーものは、どちらもぼくの愛読しているシリーズ。そのふたりが協力して犯人を追いつめ、法廷で丁々発止とやり合うのだからたまらない。これも、徹夜本。でも、ひとつだけ不満が残る。それが何かは、ここには書かない。読んでみて、不満を感じたあなたは、ぼくとかなり感覚が似ているはず…。
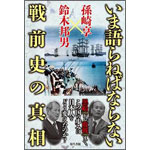 『いま語らねばならない戦前史の真相』(孫崎享・鈴木邦男/現代書館)
『いま語らねばならない戦前史の真相』(孫崎享・鈴木邦男/現代書館)
過去を振り返り、現代の問題を照射する
芳地隆之
『戦後史の正体』の著者である孫崎享が、愛国者・鈴木邦男と、近代国家となった日本が完膚なきまでに叩きのめされた第2世界大戦までの歴史をじっくり語り合う。莫大な戦費を注いで、かろうじて勝った日露戦争を、神国・日本の勝利とみなしてから、この国はおかしくなっていった。日本はそれまでの外国から学ぶ姿勢を捨て、相手国の置かれた状況を理解しようとせず、軍事力の強化を進めて、外交戦略や軍事作戦における失敗の責任の所在を曖昧にさせたまま破滅へと向かったのである。そうした戦前史は、現在の安倍政権の危うさ――世界情勢を正確に見抜く能力の欠如、中国との危険な対立、特別秘密保護法がもつ恐ろしさなど――につながってくる。
孫崎は鈴木に「自民党の憲法改正法案に記されている天皇の国家元首化は天皇を政治利用するものでしかなく、それに対して右翼は怒らないのか」と問い、「右翼の大半はいまの憲法に囚われていると考えている(天皇自身は現憲法をよきものとみているにもかかわらず)」との鈴木氏の答えに考え込み、鈴木の方は、「かつての戦争を開始する際は宣戦布告をしなければならないことはなく、真珠湾攻撃の奇襲攻撃が卑怯だとは言い切れない」という孫崎の指摘に驚く。
過去を振り返ることによって現代の問題を照射する2人の対話は、自ずとあるべき未来を模索していく。私たちは再び過ちを繰り返すのか。時代が危険な曲がり角に立っているいま、タイムリーな書籍が刊行された。
 『忘れられた日本人』(宮本常一/岩波書店)
『忘れられた日本人』(宮本常一/岩波書店)
共同体存続のための知恵を学ぶ
芳地隆之
著者は1939(昭和14)年来、日本各地を歩き、そこに住む老人たちの声を集め、それらを文字にしていった。そこから見えてくるのは、かつての農村がもっていた共同体存続のための知恵のようなものだ。たとえば長野県諏訪湖の畔の村では、60を過ぎた年寄りが村の寄合で各家庭の抱えている問題を話し合う。(家の恥となるような)悪いことも隠していると問題を深刻化させるだと考えるからだが、それを寄合いの外には決して口外せず、自分たちで調停しようとする。現在の私たちは、農村を閉鎖的で異端を許さないような社会と想像しがちだが、本書は、そこに現在のセーフティネットを考える上でのたくさんのヒントがあることを教えてくれる。いまに生かせるエピソードが満載の本だ。
 『日本国憲法 大阪おばちゃん語訳』(谷口真由美/文藝春秋)
『日本国憲法 大阪おばちゃん語訳』(谷口真由美/文藝春秋)
漫才のようなしゃべりで憲法を解きほぐす
仲松亨徳
方言を文章化するのは、意外と難しい。語尾の活用の自在さ、ニュアンスの非普遍性などがネックとしてあるのだろう。この書は日本国憲法を大阪弁、しかも「おばちゃん語訳」した。先述の難しさをクリアし、漫才のようにしゃべるおばちゃんの言葉で、憲法を解きほぐす。憲法の文章は決して難解なわけではないが、それでも法律というだけで尻込みしてしまう人も少なくないだろう。本書は言わば「言文一致運動」なのかもしれない。大阪のぶっちゃけ文化は、差別意識が入り込むことで開き直りの反知性主義化したが、その逆ベクトルの可能性を示唆した書だ。
 『僕たちの国の自衛隊に21の質問』(半田滋/講談社)
『僕たちの国の自衛隊に21の質問』(半田滋/講談社)
自衛隊についてイロハのイから教えてくれる
寺川薫
来年の統一地方選挙後、集団的自衛権の行使に向けた法案が国会に提出される予定で、再び「この国のかたち」をめぐる議論が活発になるだろう。さらに、ここ数年のうちに憲法九条改定の是非が国政の場において具体的に議論されることになるかもしれない。何しろ安倍政権が長期政権になる可能性が大きくなってしまったのだから…。安全保障や憲法に関わる議論とは、つきつめて言えば「自衛隊をどうするのか」ということ。海外派兵を積極的に行なう軍隊にするのか、少なくとも専守防衛の範囲内での活動に留めるのか、もしくは災害救助や国境警備専門の組織として特化させるのか――。そんなことを考える際に、自衛隊についてイロハのイから懇切丁寧に解説してくれる本書はうってつけだ。本書を読めば、多くの人が自衛隊の歴史、規模、組織、役割、そして政治(家)との関係などについて、あまりにも知らないことが多いことに気づかされるだろう。
著者はあとがきで、自衛隊や戦場の実情を知らずに「机上の空論」を述べる政治家を批判しているが、それは私たちにも向けられた言葉のようにも思える。「自衛隊の現実」を知らずに集団的自衛権の行使や憲法改定の是非を、あーだこうだ言うのは、まさに「机上の空論」だからだ。
本の帯に「将来、戦場に行かされる君たちへ――。」という文句があるように、本書は“若者向け”の体で書かれているが、「この国のかたち」を考える際の参考書として、年齢や主義主張に関係なく、多くの人に読んでもらいたい一冊だ。
 『世界を見るための38講』(宇都宮大学国際学部 編/下野新聞新書)
『世界を見るための38講』(宇都宮大学国際学部 編/下野新聞新書)
ローカルな問題は、グローバルな問題からやってくる
北川裕二
本書によれば、宇都宮大学国際学部は「国立大学唯一の国際学部」なんだそうだ。えっ、そうなの!? これだけグローバルだ、なんだと騒ぎ立てている昨今、国立大では宇都宮大学しかないとは。これはもう、本書を読むしかない。すると驚いた。「新書」という枠組を大幅に越えた読み応えのあるものとなっている(文字級数も小さく行間も狭い!)。本書は、宇都宮大学国際学部の教員38名の各研究分野に関するエッセイを集めたもの。シェイクスピアから日本のホームレスまで、実に多種多様なテーマを扱っており、一言でまとめることなどできない。が、強引にまとめると、本のタイトルにある「見る」にその答えがある。どうして本書のタイトルは「世界を知る」ではなく、「世界を見る」なのか。
「見る」ことは「知る」ことに繋がるが、「知る」ことが「見る」ことに繋がることは少ない。知ってしまえば、見る必要などないと考えがちだからだ。さらに、「見る」ことは、そこに「いる」からこそ「見る」ことができる。とすれば、「見る」とは、今ここに「いる」ことと、どこか遠い世界を「知る」ことの橋渡しの役を担っているといえるだろう。難しく言えば、「見る」とは、「いる」と「知る」の媒介者的な概念であるということだ。
こういう観点で38稿を読むと、そのどれもが、「いる」と「知る」をどう関連づけるかという根本的問題に関わっていると気づく。今ここでのローカルな問題が、実は世界からやってくるグローバルな問題の一局面であるということ。一方で、ローカルで些末なものに過ぎないと見做されていたものが、一挙にグローバルな破局をもたらす巨大事故に連鎖していく原因ともなる。「見る」とはしたがって、このミクロ・レベルとメタ・レベルの複雑で多様な運動の<中間>にいて、どちらの領域にも目配りしながら、いかに世界を見据えていくかということになるだろう。
宇都宮大学国際学部において、「3・11下の世界」でアクチュアルに対応している学者の熱意が伝わってくる。





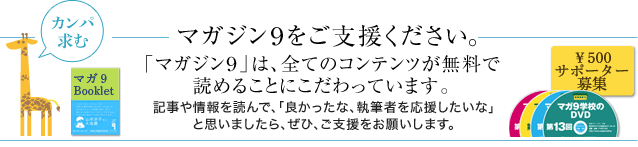

本のご紹介有難うございます。
私はtwitterをしないのですが鈴木様のはいつも読んでおりミステリー好きだということは存じ上げております。
特捜部Qの「檻の中の女」、あとがきに映画制作中とありましたが、1月3日からヒューマントラスト渋谷で「未体験ゾーン」の映画のなかで何回か上映されますよ。HPをご覧になってください。私もどのように仕上がっているのかとても楽しみにしているところです。日本ではデンマーク映画もあまり上映されませんし…。
お便り、ありがとうございます。また、面白い本を見つけたらお知らせしますね。そういえば「ミレニアム」の映画はいかがでした? ぼくはつい、全部観てしまいましたが…。
「冬休みに読みたい本(2014—2015)多分、ハズレなしの読書案内」として、『帝国の慰安婦』(朴裕河 著)を私は紹介したい。
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=16443
先ずは、著者である朴裕河のFacebookに「本の内容の一部をまとめたのでアップしておきます。」という投稿があるので、それを参考にするのが一番であろう。
https://www.facebook.com/notes/705074766186107
本書の「帝国」への批判については、マガ9の愛読者の大半は「水が染み入る」様な、一部の人には「ぬるい」という様な感想を抱くであろう。
しかし、「冷戦的思考」についての朴の批判について、マガ9の愛読者の一部の人は苛立つことになるだろう。
本書の「冷戦的思考」の考察は、Facebookに寄稿されていた文章よりも遥かに手厳しい。
例えば、「在特会」はまさしく「冷戦的思考」の権化であろう。
しかし、例えば田母神論文問題で田母神を(麻生政権が)航空幕僚長から更迭したという自民党の多様な側面の一部や、肝心要の韓国人慰安婦が求める「『謝罪と賠償』以外の解決法」など、「不必要な事実」を平然と無視する韓国・日本の運動家達もまた「冷戦的思考」の権化ではなかろうかという指摘は、私としては非常に興味深い。
突き詰めれば、「在特会」を激しく非難する人々も「在特会」と同様に、「冷戦的思考」の権化ではなかろうかという疑念が生まれることになるだろう。
何れにせよ、「フェミニズム」という古典的なスタンスからの推察ながらも、「帝国的(あるいは愛国主義的)」や「冷戦的思考」から完全に独立したスタンスからの推論は、いわゆるオルタナティブ性を強く感じ、私としては新鮮な感想を持った。
本書に対し、賛否両論は噴出するであろうが、「まっとうなリベラルの著書」という本書に対する認識を、万人が共有することは間違いないであろう。
また、「基地問題の解決」についても本書は軽く触れているが、本当に「基地問題」を解決したいと切望する人は、まずは本書を手に取る方が良いのではなかろうか?