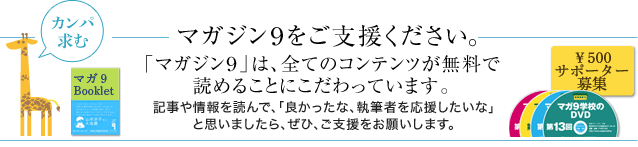(日本2016年/片渕須直監督)
※公式サイトにリンクしてます
映画館で幸せな時間を過ごした、といっては語弊があるかもしれない。
漫画家・こうの史代には、同じく戦争を題材にした作品『夕凪の街 桜の国』があるが、これが戦後、原爆の後遺症に苦しむ人々を焦点にしていたのに対し、本作品は、満州事変の2年後の昭和8年から日本の敗戦の翌年となる昭和21年、戦争を続けた日本が破滅するまでを時代背景としている。主な舞台は軍港のある広島県呉市だ。度重なる空襲、そして隣の広島市への原爆投下で無数の人々の命が奪われた。理不尽で残酷な戦争に対する怒りが湧く。にもかかわらず、私は冒頭に書いたような感覚でスクリーンを見ていた。
忘れられない2つのシーンがある。
ひとつは、呉の港近くで道に迷った主人公のすず(広島から呉に嫁いだ)が道端でしゃがみ、木の枝でスイカやキャラメルの絵を描いているのを見た遊郭の女性が、紙にわらび餅やはっか糖も描いてくれないかとせがむ場面。
もうひとつは、すずの幼なじみである水原哲が、自らが乗る軍艦が呉に寄港したのを機に、水兵姿で彼女の嫁ぎ先に現れ、別れ際に「この世界で普通でまともでおってくれ。わしが死んでも一緒くたに(中略)英雄にして拝まんでくれ。笑うて、わしを思い出してくれ」という場面。
すずと交わす言葉のやり取りの後ろにある、遊女と水兵の生い立ちや思いを想像する私の中で普段は顔に出さないような感情がわきあがり、自ずと涙がこぼれてきた。
冒頭の「幸せ」は、スクリーンに登場する人々への愛おしさであった。
監督の片渕須直は1960年生まれ。こうの史代は彼より若い1966年の生まれである。ともに高度経済成長期に幼少期を送ってきたが、主人公すずの声を演じた能年玲奈あらため「のん」にいたっては1993年である。生まれたときにはバブルも終わっていた。
戦争を知らない世代が描き出したこの作品を見ると、戦争の語り部は、時代とともに表現方法を変えながら、引き継がれていくのだろうなと思う。写実的な絵の中にときおり放り込まれる抽象的なタッチには、「なぜこの作品がアニメでなければならなかったのか」の説得力がある。
芸術の真髄は、受け手のなかに眠っている感情を喚起することにある、と言い切ってしまおう。
(芳地隆之)