日本の近現代史をなぞると、どうしても避けて通れないのが「満州」だ。1932年から1945年までの13年だけあった、幻の国。ある人は嫌悪を、ある人は郷愁を、ある人は理想をそこに投影する。そういえば、現首相の祖父も、この地で大物官僚として君臨したんだっけ。
この地に存在した満映(満州映画協会)を舞台にした、『さらば八月の大地』を東京・新橋演舞場で観劇した。演出は映画監督の巨匠として知られる山田洋次さん、脚本は映画『月はどっちに出ている』や舞台『パーマ屋スミレ』などの鄭義信さんという豪華な顔合わせだ。山田さんの父は満鉄(南満州鉄道)社員だったそうだ。
満映は満州国建国から遅れること5年、1937年に設立された映画製作・配給会社。当地の映画市場を独占し、日本文化帝国主義の尖兵としての役割を果たした。と同時に、日本の「活動(写真)屋」が集い、まるで梁山泊のような活気に溢れていたとも言われている。
主人公はチーフ助監督・張凌風(中村勘九郎さん)。中国人でありながら満映で働く彼は、揉め事があっても何とか収めていく。ある日、日本から流れてきた撮影助手・池田五郎(今井翼さん)が不躾に近寄ったため、凌風は態度を硬化させる。五郎には悪気は全くないのだが、言葉の端々に「満人にしては」「満人のくせに」と出てしまうのだ。
凌風の恋人・陳美雨(檀れいさん)は主演に抜擢されるが、満映の作る映画なので日本に都合のよい内容。それが凌風には我慢ならない。王国慶(田中壮太郎さん)の脚本が気に入らぬ監督は、内容を勝手に直してしまう始末。それでも映画に情熱を傾ける凌風・五郎・国慶の3人は、いつか一緒に映画を撮ろうと誓い合う…。
満映では日本人と中国人の待遇には相当な差があった。日本語のできる人はともかく、他は皆雑用係で腰掛けしか与えられず「あれ買って来い」などと顎で使われるだけだった。戦後、日本の人形アニメーションの第一人者となった持永只仁さんはこれに憤慨し、当時線画と呼ばれたアニメーションの制作を中国人に指導して感謝されたという話もある。
山田洋次さんは次のように語っている。「日本人は自分たちのことを兄貴、中国人のことを弟であるように思ってつけあがっていた。『教えてやる。指導してやる。』発想はすごく傲慢だ。でも中国人は下手に抗えなかった。食っていかなければならない状況と、映画の先進国だった日本から学ぶという気持ち。当時の中国人スタッフがどんなにつらい、屈折した気持ちだったか」
満州国のスローガンは「五族協和」「王道楽土」。しかし実態は伴わぬまま、スローガンだけが上滑りしていた。何よりも日本人が「満人」と一括りにして差別していた。劇中では五郎が当初そうだったが、観念だけの「満人」ではなく、彼ら一人ひとりと向き合うことで、その考えはなくなっていく。
ラストシーンは、日本の敗戦によって凌風も美雨も、五郎も国慶も、皆散り散りに。敗戦国民になったことを受け入れられぬ日本人と、中国人の温度差は如何ともしがたい。ほろ苦い結末だが、それでも映画に注ぐ情熱は、好きだからこそ民族を超えて理解しあえるのだろう。(中津十三)
※ 『さらば八月の大地』は東京・新橋演舞場で11月25日まで。詳しくはこちら。





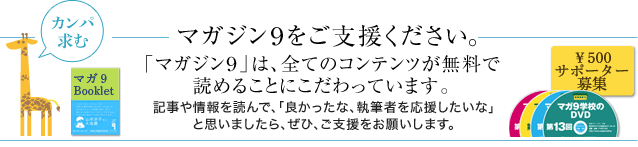

「中国人は○○だから嫌い。」などと、くだらない雑誌と同じようなことを言っていた人が、
あとで知り合った中国人の友達や知り合いには親切にしていました。
そういうところに、問題のカギがあるのかもしれないと思いました。
マスコミにつくりあげられた虚像としての観念的な「中国人」像。
これに基づいて差別や敵意の煽りが行われているのかもしれない。
しかし、実際の彼らに接すれば、日本人にいい人も悪い人もいるのと同様
中国人もいろいろで、「○○人だから」とひとくくりにするのは難しいと感じる。