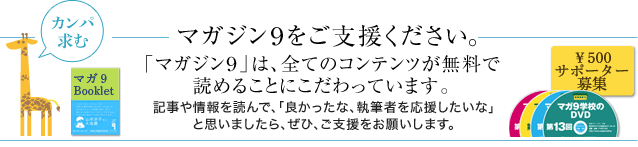その月に書かれた新聞やテレビ、雑誌などからジャーナリスト柴田さんが
気になったいくつかの事柄を取り上げて、論評していきます。

今年の夏は、ひときわ暑かった。物理的にも温度の高い日がつづき、寝苦しい夜がつづいたが、そのうえにメディアを通じて伝わってくるニュースに、なんとも「暑苦しい」ものが多かったからだ。
といって、ロンドン・オリンピックのことを言っているわけではない。オリンピックは、時差の関係で寝不足にこそなったが、むしろ「寝苦しい夜」を救われた部分も少なくなかった。多少、国威発揚にこだわりすぎのところはあったが、やはりスポーツはさわやかでいい。
ただ、オリンピックに関してひと言、皮肉を言わせてもらうと、8月20日のメダリストの銀座パレードに、どのメディアも「50万人の人出」と主催者発表の数字しか報じてなく、原発デモでは主催者発表の数字より極端に少ない警察推定の数字は、どこを探しても見つからなかった。
ところで、今年の夏をひときわ暑苦しくしたニュースは、政界、増税、原発といろいろあるが、私が最も暑苦しいと感じたニュースは、竹島と尖閣諸島をめぐる領土紛争の騒ぎだった。この8月、まず韓国大統領が突然、竹島(韓国名、独島)に上陸、つづいて香港の活動家や日本の地方議員らが尖閣諸島に上陸して、日韓、日中の両国間にトゲトゲしい空気が一気に高まった。
国際紛争のなかで領土争いほどやっかいなものはない。ナショナリズムを刺激し、国民感情が熱くなるからだ。人も住んでいない小さな島をめぐって争うよりは、両国が譲り合って仲良くするほうが、どれほどプラスが大きいか、理性では分かっていても、なかなか言い出せないものである。
まして現在、竹島は韓国が、尖閣諸島は日本が実効支配をしており、それぞれ実効支配をしている国は「領土問題は存在しない」と主張しているのだから、いっそうややこしくなっているのだ。
実効支配している韓国の大統領が、わざわざ竹島に上陸して対立を煽ったのはなぜなのか。従軍慰安婦問題をめぐって冷ややかな日本側の対応に「業を煮やして」と解説されていたが、それより大統領選挙が近づくなか、人気が低迷している李明博大統領が支持率の回復を目指して打った手だというほうが分かりやすい。
昔から落ち目の政治家は、外に敵をつくって国民のナショナリズムを煽るのが常套手段だと、洋の東西を問わず、いわれている格言があり、日本のメディアにもそういった解説が一斉に報じられた。現に、竹島上陸後、李明博大統領の支持率は10%も跳ね上がったという報道まであった。
一方、尖閣諸島への香港活動家の上陸は、中国政府の暗黙の了解のもと、船を仕立てての大仰なデモンストレーションだったが、こちらの騒ぎのそもそもの仕掛け人は、日本側だった。石原慎太郎・東京都知事がこの6月、尖閣諸島の買い取り計画を発表、寄付金を募集したら20億円ものカネが集まったのだ。
もともと日本が実効支配しているうえ、東京都とはまったく関係のない尖閣諸島を買い取るなんて、人気取り以外のなにものでもないのに、日本のメディアは、ほとんど批判らしい批判もしなかった。せめて韓国大統領に対して示した解説くらいは、石原都知事に対してもあってしかるべきだったのではないか。
また、香港の活動家のあとに尖閣諸島に上陸した日本の地方議員ら10人の行動などは、日本にとって何のプラスもない、ただ中国の国民を刺激するだけの行為なのに、メディアの批判は弱かった。
メディアにとって、領土紛争が扱いにくいテーマであることは、よく分かる。煽ってはならないことは当然だとしても、かといって相手国にちょっとでも理解を示すような言動をとれば、「弱腰だ」「軟弱だ」さらには「非国民だ」という非難までが「愛国的な人々」から寄せられるのである。
ナショナリズムは相互に刺激しあうとどんどん高まっていく性癖があり、今回の紛争でも、韓国大統領の発言は天皇の謝罪要求にまで及び、野田首相の抗議の親書を突き返すという異例の対応までやってしまった。それに対し日本側も突き返しに来た外交官を外務省に入れないというような措置までとったのである。
こうした状況に対する新聞論調は、8月24日の読売新聞の社説の書き出しが、最も象徴的である。「領土問題では、毅然として自国の立場を主張するとともに、平和的な解決を冷静に追求することが肝要である」とある。
毅然として、ただし、平和的に冷静に、という主張はどのメディアにも共通するものだといっていい。しかし、この二つの両立が難しいのだ。読売新聞の社説もこのあとの言葉は、どんどん「毅然」のほうに寄っていって、全体の見出しは「民主は『配慮外交』を反省せよ」となってしまうのだ。
領土紛争ではメディアが熱くならないことと、政治家や外交官が自国の主張だけにこだわらず、相手国の言い分にも耳を澄ますことが大事だ。その点、石原都知事が尖閣の購入計画を発表したとき、中国駐在の丹羽大使が「日中関係に重大な危機をもたらす」と語ったことが咎められ、注意処分と更迭論に発展したのに、擁護するメディアがまったくなかったことには驚いた。
たとえ自国民の耳に痛いことでも、相手国の反応を正確に伝えることは大使の大事な役目だと思うからだ。これでは戦前・戦中の外交官が戦争の回避や戦争の早期終結にまったく寄与できなかった過去の轍を、またまた繰り返すことになろう。メディアも同様だ。
8月24日の国会の領土問題集中論議の中継を見ながら、日本は最も仲良くすべき近隣諸国となかなかうまくやれそうもないな、と絶望的な気分になったことは確かである。
原発世論をまたまた尊重しなかったら、今度こそ怒ろう
この夏を暑苦しくしたもう一つのニュースは、再稼働させた原発をこれからはどうするのか、という問題である。2030年に原発の比率を電力の「0%」にすべきか、「15%」にすべきか、「20~25%」にすべきか、3つの選択肢を示して「国民的な議論」としてきた討論型世論調査の結果などが8月22日に出揃ったのである。
再稼働に反対する官邸前の毎週金曜日のデモは、自然発生的にどんどん膨れ上がり、再稼働こそ阻止できなかったが、野田首相とデモ隊の代表が会談するところまではきた。8月22日に行われた会談は、僅か30分で、それぞれ言い分を述べただけで終わって実りは少なかったが、それでも首相と対話ができたことは一歩前進ではあった。
ところが、この会談に読売新聞が真っ向から異議を唱えた。「原発政策『迎合』で迷走、首相、市民団体と面会、悪い前例作った」と大見出しで報じ、さらに社説でも「禍根残す面会パフォーマンス」と全面否定なのである。
首相は忙しいから誰とでも会うというわけにはいかないだろうが、時間さえあれば反対派であろうが、デモ隊の代表だろうが、「民意を聴く」という意味では歓迎すべきことではなかろうか。それを、真っ向から全否定するとは、メディアとして少しおかしいのではあるまいか。
社説の書き出しは「民主党政権の場当たり的な大衆迎合主義(ポピュリズム)を象徴する出来事と言えよう」となっており、最近の読売新聞は自社の社論と違う意見を「ポピュリズム」と称して切り捨てるケースが増えているような気がしてならない。
もう一つの国民的議論のほうも、3つの選択肢を示して真ん中の「15%」に落とそうと政府は考えていたのかもしれないが、結果はなんと圧倒的に「0%」に意見が集中した。討論型世論調査も、討論ごとに「0%」の比率が高まって、33%、41%、47%と増えていったのだ。意見聴取会の結果も68%が、パブリックコメントにいたっては90%が、という集中ぶりである。
問題は、この結果がこれからのエネルギー政策にそのまま反映するのかどうかである。民主党エネルギー・環境調査会がこの結果をもとに9月8日までに野田内閣に提言を出すことになっているが、国民世論と違う結論を出したら、それはそれであらためて問われることになろう。
というのは、1986年にチェルノブイリ原発事故があり、日本の国民世論も圧倒的に反対意見が多くなったのに、日本の原発政策は推進一色からまったく変わらず、世論と政策が乖離した歴史があるからだ。
ただ、そのときは「日本ではチェルノブイリのような事故は起きない」という原子力関係者の説明を、メディアも国民もある程度、信じていた部分があり、福島事故が起こったあとの現在とでは、まったく様相は違うのだ。
メディアがどう対応するか、原発政策をめぐって主張が二極分化しているメディアの対応を注意深く見守りたい。
シリアでの女性ジャーナリストの戦場死を悼む
最後にもう一つ、シリアの戦場で死亡した女性ジャーナリストの山本美香さん(45)に心からの敬意と弔意を捧げたい。山本さんは「報道で社会は変えられる」と信じて、常に女性や子どもたちといった弱者に目を注ぎ、危険な戦場にも自ら飛び込んでいった人だ。
日本テレビと契約して、取材した映像などを日本テレビに送っていたフリージャーナリストの一人で、そのことを報じた朝日新聞の紙面に「わが社はフリージャーナリストに記事を依頼することはない」と書かれていたのをみて、ちょっと違和感を覚えた。
というのは、ベトナム戦争では危険な戦場に記者を送り込んだ日本の新聞社やテレビ局が、湾岸戦争では各社が談合してバグダッドから記者を引き揚げ、イラク戦争では談合しないでバグダッドから記者の総引き揚げをやったのである。外国の記者や日本のフリージャーナリストは残っていたのに、である。
つまり、日本の新聞社とテレビ局は世界でも珍しい「危険な地域には記者を入れないメディア」になっているのだ。それでいいのだろうか。そのことをあらためて考えさせられた山本さんの戦場死だった。