スタジオジブリの高畑勲監督の名は、盟友宮崎駿監督のように人口に膾炙しているわけではないが、名匠として名高い。14年ぶりの作品『かぐや姫の物語』には予想通り、いやそれ以上に圧倒された(本稿はいわゆる「ネタバレ」も含みますのでご了解ください)。
映画は『竹取物語』の通り、「今は昔、竹取の翁といふものありけり」から始まる。光る竹に鎮座する小さな姫は赤ん坊となり、翁と媼に育てられる。野山を駆け回る少女だったが、都へ出ての栄達を姫の幸せと考えた翁は、村を捨てる。
都では教育係の相模に口うるさく指導される。姫は反抗するがやはり不思議な能力があったのだろう、自然とそれを会得していく。野山での「冬」を見て「春」を待つべくしとやかになり、書や琴、眉を抜きお歯黒を塗る化粧も身につけた。
私は、高畑監督が手がけたテレビシリーズ『アルプスの少女ハイジ』を思い出した。自然児ハイジがアルプスの山から大都会フランクフルトに連れてこられる。教育係はロッテンマイヤー女史。ハイジはその押しつけによって心を病み、結果山に帰ることが出来た。
では、この映画ではどうだろう。姫は裳着の宴での、翁への侮蔑や自分への品評を含む都人の無礼な振る舞いに激怒し、夜の都大路を疾駆する。また現れた求婚者を試すことで人死にが出たことに荒れ狂う。故郷の野山にもはや知人はおらず、帰ることもままならぬ。
姫の感情は次第に沈積していく。「幸せ」とは何なのだろう。「女性」が人として生きることがなぜこんなにつらいのだろう。幼少時に親しかった捨丸との再会で、2人で宙を舞う夢は「こうあったかもしれない」願望なのだ。しかし身分は違い、捨丸も既に妻帯していた。
そのつらさが限界に達したとき、月世界からのお迎えが来てしまった。あれほど地上で生きることがつらかったはずなのに、帰らなくてはならないことに抵抗するかぐや姫。何より、紫の羽衣を掛けられると地上での記憶はなくなってしまう。僅かな時間、翁と媼との別れを惜しむ悲しさ。ハイジのように野山に帰ることはできず、全くの別世界に姫は去っていった。
水彩画や墨絵がそのままアニメーションになったような技術にも目を瞠らされる。動物や子どもの可愛らしさ、四季の山々の美しさはもちろんだが、かぐや姫の躍動感、疾走感は、女性が人として生きるパッションを十分に感じさせた。
思えば、高畑監督は女性の「解放」を多く描いている。先述の『アルプスの少女ハイジ』はもちろんのこと、悪魔の妹・ヒルダが重要な役となるデビュー作『太陽の王子ホルスの大冒険』、モンゴメリ原作のテレビシリーズ『赤毛のアン』などだ。
都と鄙、貴と賤、そして男性原理と女性原理との対比が綾なす物語だが、そこに善と悪はない。人として生きる喜びと、生きられぬつらさが涙を流させ、見終わった後も胸を疼かせる。果たしてかぐや姫は「解放」されたのだろうか。(中津十三)





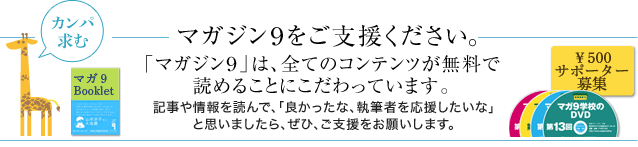

姫の罪と罰は「自分らしく生きること」だったと解釈しました。
自分の美貌でたくさんの貴公子に言い寄られ、帝の寵愛を受けるのは、女の子が憧れる定番のストーリー。
そこに、姫の「元気いっぱいでおてんばな自分らしさ」を加えたら、ちょっと違う輝きのある物語になった。
貧乏人が暮らす山里の生活では姫は生き生きとしていた。
金持ちが暮らす都では、かごの鳥のよう。ストレスのたまる窮屈な生活。
これは物語だから、極端な例だけど、誰しも「自分らしさ」を社会で100%発揮しているとは言い難い。
社会では「自分らしさ」をおさえて生きていかなければならないこともある。
いつでも「自分らしく」生きてはいけない。とはいえ、「自分らしさ」を月の羽衣を着て全部忘れるわけにもいかない。
だから「自分らしさ」を磨いて「社会」に貢献できる方法を探すのが幸せな人生への一歩だと思います。
「自分らしさ」を「社会」に貢献できる方法が「仕事」であれば、最高に幸せな人生だと思います。
そういうケースはまれだけど、絶対無理とも言い切れません。転職しなくても、工夫できることはあるはずです。