その月に書かれた新聞やテレビ、雑誌などから、ジャーナリスト柴田さんが気になったいくつかの事柄を取り上げて、論評していきます。
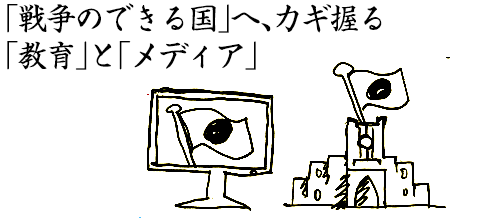
政府が提出を準備している安全保障関連法案について、国会で「戦争法だ」と言った野党議員の発言が波紋を呼んでいるが、安倍政権が進めている政策が、実際に戦争をするかどうかはともかく、日本を「戦争のできる国」へと変えようとしていることは間違いない。
特定秘密保護法の制定に始まって、武器輸出三原則の撤廃、集団的自衛権の行使容認と続いた政策は、憲法9条を実質的に無力化し、自衛隊を世界中のどこへでも派遣して武力行使をできるようにしようとするものであることは確かだからだ。
もちろん政府は、戦争を「する」ためのものではなく、「しない」ための安全保障を高めるためのものだと言っているが、「戦争のできる国」から「する」国への変化が紙一重であることは、世界の歴史が示している。それに、自衛隊が海外の武力行使に参加すること自体が戦争を「する」ということであり、それができるようにする法案に「国際平和支援法」という名をつけたのは、ブラックユーモアであろうか。
戦争の「できる国」から「する国」への変化のカギを握るのは国民の意識であり、政府の指導者が国民をマインド・コントロールできるかどうかにかかっている。戦前の日本が戦争を「する」国に変わっていった歴史をたどってみると、政府がマインド・コントロールの武器として「教育」と「メディア」を使ったことが浮かび上がってくる。
教育のほうは、国定教科書で愛国心を煽り、戦争に反対する学者を大学から追放することから始まって、最後の仕上げともいうべきものとして、「戦う少国民」をつくるためにと小学校を国民学校と名前まで変えたのである。
私はその国民学校に入学し、「撃ちてしやまん」「鬼畜米英」「欲しがりません、勝つまでは」といった軍国教育を実体験し、「日本は神の国だから、最後は神風が吹いて勝つ」と信じていたのだから、完全にマインド・コントロールされていた一人だったのだ。
メディアのほうは、治安維持法や軍機保護法、新聞紙法などによって規制を強めていき、1931年の柳条湖事件が日本軍の謀略による鉄道爆破だとメディアはうすうす知りながら「中国軍によるものだ」という政府の発表をそのまま流して戦意を高揚させ、この事件を発端とした満州事変以降は政府を批判する新聞は一紙もなくなるという状況を生み出した。
新聞が、政治権力を監視する「番犬」ではなく、政府のお先棒を担ぐ「忠犬」に成り果てた姿で、日本のメディアが「死んでしまった」ことが戦争を止められなかった最大の原因だったといわれている。
「国立大学でも国旗・国歌を!」と安倍首相
いま安倍政権が、教育とメディア戦略に異常なほど熱意を込めているように感じるのは、私だけだろうか。教育のほうでは、かねてから愛国心の涵養を指導要領にうたい、国旗や国歌の尊重を文部科学省が奨励しているが、安倍政権になってそれが一層、激しくなった印象がある。
安倍首相は、今月初めの参院予算委員会で「国立大学でも入学式や卒業式で国旗の掲揚や国歌の斉唱を正しく実施されるべきだ」と述べた。下村文部科学相も「各大学で適切な対応がとられるよう要請したい」と語った。文科省がすでに実態調査をしていたことにも驚いたが、86国立大学のうち、先月の卒業式で国旗を掲揚したのが74校、国歌を斉唱したのは14校だったというのである。
国旗・国歌といえば、1999年に「国旗及び国歌に関する法律」が制定されたとき、当時の小渕首相は「国として強制や義務化をすることはない」とはっきり述べていたのに、いつのまにか小中高校では義務化のような状況になってしまった。
とくに、石原慎太郎氏や橋下徹氏のような右翼的な歴史観をもった知事がいた東京都や大阪府では、国歌を歌っているかどうか唇まで監視して、歌っていない教員を処分する騒ぎにまでなっているのである。
天皇陛下が園遊会で東京都の教育委員に「強制しないほうがいいですね」と語ったことさえあった国旗・国歌問題だが、安倍首相は「国立大が税金で賄われているのだから、教育基本法にのっとって実施されるべきだ」というのだから驚く。
まるで、カネを出しているのだから政府の言うことに従え、といわんばかりである。国からの補助金は私立大学にも出ているのだから、私立大学にもやれということなのか。
教育基本法には「国や郷土を愛する態度を養う」という部分もあるが、一方、大学には「自主性、自立性が尊重されなければならない」という部分もあるのだ。予算配分をちらつかせながら、大学にまで言うことをきかそうという姿勢はなんともいただけない。
教科書から従軍慰安婦の記述が消え、竹島や尖閣諸島については日本の固有の領土だと強調するだけの表現が増えているというのも気になる。教科書に政府見解がある場合は必ず入れよと、今回の検定からルールを変えたことも問題だ。教育を通じての国民のマインド・コントロールはすでに始まっているのかもしれない。
一方、メディア戦略のほうは、もっと極端だ。安倍首相の就任以来、メディアのトップと会食を繰り返し、かつてはやらなかった個別インタビューにも応じてメディアへの介入を強めている。
NHKの経営委員に首相の任命権を行使して「政府が右というものを左とは言えない」というような会長をNHKに送り込み、総選挙直前には自民党から主要テレビ局に「公平、中立に」という恫喝ともいうべき要請書を送りつけている。
そしてさらに今月、テレビ朝日の報道ステーションで、コメンテーターの古賀茂明氏が「官邸からバッシングを受け、番組を降ろされた」という趣旨の発言をしたことに対して、NHKのやらせ問題と一緒にテレビ朝日の責任者が自民党から呼び出され、事情聴取されるという「事件」が起きた。
政治権力によるメディアへの明らかな介入であり、テレビ朝日は断ってもよかったと思うのだが、出ていくからには「何を訊かれ、どう答えたか」を国民の前に明らかにすることがメディアとして最低限の義務だろう。事情聴取が非公開で、事後の発表もないとは、どうしたことなのか。
かつてテレビ朝日は、報道局長が民放各社の内輪の会合で「非自民政権の誕生を期待する」と発言したと報じられ、国会に喚問されて平謝りに謝ったことがあった。この時も喚問を拒否するか、あるいは出て行って、内輪の会合でも語ったという番組への政界からの圧力について堂々と語ればよかったのである。
それを「荒唐無稽の発言だった」と平謝りに謝ったため、自民党の「成功体験」となって今回の恫喝にも利用されるという状況になったのだ。放送法の「公平・中立」は、政府への批判や少数意見を放送できるようにするためのものであって、今回のような政権党が個別の番組についてテレビ局を呼びつけるというのは、放送法違反の疑いさえある行為なのである。
新聞は、電波と違って政府の直接の権限は及ばないが、昨年来の朝日新聞の『変調』の陰には安倍政権の介入があったことが次第に明らかになってきつつある(七つ森書館『いいがかり: 原発「吉田調書」記事取り消し事件と朝日新聞の迷走』参照)。
どうやら戦前と同じような「いつか来た道」を歩んでいるような気がしてならない。教育界もメディアも「しっかりせよ!」とあらためて喝を入れたい心境である。
原発のチェックに司法が動き出す?
今月のニュースで注目すべきものに、高浜原発3、4号機の再稼働に福井地裁が差し止めの仮処分を決定したことがある。昨年5月の同じ福井地裁による大飯原発3、4号機の運転差し止め判決に続くものだ。
原発をめぐる裁判は、1973年の伊方原発訴訟以来、数えきれないほどあるが、ほとんど原告敗訴といってよく、原発に対する司法のチェックは、まったくといっていいほど働いてこなかった。それが福島原発事故を招いた遠因だとさえ言われてきたのである。
それだけに、今回の福井地裁の一連の決定は、司法のチェックが働きはじめたのではないか、という期待を抱かせるものだ。
しかも、昨年5月の判決は、上級審で確定するまで効力を発しないが、今回の仮処分の決定は直ちに効力を発揮して、仮処分が取り消されるまで再稼働はできないのである。
それだけに、昨年の判決にはどうせ上級審でひっくり返るさ、と楽観していた原発推進派の人たちも、今度の決定にはあわてたようである。とくに、安倍政権の与党新聞化している読売、産経新聞の反発は激しかった。
読売新聞は1面トップだけでなく、3面も全面使って「科学的知見を否定」「『11月稼働』に暗雲」と大々的に報じたのである。社説でも「規制基準否定した不合理判断」という激しい見出しで「司法への信頼を損ないかねない」とまで論じているのだ。
昨年の判決も今回の仮処分も、同じ裁判官による決定なので、司法が反省したのかも、という推定は早すぎるのかもしれないが、私がそう考えた理由は、その裁判官が昨年の判決後に人事異動になったのに、同じ名古屋高裁の管内移動だったため福井地裁と兼務できたからだ。最高裁が嫌う判決だったらそんな人事異動はしないだろう。
ところが、福井地裁の仮処分決定から僅か1週間後に、鹿児島地裁で川内原発3、4号機に対する再稼働差し止めの仮処分請求を認めない決定が出た。いまだに十数万人の人々が故郷へ帰れないという福島事故をみて、司法が反省したのかもしれないという私の見方は、やはり甘すぎるのかもしれない。
どちらの仮処分にも取り消し請求が出ているので、もうしばらく司法の判断を見守るほかない。とくに、原子力規制委員会の安全審査の基準が甘すぎると判断した福井地裁の決定を、国民の生命、財産を守ることを使命とする司法界全体がどう見るか、注目しよう。
沖縄の知事に、首相や官房長官が会うだけは会ったが…
昨年の沖縄知事選で圧倒的な支持を得て当選した翁長知事に対し、政府・与党の要人が会おうともしない「無視」あるいは「敵視」といってもいい状況が続いていたが、ようやく今月、菅官房長官につづいて安倍首相も会うだけは会った。
しかし、辺野古基地の建設は「粛々と進める」という政府の姿勢はまったく変わらず、「オバマ米大統領に沖縄県民が反対していることを伝えてほしい」という翁長知事の要請に対しても、安倍首相は何も答えなかった。
こうなってはもう沖縄は、日本から離れて「独立」したほうがいいのかもしれない。
朝日新聞社が今月21日に紙面で発表した世論調査によると、普天間基地の辺野古への移設問題に対する安倍政権の対応について、沖縄県民の73%が「評価しない」と答え、「評価する」は18%にすぎなかった。
いや、沖縄県民だけではない。全国でも「評価しない」が55%と、「評価する」の25%を2倍以上も上回っているのだ。一昨年の調査では「評価する」が42%、「評価しない」が33%と、全国では評価するほうが多かったのが、完全に逆転したのである。
沖縄県民の民意を無視する政府の姿勢に、全国民もようやく厳しい目を向け始めたといっていいだろう。今月末の日米首脳会談で安倍首相が沖縄の民意をどう伝えるか、米議会での演説で歴史認識をどう語るかという問題とともに、注目しよう。
沖縄問題について、4月27日の朝日新聞の朝刊を見て驚いたことがあるので、もう一言付け加えたい。朝日新聞は今月から「読者の目線」で報道を点検するパブリック・エディター制度を発足させ、任命した3人の所信表明が載っていたのだが、そのうちの一人、高島肇久氏の意見を呼んで仰天したのである。
高島氏の意見は「読者の目線」ではなく、「政府の目線」そのものなのだ。元NHKキャスターだといっても、その後、外務省の広報官を務めた人だから、そうなるのも当然なのかもしれない。それなら、なぜそういう人を選んだのか、が問題となろう。
「政府のお目付け役」ともいうべき目線で朝日新聞の報道がこれからも『監視』されるのかと思うと、いささか憂鬱な気分にならざるを得ない。





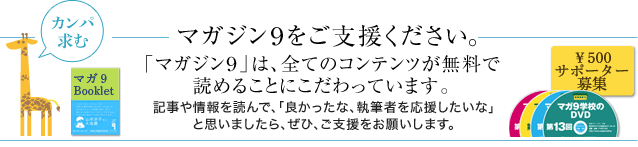


安倍政権が、教育とメディア戦略に「異常なほど熱意を込めている」という柴田さんの指摘、さまざまなニュースから実感させられます。自分たちがやっているのは「正義のための戦争」なのだから、「お国のために身を捧げる」のは当然、それに対して疑問を持ってもなかなか口に出せない――。かつての戦争のとき、社会を覆っていたというそんな空気も、同じようにして少しずつつくられていったのでしょうか。私たちはやっぱり「いつか来た道」を歩んでいたのだ――。そう、後になって気づくことはしたくない、と思います。
「全体主義国家」を歓迎しているかのような風潮は一体どこから来るのか。国民は「思考停止状態」に陥ってしまったか。 権力や支配体制への疑問を一切持たず批判能力を全く失なった国民ばかりになった国は、一体どんな国になるのだろうか」と憲法学者は指摘する。これは想像力がものをいう世界、受験学力で解くのは難しい。 子どもの頃から学校、家庭で「集団」に馴らされ、加えて、物の豊かさは人間から考える力を奪い去った。長寿社会は「孤独」が待ち構えている。それにも気づこうとしないのだ。何処までも「他人依存」なのだ。全ては「集団」を強調してきた教育の成果といえるだろう。土壌改良が進みしっかり「個」が育たない土壌になってしまった。 「個」が強くならなければ「集団」は強くなれない。集団が弱ければ「排外主義」が横行、人に優しくはなれない。この命題は揺るがない。 背筋の伸びた日本人はもはや絶滅危惧種になってしまったか。