マガジン9
憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。
2011-06-22up
イベントレポート:
国際NGOからみた日本復興の課題〜被災地からの報告〜
伊勢崎賢治×篠田英朗
@ジュンク堂難波店
4月24日、大阪・なんばのジュンク堂で、伊勢崎賢治さんの新著『紛争屋の外交論』(NHK新書)の出版記念トークイベントが開催されました。
その1カ月弱前、伊勢崎さんは自身も代表理事を務める平和構築NPO「ピースビルダーズ」の篠田英朗さん(広島大学平和科学研究センター准教授)とともに、東日本大震災の被災地を訪れてきたばかりでした。世界各地の紛争後支援に携わってきた視点から考える、今後の被災地復興に向けての課題とは何だったのか。トークの内容の一部をご紹介します。
※収録にあたり、トーク内容を一部再構成・加筆しています。
住民参加による「復興」を
伊勢崎賢治さん
いせざき・けんじ●1957年東京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東京外国語大学大学院「平和構築・紛争予防講座」担当教授。インド・スラムの住民運動を組織した後、アフリカで開発援助に携わる。国連幹部や日本政府特別代表として、アフガニスタンなど紛争地各地で武装解除を指揮。著書に『武装解除』(講談社現代新書)、『伊勢崎賢治の平和構築ゼミ』(大月出版)、『国際貢献のウソ』(ちくまプリマー新書)、『紛争屋の外交論』(NHK出版新書)など多数。
■それでも「人間」は復興する
僕の専門は「戦後復興」ですが、これまで直接的、間接的に関わってきた中には、戦争と災害の両方にダブルパンチで襲われた地域があります。ミンダナオ沖の地震で津波が起こり、20万人が犠牲になったインドネシアのアチェ、それから人口400万人程度という小さな国ながら、地震で30万もの人が亡くなったハイチなどがそうですね。
これらの国々の状況と、日本の今の状況を単純に比較することは非常に難しい。しかし、そうした国々は、そもそも内戦などでずっと政府がよれよれで、無政府状態が続いていた。そこに災害が起こって、社会が全部壊されるわけです。復興が始まっても、内戦の火種がくすぶっている。復興の困難さから言うと、今回の震災の比ではありません。
それでも、「人間」は復興するのです。そこへ国連をはじめとする国際社会が「新しい国づくりをしよう」と殺到するわけですが、僕たちはそういう極限の状況でも人間の底力を見せつけられます。社会が焦土と化しても、瓦礫から、難民キャンプから、細々ではあるけど、社会活動が始まるのです。日用品の単純な売買みたいな経済活動も。瓦礫を再利用しての建設業も。「焼け跡」経済です。
ましてや日本人です。政府がアホでも、無政府状態でも、日本人は自力で復興するに決まっています。だから、東北の復興そのものは心配する必要ない。問題は、復興のやり方によってもたらされる国のあり方の変化です。
不謹慎だという誹りを恐れずに敢えて言わせていただくと、大災害は国家体制を根底から変革する大きな「チャンス」でもある。少なくとも、復興を部外者として支援する国際社会は常にそのように考え、「介入」します。アメリカなんかは、彼らの都合の良い政権づくりのために「民主化」を掲げます。いまだ迷走するイラクやアフガニスタンがよい例ですね。一番うまくいったのは、農地解放までやった日本の戦後(占領)復興でしょう。
国連、世銀など、いわゆる国際社会が関わるケースでも基本的には同じです。国際支援をする引き換えに、さまざまな改革の要求を現地政府、もしくは社会に対して、半ば強制的にする。「小さな政府」や「地方分権」なんかは、国際社会が強要する要求の定番です。
政府というのは、どこでも改革に抵抗を示すし、「内政干渉」を楯に拒否したりする。しかしそこで手間取っているうちは、地方の復興もままならない。ということで、中央政府をバイパスして、復興資金を直接「地方」に届けるということを模索し始める。地方政府も中央政府と同じように硬直化しているから、県より町、町より村といった具合に、国際社会は、できるだけ住民に近い行政単位を復興の主体と見なしたいわけです。
それでも、やっぱり行政単位は「役所」だから旧態依然としている。そこで、市民社会の代表である地元のNGOやNPOを復興資金運用の主体にするのも一般的です。そして、コミュニティ・エンパワーメントと称して、地元社会に復興開発を担う住民組織を、それまでの地元の慣習を全く無視して、新設する事もある。もちろん、復興資金運用のノウハウも同時に短期間に住民に教え込んでいくわけです。
これらの「介入」に国際社会が正当性を見出すのは、住民が出来るだけ自分たちに身近な組織を通じて主体的に開発に直接参加し、NGOやNPOの市民社会が隆盛し、その結果、政府が小さくなるのは良いことだ、と信じるからです。当然、中央政府は面白くありません。大変な摩擦が起きます。それでも、国際社会は、援助を楯にして、その要求を呑ませる。
こういうストーリーは国際協力のお話で、自力で復興できる日本には直接当てはめることには無理があります。しかし、ちょっと無理な設定ですが、仮に日本が被援助国だとして、現在の日本政府のテイタラクを見たら、国際社会は、このストーリーのように、日本政府をバイパスする道を選んでいたでしょう。
■必要なのはボランティアより「住民参加」という「自己責任」
もうすでに遅すぎるのかもしれませんが、それでもこれからでも、復興財源を象徴縦割りではなく一元化する努力はするべきだと思います。今お話ししたような国際開発の手法では、一元化した予算を、より住民に近い組織単位に丸投げし、どう使うかの優先順位も予算配分もそこで決めさせる。地域の小学校や診療所などの公共インフラの復興にまで、この手法でやっちゃいます。中央省庁が介入するとしたら、そういう組織単位を横断する基幹インフラを扱う時の、該当する組織単位間の調整とか、国レベルでの制度との整合性の指導ぐらい。
こういう考え方を日本でやるとしたら、一番分かりやすいのは仮設住宅建設でしょう。周知の通り日本には「プレハブ建築協会」という大手企業の談合組織の社団法人があって、そこが国から一手に仮設の発注を受けるという「仮設業界」が出来上がっています。平常時でさえ汚職、談合が多くささやかれる建設業界です。その灰色度は推して知るべしです。
震災後の「住まい」の復興という視点から見ると、仮設はそのためのオプションの一つでしかないはずです。建設地確保の遅れ、それと入居がきまっても未入居を続ける被災者が続出する現在、被災地域によって異なるニーズに、こういう中央集権的なアプローチではついていけません。一戸270万円から400万円――この辺がまた灰色なんですが――といわれる仮設住宅は、役目が終われば取り壊される「公共施設」です。ムダと言えばムダな出費と言えなくもない。なぜこの予算の一部を「常設」に使えないのか。個人家屋の修理や自力建設――例えば地元の大工さんの手で瓦礫を再利用しての――、そしてちゃんとルールをつくって新しい住宅ローンの補助にするのもいい。こういう采配は、仮設が公共物として国交省や厚労省によって縦割り予算化されている限り、無理です。だから、予算の一元化と地元の采配の強化が必要なのです。
公的資金を使ってそうした自力建設・修理を行ったあと、瑕疵担保責任や何らか事故が起こった場合の賠償責任はどうするのか、とかいう議論があるでしょう。こういう平常時の議論を持ち込むと全てが硬直化します。復興は非常事態なのです。「住民参加」とは一つのリスクであり、それでもそれを現場特有のニーズに合ったスピードある復興のために必要とするならば、「住民参加」とは「自己責任」なのです。
被災者への同情から、「自己責任」なんて、という向きもあるでしょう。日本人として僕も、とても被災者にそれを面と向かっては言えません。しかし、事実として、国際援助の現場では、日本よりもさらに悲惨な目にあった人たちに、「自分の足で立て」と復興への参加を迫るのです。それを援助の、冷たいプロフェッショナリズムと捉えるからです。
また、もう一つ指摘しておきたいのが「ボランティア」の存在についてです。国際協力の世界では、ボランティアの派遣も、本当に緊急で現地に存在しない専門性のあるケース以外は、自粛します。住民の就労機会を損なうからです。ボランティアよりも、まず、Cash for workを前提に考える。
「復興」とは、一言で言えばいかに被災者の貨幣経済への復帰を図るかということです。つまり、被災者とそれを取り巻くコミュニティに、どうやって早期に経済活動を取り戻させるか。最初に言ったように、どんな悲惨な被災状況にあっても、ものの売買といった「民衆経済」は必ず出現します。そしてそれが、後の「上」からの復興政策を底辺から支えるんです。国際支援の現場はそれを経験値として知っているから、かつて僕が経験した東ティモール復興のケースでは、貨幣をヘリコプターから落とすということまで行われたくらいです。
日本ではさすがにそれはできませんが、被災者が避難所で炊き出しの列に並び続けるのでなく、お金を持って被災を免れたコンビニに買い物に行ける状況――もちろん、物理的に不可能な地域はあっても――をいかに早くつくるかが問われるのは同じです。これは、被災者自身の勤労意欲創出のきっかけをつくるという意味で、すごく意味のあること。そしてそれが、経済復興のもっとも根本的な土台になるのです。
そのためには、例えば被災者の中で身体を動かせる人を、一時的に準公務員扱いにして、日当を払って自身に瓦礫処理などに従事してもらう。これがCash for workです。現金が手に入れば、被災者自身が自分の意思で、どんな小さいものでも経済活動をはじめる、その「芽」が生まれるんです。
今回の震災についても、もうそろそろこういう視点に立って被害者の未来を考える時期なのではないか。原発被害という特殊性のある福島は別にして、もうそろそろ被災者自身の間から、「被災者根性は止めよう」という声が出てくるのではないかと僕は思います。
こうしたことも含めて、とにかく復興予算の配分と運用は地元の采配に委ねる。アカウンタビリティなんてどうでもいいのです。緊急時なのです。一方で予算を一元化するために、中央に「復興庁」をつくるなんて愚の骨頂です。関東大震災の時の後藤新平の功績を例にとる人もいますが、時代錯誤も甚だしい。必要なのは、平常時の規制、慣習、そしてアカウンタビリティを全て取っ払い、公的資金を地元、それも県行政ではなく、市でもなく、もっともっと個々の住民に近い復興主体に丸投げする一大政治決定です。予算の一元化とは、権力の一元化ではありません。その逆です。
■「とどまる」選択をした人たちへの支援を
さて、僕は4月のはじめに約1週間、篠田さんとともに被災地を訪れました。主な行き先は福島。放射能の影響下で、どうやったら民間援助団体が活動できるのかを線量計片手に調査することが目的だったんです。
原発に近い地域については、援助を考えるよりも避難させるべきだという意見を持つ人もいるでしょう。僕自身もそこに住む人たちが、必ずしもとどまるほうがいい、とどまるべきだと思っているわけではありません。僕自身も住民だったら避難を考えるだろうし、放射能の影響が出やすい小さい子どもなどがいればなおさらです。ただ、そこで忘れたくないのは、危険性を十分に理解した上でも、そこに「とどまる」選択をする人は絶対にいるだろう、ということなのです。
僕がこう考えるのは、紛争の現場における「難民」の問題をいくつも見てきたからだと思います。紛争や内戦が起こると、国内避難民も含めて必ず周辺の国や地域に大量の難民が発生します。しかし、すべての人が難民となって避難しているのかといえば、そんなことはない。どんなに戦火が激しくなっても、死と隣り合わせで、そこにとどまる選択をする人たちが必ず存在する。僕は職業柄、そっちの方の人々が気になるし、気にしたいんです。
戦火の中に留まる選択をした人々の中には、安全を保障する政府が既に崩壊してしまっているので、自らを、そして家族を護る為に武器を持つという人も出てくるでしょう。それを考えると、もし福島で留まる選択をした人を支援するとしたら、個人個人が被爆線量をきめ細かく管理できる体制を整えることが、政府というより社会がやるべきことなのではないかと思います。具体的には、個人線量計の配布と、その使用の管理支援ということでしょうか。
繰り返しますが、これは別に放射能の危険の中で生活することを奨励するということでも、放射能の危険を過小評価するということでもないのです。戦火の中に留まる選択をした人に銃を託すのと同じ「悲壮感」で、日本人が福島県民に線量計を託すということなのです。この「悲壮感」が共有されないのなら、止めた方がいい。とにかく、東京電力と政府の責任を追及し、最大限の補償を「放射能難民」のために引き出す支援だけに徹した方がいい。
でも、僕はそういう「悲壮感」が共有されるような形で福島と関わりたい。それができれば、一部で報道されている、福島から避難してきた人たちがホテルで宿泊を拒否されるような、日本人として本当に恥ずかしい「風評差別」に対処できると思うのです。
失われたコミュニティを、どう再建するか
篠田英朗さん
しのだ・ひであき●1968年生まれ。広島大学平和科学研究センター准教授。学生時代から難民救援活動に従事し、イランやソマリアでの短期ボランティアを体験。国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の投票所責任者も務めた後、ロンドン大学(LSE)で国際関係学博士号を取得。主な著書に『平和構築と法の支配:国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社)、『日の丸とボランティア:24歳のカンボジアPKO要員』(文藝春秋)、『紛争と人間の安全保障:新しい平和構築のアプローチを求めて』(国際書院、共著)など。
■破壊されてしまった町を、どう取り戻すのか
私の専門分野は、伊勢崎さんと同じく「平和構築」。紛争が終わった後の社会に平和をつくるために何が必要なのか、を考える学問です。研究者ですが、その研究の性格上、アフリカの紛争地などにもしばしば足を運んできました。
なぜそういう人間が、今回の東日本大震災の支援に関わっているのか。私は以前から、現地の人々とともに平和構築を考えようというNGO「ピースビルダーズ」を運営してきました。今回の大震災も、社会が大きく破壊されてしまったということで、私たちがこれまで見てきた戦後復興のケースと同じような性格の問題があるかもしれない。であれば、私たち平和構築を専門にしている人間の考えや活動が役立つことが少しでもあるのではないか。そう思って、他のNGOなどとも協力しながら、支援活動を始めたわけです。
4月のはじめには実際に被災地を訪れましたが、そのときの印象も、私たちが通常平和構築研究の対象にしているアフリカなどの状況と、もちろん違うところもあるけれど似ているところもたくさんあるというものでした。もっとも顕著な共通性は、一つの町――あるいは村とか集落と言い換えてもいいですが――我々が「コミュニティ」と呼んでいるものが、まるまる破壊されて、消えてしまったことだと思います。
水、食糧などライフラインにつながる支援の段階の次には、その「コミュニティ」を再興するということを考えなくてはなりません。あれだけ破壊された町を取り戻すのはもう無理なんじゃないかという雰囲気もあるけれど、生き残った方々もいる以上、やはり何らかのコミュニティはできなくてはならない。ただ、以前とまったく同じものができるかどうかはわからないし、そうするのがいいとも素朴には言えませんよね。
本来、被災地への支援を進めるにあたっては、そういう大きな問題を話し合ってから進めていかなくてはならないはずなんですが、政府は残念ながら議論にばかり――というよりは、議論の場を「つくる」ことにだけ熱心なように見えます。もっとスピーディに意見や知恵を出し合っていかないと、支援のあり方も定まらないのではないでしょうか。
私は今、広島で仕事をしていますが、ご存じのとおり広島はかつて原爆で焼け野原になりました。生き残った方々の中にも「もうここには住みたくない」といって離れられた方もいますし、復興の段階でも、「焼け野原になってしまったところにまた町をつくるより、20キロくらい離れたところに『新広島』をつくったらどうか」という意見もあったそうです。
でも、そうして議論をする中で、やはり広島というその場所に再び町をつくることに意味があるのではないか、という結論になった。多くの人にとって先祖から受け継いだ土地であるということ、そしてもっと大きな哲学的な意味も含めて、です。軍国主義と決別した新しい日本の象徴という役割を果たすために、焼け野原になってしまった町をつくり直す。戦後66年経った今の広島を見れば、その試みはとりあえず成功したと言える部分もあるのではないかと思います。
今回の震災も同じで、コミュニティ単位、町単位で新しくものごとをつくり直していかなくてはいけない。それは、阪神・淡路大震災のときにも相当程度迫られていた挑戦だけれど、今回の大震災ではさらに顕著な形で大きな課題が突きつけられている。それは外から見ている人間にとってもそうですし、現場に行くと、被災した皆さんがそのことをすごく悩まれているのをすごく強く感じます。
一度破壊されてしまった町を、どういうふうにつくり変えていくのか。それは、気の遠くなるような大きな課題ですが、我々がこうして生きている以上、そして生き続けるためには考え続けなくてはいけないのだと思います。
■ふるさとへの誇りを失わせない
「ピースビルダーズ」では今、岩手県沿岸部と福島県南相馬市を中心とした支援を行っています。国際支援の現場でも、援助はまず戦争が起こった国の首都やその周辺の、報道が入りやすい場所に集中するということが多いんですが、今回の震災でも、大規模な緊急援助は宮城県、それも仙台が中心になることが多かった。そこで私たちは、その「穴埋め」的なニーズに応えよう、と考えたわけです。
伊勢崎さんと2人で現地を訪れたときは、福島市内から車で海岸沿いへ向かって、一部が福島第一原発20キロ圏内に含まれる南相馬市へ入りました。ずっとガイガーカウンターで放射線を測定しながら進んだのですが、そのとき感じたのは、原発から距離が近いほど線量が高いというわけではないということです。もちろん、爆発のときにはやはり近い場所ほど危険ですが、その後は風向きや地形によって放射性物質が溜まりやすいところと溜まりにくいところが出てくる。例えば、内陸の福島市でも、場所によってはむしろ南相馬市より値の高いところがありました。考えてみれば当然ですが、放射性物質が10キロ、20キロといった線に沿って広がるわけはないんですよね。
それでも、政府の「偉い人」たちは、地図の上にコンパスで円を描くようにして、10キロ圏内、20キロ圏内といったカテゴリーで退避などの指示を出します。私たちにしてもずっとそういう言葉を耳にしているうちに「20キロ圏外と圏内だと危険性が大きく違う」ような気がしてくる。でもそれは、現地に暮らす人たちにとっては、「隣の山田さんちは20キロ圏外で大丈夫なのに、うちは立ち入り禁止になっちゃった」ということ。一夜にしてコミュニティが分断される事態でもあるんです。そうした、10キロ、20キロという境界線が持つ危うさと、「圏外と言ったって隣のうちじゃないか」という日常的な感覚をどう折り合わせていくのかということを、しっかりと考えないといけないと感じました。
また、「コミュニティ再建」という課題は被災地全体に共通するものですが、福島県の場合はかなり複雑な、特殊な状況があります。例えば東京でも、福島ナンバーの車を駐車場に入れたら両隣には誰も車を駐めなかったとか、インターチェンジで立ち寄り拒否されたとか、そういう悪い冗談みたいなことも起こっていると聞きます。ふるさとの窮地を何とかしたいと思う前に、まずそのふるさとに誇りを持てないというような状況ができてしまっているわけです。
でも、まずは自分のコミュニティに誇りを持ってもらわないと、再建もへったくれもない。だから、福島の人たちが誇りを持って「福島人」として生きていけるような、精神的な面も含めた支援をこれからやっていきたいと考えています。その一環として、「我福島人」ポロシャツの作成・販売も開始しました。物資支援だけではなくて、県外に「福島サポーターズ」のようなものをつくって、みんな福島に頑張ってほしい、立ち上がってほしいと思ってるよ、という直接的なメッセージを届けることも必要なのかな、と思っています。
■日本で今「難民問題」が起こっている
先ほど伊勢崎さんが「難民」の話をされましたが、「難民」とは「戦争などで自分が住んでいた場所にいられなくなって逃げ出したり、無理矢理追い出されたりした人たち」のこと。そう考えると、放射能被害で地元を離れざるを得なくなった福島の人たちは明らかに「難民」なんです。国境を越えているわけではありませんから、もう少し専門的な言葉で言えば「国内避難民」ですね。
「ピースビルダーズ」では、アフリカなどで平和構築に携わりたいという日本人、アジア人への研修事業を実施しているのですが、そこでも「数万人の国内避難民が出た場合はどうするか」といったシミュレーションを以前からやっていました。まさにそれが今、日本で起こっているという感じがしています。つまり、アフリカで起こっているのと同じような、深刻な人権侵害である国内避難民の問題が今、日本にあるんだということ。言葉のマジックというか、日本人に対しては「難民」「国内避難民」という言葉を誰も使いませんが、実際にはこれはそういうレベルの問題なんだと捉えなくてはならない。
もちろん、毎日の食糧がきちんとあるかとか、そういうことは重要です。でも、それを超えた人間の尊厳、住民の人権をどう守っていくのかということも、絶対に考えていかなくてはならない。もっと、これは人権問題なんだという視点で議論していく必要があるのではないでしょうか。
震災から3ヶ月以上が経ちましたが、
被災地の復興はまだまだこれからの「長期戦」。
そして原発事故の被害は、いまだ進行形で広がり続けています。
さまざまな角度からの、多面的な議論が必要だと改めて感じます。
***

【読者プレゼント】
伊勢崎さんの新刊『紛争屋の外交論-ニッポンの出口戦略』を、
3名の方にプレゼントいたします。
ご希望の方はメールフォームより、記事名「読者プレゼント」をお選びのうえ、
件名を「伊勢崎賢治さんの本希望」としてお送りください。
記事へのご意見、ご感想もお待ちしています。
※申し込み締め切りは6月29日(水)です。
当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
協力:NHK出版(伊勢崎さんのインタビュー記事が読めます)
***
マガ9のメルマガ

↑メールアドレスを入力して、ぜひ『メルマガ9』にご登録ください。毎週、更新ニュースを送らせていただきます。/Powered by まぐまぐ
登録解除はこちらから↓
マガ9対談
「マガ9」コンテンツ
- 立憲政治の道しるべ/南部義典
- おしどりマコ・ケンの「脱ってみる?」
- 川口創弁護士の「憲法はこう使え!」
- 中島岳志の「希望は商店街!」
- 伊藤真の「けんぽう手習い塾」リターンズ
- B級記者、どん・わんたろう
- 伊勢崎賢治の平和構築ゼミ
- 雨宮処凛がゆく!
- 松本哉の「のびのび大作戦」
- 鈴木邦男の「愛国問答」
- 柴田鉄治のメディア時評
- 岡留安則の『癒しの島・沖縄の深層』
- 畠山理仁の「永田町記者会見日記」
- 時々お散歩日記
- キム・ソンハの「パンにハムをはさむニダ」
- kanataの「コスタリカ通信」
- 森永卓郎の戦争と平和講座
- 40歳からの機動戦士ガンダム
- 「沖縄」に訊く
- この人に聞きたい
- ぼくらのリアル★ピース
- マガ9対談
- 世界から見たニッポン
- マガ9スポーツコラム
- マガ9レビュー
- みんなのレポート
- みんなのこえ
- マガ9アーカイブス
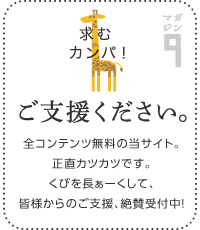

 川口創さん×
川口創さん× 愚安亭遊佐さん×
愚安亭遊佐さん× 中島岳志さん×
中島岳志さん× 雨宮処凛さん×
雨宮処凛さん× 雨宮処凛さん×
雨宮処凛さん× 中島岳志さん×
中島岳志さん× 伊藤真さん×
伊藤真さん× 鈴木邦男さん×
鈴木邦男さん× 蓮池透さん××
蓮池透さん×× 堤未果さん×
堤未果さん× 伊勢崎賢治さん×
伊勢崎賢治さん× 雨宮処凜さん×
雨宮処凜さん×